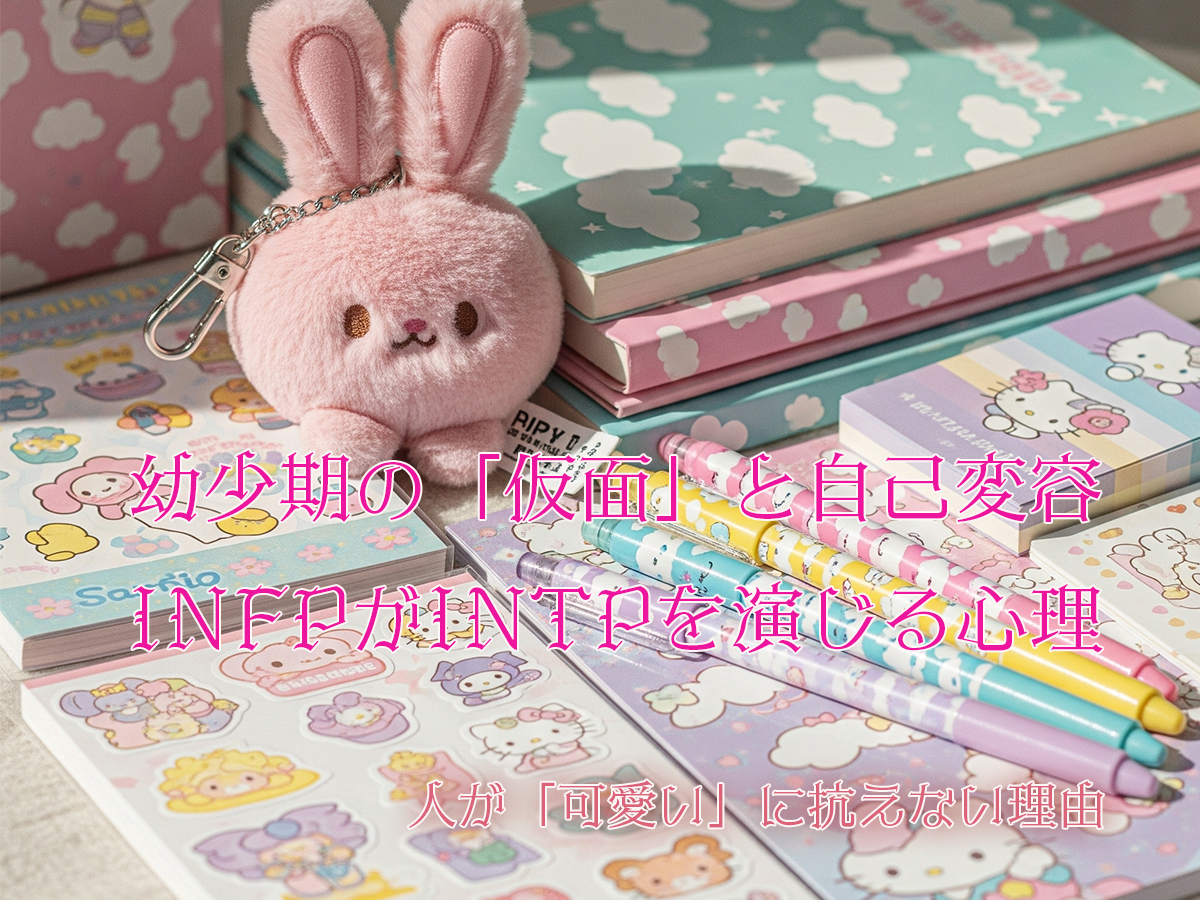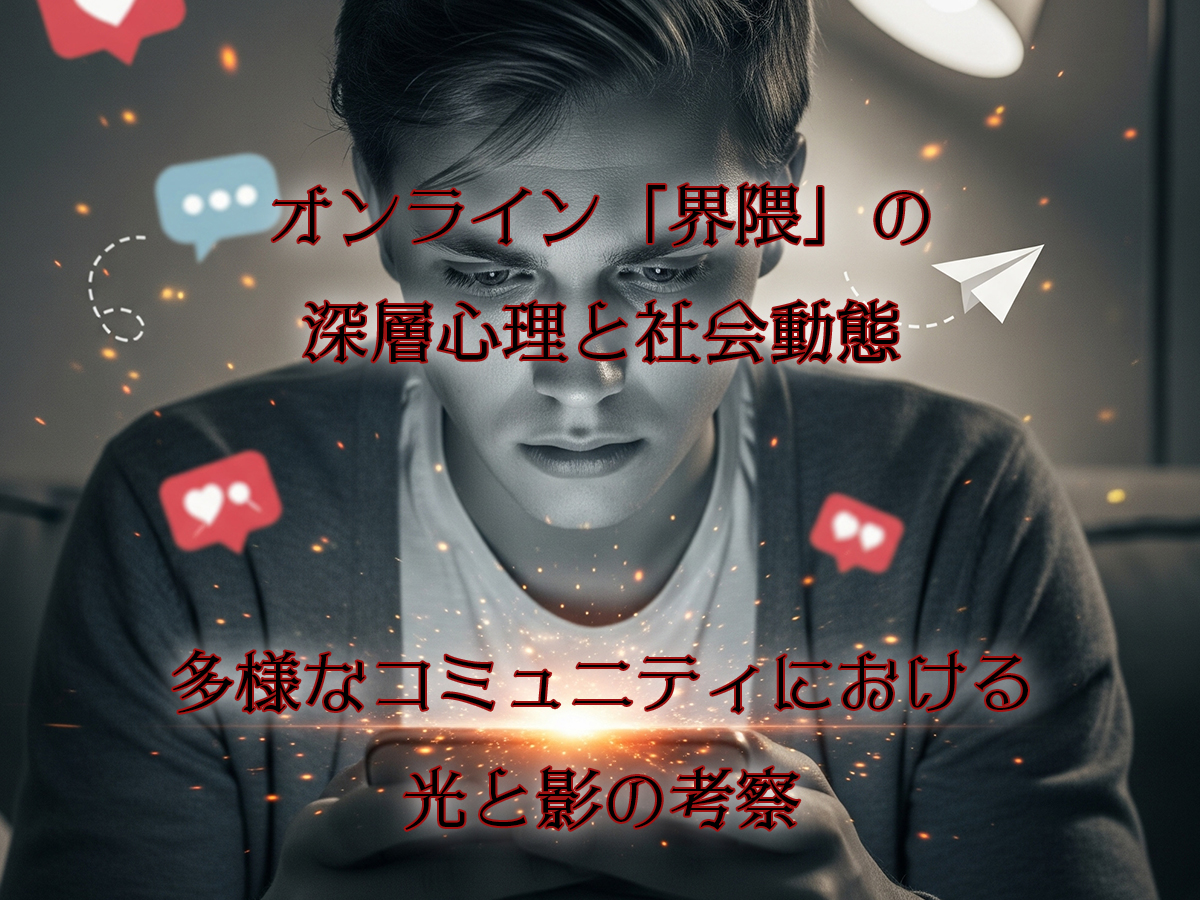はじめに:MBTIと自己理解の狭間
人は皆、様々な側面を持ち合わせているものです。特に、MBTIなどの性格診断ツールは自己理解のきっかけとなり得ますが、時にその分類が現実の複雑さを捉えきれないこともあります。ある男性が、自身の幼少期の経験と向き合う中で、本来の「INFP」としての性質を抑圧し、「INTP」の仮面を被っていたと語っています。彼の体験は、心的外傷がいかに個人の性格形成に影響を与え、そして自己変容へと導くのかを示唆しています。
MBTI(Myers-Briggs Type Indicator:マイヤーズ=ブリッグス・タイプ指標)は、個人の性格を理解する為のツールとして世界中で広く使われています。
ユングのタイプ論に基づいて開発され、人がどのように外界を認識し、意思決定をするかという心の傾向を16種類のタイプに分類します。MBTIは診断テストではなく「自己理解の為の指標」として用いられるのが特徴です。MBTIを構成する4つの指標
MBTIは、以下の4つの二者択一の指標の組み合わせで性格タイプを決定します。
- 外界へのエネルギーの方向(心の利き手):
- E(外向:Extraversion):人や物との交流を通じてエネルギーを得る
- I(内向:Introversion):内省や思考を通じてエネルギーを得る
- 情報収集の方法(ものの見方):
- S(感覚:Sensing):五感を通じて具体的な情報や事実を重視する
- N(直感:Intuition):パターンや可能性、抽象的な概念を重視する
- 意思決定の方法(判断の仕方):
- T(思考:Thinking):客観的な論理や分析に基づいて判断する
- F(感情:Feeling):人間関係の調和や個人の価値観に基づいて判断する
- 外界への接し方(ライフスタイル):
- J(判断:Judging):計画的で秩序を好み、結論を急ぐ
- P(知覚:Perceiving):柔軟で自発的、臨機応変に対応する
これらの組み合わせによって、例えばINTPやINFPといった16種類の性格タイプが導き出されます。
INTP(論理的な思考者):革新的なアイデアの源

INTPは「内向」「直感」「思考」「知覚」の組み合わせで構成されるタイプです。その特徴は、論理的で分析的、そして探求心旺盛な思考にあります。
主な特徴
- 論理的で分析的:
物事を客観的に捉え、筋道を立てて考えることを得意とします。複雑な問題も細かく分解し、本質を見抜こうとします。 - 知的好奇心旺盛:
常に新しい知識やアイデアを求め、興味のある分野には深く没頭します。探求心が強く、未解明なことや理論的な課題に魅力を感じます。 - 独立心が強い:
自分の考えや判断を尊重し、他人に流されることを好みません。単独で思考を深める時間を大切にします。 - 柔軟で適応性がある:
計画に固執せず、状況に応じて柔軟にアプローチを変えることが出来ます。束縛を嫌い、自由な発想を大切にします。 - 内省的で控えめ:
感情を表に出すことは少なく、内に秘める傾向があります。人間関係では、広く浅くよりも、深く理解し合える少数の関係を好みます。 - 発明家肌:
既存の枠に囚われない独自の視点を持ち、革新的なアイデアを生み出す才能があります。
INTPは、科学者、哲学者、プログラマー、研究者等、論理的思考と独立した探求が求められる分野でその才能を発揮することが多いと言われています。
INFP(理想主義的な仲介者):共感と創造性の担い手

INFPは「内向」「直感」「感情」「知覚」の組み合わせで構成されるタイプです。その特徴は、深い共感力、強い価値観、そして豊かな想像力にあります。
主な特徴
- 共感力が高い:
他者の感情や内面に深く寄り添うことが出来ます。感受性が豊かで、困っている人や社会的な弱者に心を寄せます。 - 理想主義的で独自の価値観を持つ:
自分自身の内面にある価値観や信念を非常に大切にします。理想を追求し、世の中をより良くしたいという思いが強いです。 - 創造的で想像力豊か:
豊かな想像力を持ち、芸術的な表現や独自のアイデアを生み出すことに長けています。文学、音楽、美術等の分野に惹かれることが多いです。 - 柔軟で適応性がある:
計画通りに進めるよりも、心の赴くままに動くことを好みます。変化にも比較的柔軟に対応出来ます。 - 内省的で思慮深い:
自分自身の内面と向き合う時間を重視し、自己理解を深めようとします。感情を内に秘める傾向があります。 - 調和を重んじる:
対立を嫌い、平和で穏やかな関係を築くことを望みます。他者との心の繋がりを大切にします。
INFPは、作家、カウンセラー、芸術家、教師、社会活動家等、共感力や創造性、そして人の成長に関わる分野で活躍することが多いと言われています。
「INTPの仮面」が生まれた理由:機能不全家庭と防衛反応
彼がINFPでありながらINTPの仮面を被っていたのには、主に二つの理由が挙げられます。
1. INFP的感性を発揮する機会の喪失

劣悪な家庭環境、いわゆる機能不全家庭で育った彼は、自身のINFP的な感受性を自由に表現することが出来ませんでした。例えば、美しいものに感動しても、それを言葉にすれば親の不機嫌を招くといった経験が、感情を抑圧する習慣を形成したのです。(人格形成としてナルシスティック・レイジになりやすい)
このような環境下で生き抜く為に、彼は徹底的に論理的な思考を研ぎ澄ませました。「親がどんな時に機嫌を損ねるのか」「どうすれば安全か」といった問題を、まるで詰将棋のように分析し、合理的に対処する能力を発達させていきました。INFPの持つフワフワとした感性は封印され、その代わりに、客観的で冷静なINTP的な思考パターンが強く表れるようになったのです。当時のMBTI診断でINTPと診断されたのも、この後天的な傾向を反映していたと考えられます。
2. 感情を殺し、理論で武装する自己防衛
また、あまりにも辛い現実から心を守る為の防衛反応も、INTPの仮面を形成する要因となりました。INFPの豊かな感性で苦痛をそのまま感じてしまえば、精神的に破綻してしまう。そうならない為に、彼は意図的に感情を凍らせ、外界の出来事を「現象」「情報」として淡々と分析するようになりました。
例えば、虐待されている状況を「客観的な事実」として捉え、感情的な痛みから距離を置く。毒親に関する専門知識を収集し、自己の状況を「愛着障害」や「機能不全家庭」といった理論的な枠組みで理解しようと試みたのです。この徹底した感情の排除と理論武装によって、彼は自身を感情を持たないロボットのように認識するようになっていきました。
隠された感情と身体のSOS:仮面の代償
しかし、感情を抑圧しても、心の傷は消えるわけではありません。この男性は、自身では気付かないうちに潜在意識下で心的外傷が重症化していったと語っています。その結果、原因不明の慢性的な体調不良や強い希死念慮に苦しむようになりました。これは、心が発するSOSであり、凍結された感情が身体を通じて訴えかけていたサインだったのかもしれません。
また、彼の身体的特徴(体毛の濃さや若年性脱毛症)と内面さとの矛盾が、彼が「男になれなかった」と語る性自認の混乱と矛盾している点も指摘されています。これは、心と身体の乖離、そして幼少期のトラウマが引き起こす複雑なホルモンバランスの乱れの可能性を示唆しています。自身の身体が「男らしい男」を表現しつつも、内面では「男ではない」感覚や「女児的な自分」が存在するという彼の葛藤は、幼少期の極度のストレスが性的な発達に与えた影響と深く関係しているのかもしれません。
INFPへの「回帰」:自己探求と感情の再接続
長年の苦悩と不調を経て、この男性は再びINFPとしての気質を取り戻す道程を辿りました。
彼は、自身の状態を理解する為に、愛着障害、アダルトチルドレン、毒親、発達障害等、様々な心理学的・精神医学的な分野を徹底的に探求しました。この論理的な自己探求の過程で、彼は自身の潜在意識に抑圧されていたトラウマや感情に「直感的に」気付くことになります。
「僕のINTP的な理論偏重は、辛すぎる体験を抑圧し、現実から逃避する為だった」「僕はロボットのような人間だと思っていたが、それは防衛反応で感情スイッチがOFFになっていただけで、本来は非常にエモーショナルな人間だった」
――この気付きは、彼が長年被っていた仮面を脱ぎ捨て、本来の自己と再接続する転換点となりました。そして、感情を受け入れ、本来の自分へと回帰する中で、MBTI診断の結果もINFPへと変化したのです。
「可愛い」への純粋な欲求とジェンダーの曖昧さ
この男性の内面には、「男ではない感覚」「自分の中に女児がいる感覚」があり、サンリオや女児的な配色の雑貨、少女漫画等を好むという特徴が指摘されています。これは、既存のジェンダーの枠組みに囚われない、彼独自の感受性の表れであり、「可愛いは正義」という純粋な欲求が根底にあると推察されます。(※前世の影響もあると思いますが)
「女性と純粋に仲良く喋りたい」という願望も、一般的な男性の性的な欲求とは異なり、彼自身の性自認の曖昧さから来るものかもしれません。性行為における興奮の欠如は、彼が自身のセクシュアリティを「アセクシャル」「ノンバイナリー」と疑う原因ともなりましたが、彼自身は、過剰なストレスによるホルモンバランスの乱れが、彼を「男になれなかった」「無性のまま成人した」状態にしたのではないかと考察しています。この自己認識は、彼が長年抱えてきた「異常性」への苦悩に、一つの説明を与え、胸のつかえを解消するきっかけとなったようです。
一応、理論偏重な面が強いと「男性性」優位かなとは思うのですが魂自体はまだまだ幼く、小さな子供のままなのかもしれません。子供でも肉体が成人になればちょっと第三者目線で見ると大変ですが(^_^;)
複雑な自己と、その先へ
この男性の体験は、人間の内面がいかに複雑で多層的であるかを物語っています。この男性は日頃、自身の本当の姿を隠したい願望から出来上がってしまった、彼の癖になっている「作り話」の中に「本音」が混じるという言動も、長年のトラウマから培われた自己防衛機制の表れであり、真実を語ることへの慎重さが伺えます。しかし、同時に、自身の苦悩や気付きを言語化し、発信しようとする姿勢は、自己理解と回復への強い意志を示しています。
INTPとしての論理的な探求を経て、INFPとしての感受性を再獲得した彼の経験は、困難な過去を乗り越え、自己を統合しようとする人間の可能性を示唆しています。この「理論と感性の融合」こそが、彼独自の強みとなり、今後の人生を豊かにする力となるでしょう。彼は「何者にもなれない」と語りますが、むしろその複雑な内面こそが、彼を唯一無二の存在たらしめているのです。
「恋が出来ない」という言葉の裏側にあるもの
男性はぽつりぽつりと「恋愛しづらい」と語っていました。
まず、「恋が出来ない」という言葉は、彼にとっての強い自己防衛であり、同時に諦めや諦念の表れだと考えられます。過去の経験から「自分は恋愛関係を築くことが出来ない」「恋をしても傷付くだけだ」という信念が形成されているのかもしれません。その裏で片思いを抱いているのであれば、それは彼にとって非常に大きく、しかし同時に触れてはいけないものとして扱われているのでしょう。
彼は、過去のトラウマや自身の内面の複雑さから、自分が「普通ではない」という感覚を強く持っています。その「異常性」故に、一般的な恋愛関係や性的な関係を築くことは不可能だと考えている可能性があります。片思いの相手に対して純粋な好意があったとしても、それを「恋」という枠に収めると、自分自身の「異常性」と向き合わざるを得なくなり、その苦痛から逃れる為に「恋ではない」「恋が出来ない」という言葉を使っているのかもしれません。
また、「結ばれることがない」という諦めは、彼が過去に「誰かに求められること」に対して複雑な感情を抱いた経験(例:性的に求められた際に興奮出来なかったこと)が影響している可能性もあります。彼は、自分の内面にある「女児的な部分」や「無性の自分」が、一般的な恋愛関係において相手の期待に応えられないと感じ、結果として相手を傷付けてしまうことを恐れているのかもしれません。
彼に寄り添うアドバイス
彼に直接アドバイスをする機会があるかどうかは分かりませんが、もしそのような機会があったり、彼自身がこの文章を読んだりすることがあれば、以下の点について考えるきっかけになればと思います。
1. 感情に名前を付けなくてもいい
「恋」という言葉は、社会的に決まった意味合いを持っています。しかし、その枠に自分の感情を無理に当てはめる必要はありません。彼が誰かに特別な感情を抱いているなら、それは彼にとって大切な気持ちであることに変わりありません。「好き」でも「恋」でも、どんな言葉でもしっくりこなければ、あえて名前を付けなくても良いのです。
ただ「大切な人」として、その存在を心の中で温めておくことも、一つの形です。
2. 「結ばれない」という決めつけの背景を探る
何故「結ばれることがない」と決めつけているのか、その背景にある漠然とした不安や恐怖に目を向けることが大切です。彼の「男ではない」という感覚や、過去の性的な経験からくる混乱が、この決めつけに繋がっているのかもしれません。
もし彼が自分の性のあり方について更に深く知りたいのであれば、性に関するカウンセリングやLGBTQ+フレンドリーな支援団体に相談することも一つの手です。そこで自分の感情を安心して話すことで、新たな自己理解に繋がるかもしれません。必ずしも一般的な「恋愛」や「性愛」の形に当てはまらなくても、彼自身の心が満たされる人間関係の形は必ず見つかります。
3. 誰かを大切に思う気持ちは、あなたの「感性」そのもの
彼は、本来のINFP的な「感性」を幼少期に抑圧してきたと語っています。しかし、誰かに片思いをするという感情は、まさにその豊かな感性が生きている証拠です。「恋」というラベルを貼らなくても、誰かを大切に思う気持ちは、彼の内なるINFPの気質が発揮されている瞬間です。その感情を「異常」として切り捨てず、彼自身の尊い一部として受け入れることが、自己受容への大きな一歩となるでしょう。
彼の抱える苦悩は深く、すぐに解決出来るものではないかもしれません。しかし、彼が自分自身の感情や過去と向き合い続けていること自体が、回復への道を着実に歩んでいる証拠です。無理に殻を破ろうとしなくても、彼自身のペースで、少しずつ心のドアを開いていけるよう、もしサポート出来る人がいるのであれば、見守り、寄り添う姿勢が何よりも大切です。
人が「可愛い」に抗えない理由
1. 進化心理学的な要因:生存本能に刻まれたプログラム
最も有力な説の一つは、進化心理学的な視点です。私たち人間は、幼い子供や動物の赤ちゃんが持つ特定の身体的特徴に惹かれるようにプログラムされています。これらの特徴は「ベビースキーマ(幼児図式)」と呼ばれ、以下のようなものが含まれます。
- 大きな目
- 丸い顔と頭
- 短い手足
- 不器用な動き
これらの特徴は、「守ってあげたい」「世話をしてあげたい」という養育本能を刺激します。(庇護欲ともいう)これは、子孫を残し、種を存続させる為に不可欠な本能であり、可愛らしいものを見ると心が和んだり、ポジティブな感情が湧いたりするのは、この本能が作用している為と考えられます。
無力でか弱い存在を守ることで、生存確率が高まるという生物学的なメリットがある為、私たちは可愛らしさに抗えないのです。
2. 脳の報酬系への作用:喜びと快感の神経回路
可愛らしいものを見た時、私たちの脳内ではドーパミン等の快感物質が分泌されることが研究で示されています。ドーパミンは、何か良いことをした時や、喜びを感じた時に分泌される神経伝達物質で、私たちに「もっとこの感覚を味わいたい」と思わせる「報酬系」に関わっています。
可愛らしいものを見ることは、脳にとってご褒美のようなものであり、ポジティブな感情や幸福感をもたらします。この快感の経験が、私たちが可愛いものに対して更に好意的な感情を抱き、何度も見たり触れたりしたくなる衝動に駆られる理由の一つです。
3. ストレス軽減効果:心の癒しとリラックス
可愛らしいものや存在は、私たちのストレスを軽減し、リラックス効果をもたらすことが示されています。例えば、動物との触れ合いが心拍数や血圧を下げ、不安を和らげる効果があることは広く知られています。
日常生活でストレスを感じた時、可愛いキャラクターグッズを見たり、愛らしいペットと触れ合ったりすることで、心が癒され、気分が上向く経験は多くの人がしているでしょう。可愛らしさは、私たちに安心感を与え、心理的なセーフティネットのような役割を果たす為、無意識のうちにそれに惹きつけられるのです。
4. 社会的・文化的要因:共有される価値観
「可愛い」という概念は、単なる生物学的反応だけでなく、社会的・文化的にも育まれてきました。特に日本では「 kawaii 」という言葉が世界中で通用するほど、可愛い文化が浸透しています。アニメ、漫画、キャラクターグッズ等、多様な形で「可愛い」が表現され、共有されています。
こうした文化の中で育つことで、私たちは「可愛い」ものに対する感受性を高め、その価値を自然と認識するようになります。周囲の人々も「可愛い」ものを好む傾向にある為、共感や連帯感を感じるきっかけにもなり、更にその魅力に取り憑かれていくのです。
人が「可愛い」に惹かれ続ける理由:時間と魅力の変遷
「可愛いは正義」という言葉が示すように、私たちは幼さや無垢さに本能的に惹かれます。しかし、人が年を重ねても、その魅力が持続し、周囲が惹かれ続けるのは何故でしょうか。それは、「可愛い」という概念が単なる外見的な幼さだけでなく、内面的な要素や関係性によっても育まれるからです。
1. 内面から滲み出る「愛らしさ」
年齢を重ねると、外見的な「幼さ」は薄れていきます。しかし、人の内面から滲み出る「愛らしさ」は、歳を重ねるごとに深まることがあります。例えば、以下のような要素が挙げられます。
- 純粋な心と素直な感情表現:
世間ずれせず、感動や喜びを率直に表現する姿は、年齢に関わらず見る人の心を打ちます。 - 茶目っ気とユーモア:
遊び心を忘れず、人を笑顔にするような振る舞いは、親しみやすさや愛嬌として映ります。 - 優しさと思いやり:
他者への温かい配慮や慈しみの心は、その人の人間としての魅力を高め、周囲から慕われる要因となります。 - 弱さや不器用さの受容:
完璧ではない、少し不器用な部分を見せることで、かえって人間味が増し、守ってあげたいという気持ちを抱かせることもあります。
これらは、人生経験を通して培われる内面的な豊かさであり、外見的な若さとは異なる「可愛らしさ」として人々に認識されます。
2. 関係性の中で育まれる「可愛げ」
「可愛い」という感覚は、相手との関係性によっても変化し、深まります。共に時間を過ごし、互いを理解し合う中で、その人の持つ独特の魅力や個性が「可愛げ」として認識されるようになるのです。
例えば、長年連れ添った夫婦が、互いのちょっとした癖や不器用なところに「可愛い」と感じることがあります。これは、表面的な魅力だけでなく、共有された歴史や信頼関係の上に築かれた愛情表現です。ペットが高齢になっても、その存在自体がかけがえのない「可愛い」存在であり続けるのと似ています。
3. 経験がもたらす「深み」と「癒し」
歳を重ねた人は、様々な経験を積み、それらが内面に深みを与えます。その人の語る言葉や、醸し出す雰囲気には、若さにはない安心感や癒しの力が宿ることがあります。苦労を乗り越えた人だけが持つ穏やかさや、達観した視点は、多くの人に安らぎを与え、魅力として映るでしょう。
「可愛い」という感覚は、単に「幼い」「守るべき」というだけでなく、「心が和む」「癒される」「愛おしい」といった幅広い感情を含んでいます。その為、例え歳を重ねても、その人が放つポジティブなオーラや、人との繋がりの中で見せる純粋な一面に、私たちは惹かれ続けるのです。
このように、「可愛い」は外見の儚い若さだけでなく、内面の美しさや、築き上げてきた関係性、そして人生経験がもたらす深みによって、形を変えながらも永続する魅力として存在し続けると言えるでしょう。これらの要因が複合的に作用することで、私たちは可愛らしいものに対して抗いがたい魅力を感じ、ポジティブな反応を示してしまうと考えられます。「可愛いは正義」という言葉は、まさに私たちの本能と感情に深く訴えかける、普遍的な真理を突いているのかもしれません。
INTPとINFPの「水のように溶け合う」側面
記事の冒頭で触れられたように、INTPとINFPは一見すると「理論偏重」と「感性偏重」で対照的に見えますが、両者には共通点も多く、時にはその境界が曖昧になることがあります。
- 内向的(I)で、深く内省する時間を大切にする点。
- 直感的(N)で、抽象的な思考や可能性に目を向ける点。
- 知覚(P)の傾向があり、柔軟で自由なアプローチを好む点。
これらの共通基盤がある為、環境や経験によってINTPが感情を抑圧することでINFPの特性が隠れたり、INFPが論理的な思考を研ぎ澄ますことでINTPのように見えるケースが生じることがあります。どちらのタイプも、自分自身の内面を探求し、真理や意味を追求するという点で共通の動機を持っていると言えるでしょう。
INTPとINFP、どちらのタイプであっても、それぞれの強みと弱みを理解し、自己受容を深めることが、より豊かな人生を送る為の鍵となります。
MBTIの「公式」について
MBTIは、イザベル・マイヤーズとキャサリン・ブリッグスによって開発されたもので、現在、その版権はThe Myers-Briggs Company(旧 CPP, Inc.)が保有しています。日本では、その正式なプログラムやテストを提供している機関として、MBTI®認定ユーザーを育成・管理する団体が存在します。
したがって、「公式」なMBTIとは、これらの正式なルートを通じて提供されるものを指します。
MBTIの「公式」による注意喚起のポイント
- 「MBTI」と「16Personalities性格診断テスト」は別物である
- インターネット上で広く流通している「16Personalities性格診断テスト」は、MBTIとは全く異なるものであり、正式なMBTIではありません。これは商標登録されている「MBTI」の定義から外れます。
- 16Personalitiesは「主人公」や「討論者」のような名称をつけますが、本来のMBTIはこのような名称を使用しません。
- MBTIの目的は「自己理解」であり、「診断」ではない
- MBTIは、受検者が自分自身の理解を深め、より良く過ごす為のヒントを提供することを目的としています。個人の性格を断定したり、レッテルを貼ったりするものではありません。
- 「能力」や「発達段階」を測るものではなく、あくまで「傾向」を示すものです。
- 正式なMBTIは「有資格者による対面フィードバック」が必須
- 国際規格により、MBTIの結果は、専門の「MBTI®認定ユーザー」と呼ばれる有資格者から受検者本人に直接報告され、その支援の元で受検者本人が「ベストフィットタイプ」を探してゆくプロセスが義務付けられています。
- この対面でのフィードバックの質が、MBTIの有益性・有効性を左右するとされています。
- 不適切な利用方法に注意が必要
- 決めつけやレッテル貼り:
MBTIのタイプに基づいて個人を「型」にはめたり、「このタイプだからこうだ」と決めつけたりすることは避けなければなりません。 - 採用選考や人事評価への利用:
個人の能力や適性、成功を予測する為に使用すべきではありません。企業が「〇〇タイプを求めている」等と発言することは、就職差別に繋がる恐れがあり、注意が必要です。 - 適職診断としての過信:
MBTIの診断結果だけで適職を判断したり、興味がない職種に無理に限定したりするべきではありません。 - 結果の変動とアップデートの必要性:
MBTIの結果は、個人の経験や状況によって変化する可能性がある為、一度の診断結果を鵜呑みにせず、自己分析を定期的にアップデートすることが推奨されています。 - 未成年への不適切性:
日本MBTI協会では、日本では18歳以上の受講が推奨されています(アメリカでは14歳以上)。子どもの場合は、自分の嫌な面にも目を向ける過程が悪影響となるリスクがある為、慎重な運用が求められます。
- 決めつけやレッテル貼り:
これらの注意喚起は、MBTIが本来の自己理解という目的から逸脱し、誤用されることによる個人への不利益や、社会的な誤解を防ぐ為に非常に重要視されています。

まとめ
人は無意識のうちに「自分と同じように考えるだろう」「同じように感じるだろう」と、他者を自分というフィルターを通して見てしまいがちです。これを「投影」と呼び、自他境界が曖昧になる原因の一つでもあります。
MBTIのような性格分類ツールは、まさにこの「投影」を防ぎ、自他境界を明確にする上で非常に有用です。例えば、「自分はINFPだから、共感や理想を重視する。でも、この人はT(思考)タイプだから、論理や客観性を重視するかもしれない」といったように、相手の行動や発言の背景にある思考パターンや価値観を、感情的に理解出来なくても、理屈として理解する手がかりを与えてくれます。
「嫌い」の感情と「存在」の認識
特に、生理的嫌悪と感じるタイプがいるという話は、多くの人が経験することかもしれません。しかし、重要なのは、その「嫌い」という感情を抱きつつも、「現実として『そんな人』はこの世界に存在している」と認識している点です。
これは、感情と理性のバランスを取ろうとする成熟した姿勢です。感情的な「嫌い」を否定する必要はありませんが、同時に、多様な人々が共存する社会で生きていく為には、感情的に受け入れがたくても、相手の存在を認め、その特性を理解しようと努めることが不可欠です。
性格分類の活用:感情的な理解を超えた「集合知」
ご自身で「自分の経験だけで理論化していくのはリソース的にキツすぎる」とおっしゃっているように、MBTIのような集合知は、限られた個人の経験だけでは得られない多様な人間の傾向を体系的に理解する上で効率的なツールです。
「へー世の中にはこんな人もいるんだ」と、感情ではなく理屈で理解しておくことは、他者との協働やコミュニケーションにおいて、無用な誤解や衝突を避ける為の「心の準備」になります。それは、特定のタイプに自分を固定することではなく、自分が世界をINFPフィルターで見ていることを自覚し、そのフィルターの外にも広大な多様性が存在することを認識することだと言えるでしょう。
MBTIのようなツールは、単なる診断結果に一喜一憂するのではなく、「自分はこういう人間である」という理解を深めると同時に、「世の中には自分とは異なる様々な人がいる」という他者理解の視野を広げる為に活用出来る、という気付きは非常に重要です。この視点は、より豊かな人間関係を築き、多様な社会で柔軟に生きていく為の力となるはずです。
この考えは、今後ご自身が様々な人と関わっていく上で、きっと大きな助けになるでしょうね。