ゲーム制作は、無限の可能性を秘めた魅力的な挑戦です。しかし、誰もが一度は「もうダメだ…」と壁にぶつかり、立ち止まってしまうことがあります。特に、「技術的な問題で前に進めない」「思い描いた通りに表現出来ない」といった状況は、多くのクリエイターが直面する共通の悩みです。
でも、安心してください。それは決してあなた一人ではありません。そして、その壁は乗り越えられないものではありません。
私も悩めるうちの一人です。(訳:要は制作に詰まっています)
この記事では、ゲーム制作で行き詰まってしまう具体的な原因を掘り下げ、そこから抜け出す為の実践的なヒントをご紹介します。→(クリエイティブ)
何故ゲーム制作でつまずいてしまうのか?
あなたの行き詰まりの背景には、いくつかの共通する原因が隠されているかもしれません。
- 「変数」という謎の存在:
ゲームの状態や情報を管理する変数。その役割が曖昧だったり、「数字」というだけで苦手意識を感じてしまったりして、ゲームのロジックが組み立てられない。 - 計算の苦手意識:
座標の移動、ダメージ計算、時間経過等、数字や計算が絡む部分で思考が停止してしまう。 - デバッグの壁:
プログラムが思い通りに動かない時、「どこが間違っているのか?」を特定する方法が分からず、途方に暮れてしまう。 - 理想と現実のギャップ:
「こんなカッコいい演出がしたい!」というこだわりがあるのに、それを実現する為の技術が見つからず、表現のジレンマに陥る。 - モチベーションの低下:
技術的な問題が続いたり、ツールのアップデートに追いつくのが面倒になったりして、制作意欲が薄れてしまう。
壁を乗り越える為の実践的アプローチ
1. 変数を「箱」として捉え直す
変数を難しく考える必要はありません。単に「何か情報を閉まっておく為の箱」だとイメージしてみましょう。
- 「プレイヤーのHP」:
「プレイヤーの体力が今いくつなのか」という数字をしまっておく箱。 - 「鍵を持っているか」:
「鍵を今持っているのか、持っていないのか」という「はい/いいえ」の情報をしまっておく箱。
このように、変数は数字だけを扱うものではありません。ゲーム内の「状態」や「条件」を記憶する為の「メモ」だと考えると、親しみやすくなります。
(※何でこの世にわざわざ変数なんてものを作ったんでしょうかね?←)
2. 「見える化」と「追跡」で変数を攻略する
頭の中だけで変数の動きを追うのは至難の業です。目に見える形で変数の変化を追ってみましょう。
- 紙とペンでシミュレーション:
ホワイトボードやノートに変数名を書き出し、ゲームの進行に合わせて値を実際に書き換えてみてください。「このイベントが起きたら、HPが100から80になった!」というように、視覚的に変化を追うことで、理解が深まります。 - デバッグツールを徹底活用:
多くのゲーム制作ツールには、非常に強力なデバッグ機能が備わっています。これを使って、プログラムが動いている最中に変数の値がリアルタイムでどう変化しているかを目で見て確認することが何よりも重要です。- ブレークポイント:
特定の場所でプログラムを一時停止させ、その瞬間の変数の値を確認出来ます。 - ウォッチ:
特定の変数の値を常に監視し、変化を追うことが出来ます。 「あれ?この値、思ってたのと違う!」という発見が出来れば、原因特定への大きな手がかりになります。これは、数字が苦手な方にとって特に有効な手段です。
- ブレークポイント:
3. 「何故?」と「何の為に?」を問いかける
プログラムの一行一行、あるいは変数の一つ一つに対して、「何故これがここに必要なのか?」「この変数は何の為に存在するのか?」という問いを投げかけてみてください。
例えば、鍵を使った扉のイベントで「アイテムを持ってないのに開いてしまった」という問題に直面した場合。
- 「扉が開く為には何が必要?」→ 「鍵を持っていること」
- 「じゃあ、鍵を持っているかどうかって情報を、どうやって覚えておこう?」→ 「変数を使えばいいんだ!」
- 「鍵を手に入れたら、その変数を『持っている』状態にしよう。扉を開けたら、その変数を『消費した』状態に戻そう。」
このように、目的から逆算して必要な情報を洗い出し、それを管理する手段として変数を使う、という思考プロセスを意識すると、変数が「嫌なもの」から「便利なツール」に変わるはずです。
4. 完璧主義を手放し、「動くこと」を最優先に
「こんなカッコいい演出がしたいのに!」というこだわりは、素晴らしいクリエイターの情熱です。しかし、それが制作の妨げになっているなら、一旦その完璧主義を脇に置いてみましょう。
- 「とりあえず動く」ことを目標に:
まずは見た目がシンプルでも、意図した通りにゲームのロジックが動くことを最優先します。 - 後から「飾り付け」:
ロジックが完成し、ゲームが正しく機能するようになったら、そこにエフェクト、アニメーション、凝ったセリフ等の「カッコいい」演出を追加していきましょう。このステップを踏むことで、技術的な壁にぶつかりにくくなり、モチベーションも維持しやすくなります。
5. 頼れるものは積極的に頼る!
一人で抱え込まず、外部のリソースを積極的に活用しましょう。
- ツールを使いこなす:
計算が苦手なら、ツールに備わっている計算機能や、プラグイン・スクリプトを積極的に利用しましょう。全て自分で組む必要はありません。 - コミュニティに飛び込む:
オンラインのゲーム制作コミュニティやフォーラムは、宝の山です。具体的な状況を説明して質問すれば、ベテランのクリエイターたちが温かいアドバイスをくれるはずです。「こんな初歩的なこと…」と遠慮する必要は全くありません。 - 得意なことを伸ばす:
算数やプログラミングが苦手でも、デザインやシナリオ、企画等、他に得意な分野があるはずです。そこを徹底的に伸ばし、自信に繋げましょう。苦手な部分にばかり目を向けず、自分の強みを活かす視点も大切です。
あなたの「好き」を形にしよう
ゲーム制作は、試行錯誤の連続であり、挫折は誰にでも訪れる通過点です。しかし、その先に、あなたのアイデアが形になり、多くの人に楽しんでもらえるという大きな喜びが待っています。
「変数」や「計算」への苦手意識は、少しずつ克服出来るものです。焦らず、一歩ずつ、ご自身のペースで、ゲーム制作の旅を楽しんでいきましょう。あなたの「好き」という気持ちこそが、最高の原動力となるはずです!
という自分に対して励ます記事でした。(完成するまでまだ時間がかかります)

おまけ:何故ゲームでキレてしまうの? 対戦ゲームと感情のメカニズムを考える
オンライン対戦ゲーム、特にチームベースのゲームをプレイしていると、「何でこんなところで!」「マジかよ…」と、つい熱くなってしまうことがありますよね。中には、怒りが爆発してコントローラーを投げつけてしまったり、心ない言葉を投げかけてしまったりする人もいます。
何故、ゲームでこれほど感情的になってしまうのでしょうか?
そして、その感情とどう向き合えばいいのでしょうか?対戦ゲームで「キレやすい人」の心理と、その背景にある感情のメカニズムについて考えていきましょう。
「キレやすい人」に見られる意外な特徴
「キレやすい」と聞くと、乱暴なイメージを持つかもしれませんが、ゲームで感情的になってしまう人には、実はある種の共通点が見られます。
- 高い「勝ちたい」気持ちと完璧主義:
- 対戦ゲームである以上、「勝ちたい」という気持ちは誰にでもあります。しかし、キレやすい人は、その勝利へのこだわりが人一倍強く、自分の理想とするプレイやチームの動きが少しでも崩れると、強い不満を感じやすい傾向があります。
- 自分自身や味方のミスをなかなか許容出来ず、「こうあるべきなのに!」という理想とのギャップに、耐えられなくなってしまうことがあります。
- 感情の「処理」が苦手:
- 瞬時に湧き上がる怒りや苛立ちといったネガティブな感情を、冷静に受け止めて処理するスキルが未熟な場合があります。
- ストレスや不満を心の中に溜め込みやすく、それがオンラインゲームという匿名性の高い空間で、思わず爆発してしまうことがあるのです。
- 自己評価やプライドの高さ:
- 「自分ならもっと出来るはず」「こんな簡単なミス、ありえない」というように、自身のプレイや実力に対するプライドが高い場合、それが発揮出来なかったり、予想外の敗北を喫したりすることを受け入れがたく感じてしまいます。
- 負けを認めることや、ミスを指摘されることを防衛する為に、感情的になったり、他者のせいにしたりする行動に出ることもあります。
- 「楽しむ」よりも「勝つ」が目的化:
- ゲーム本来の「楽しさ」――例えば、仲間との連携、新しい戦略の発見、キャラクターを動かすこと自体――よりも、「勝利」という結果だけをひたすら追い求めてしまうと、負けが許容出来なくなり、感情的になりやすくなります。
- 現実世界でのストレスが影響:
- 日常生活で抱えている仕事や学業、人間関係のストレスが、ゲームに持ち込まれてしまうケースも少なくありません。ゲームがストレス発散の場であるはずが、上手くいかないことで、かえってさらなるストレスの引き金となってしまうことがあります。
ゲームの「大変さ」を知っているからこそ?
ゲーム開発に携わった経験のある方なら、一つのゲームが完成するまでにどれほど多くの苦労や調整、デバッグが積み重ねられているか、身をもって知っているはずです。
- 膨大な技術的な壁:
プログラミング、グラフィック、サウンド、バランス調整、そして気が遠くなるようなバグ修正。 - 終わりなきデバッグと調整:
プレイヤーに最高の体験を提供する為、何度も何度もテストプレイを重ね、わずかな違和感も修正していく、地道で根気のいる作業。
これらの「大変さ」を知っているからこそ、「何でこんな簡単なことが出来ないんだ」「こんなバグ、許せない」といった、より強い苛立ちを感じてしまうこともあるかもしれません。
しかし、プレイヤーは、そのゲームがどれだけ大変な努力の結晶であるかを知らずにプレイしている場合がほとんどです。彼らにとって、ゲームは純粋に「楽しむ為のもの」であり、感情的になるプレイヤーの姿は、その楽しさを損ねるものとなってしまいます。
健全なゲームライフの為に、出来ること
もしあなたがゲーム中に感情的になってしまうことに悩んでいるなら、以下のヒントを試してみてください。
- 「休憩」という名のクールダウン:
イライラし始めたら、一度コントローラーを置き、ゲームから完全に離れてみましょう。短い休憩でも、驚くほど気持ちが落ち着くことがあります。 - 「勝利至上主義」を手放す:
勝ち負けだけでなく、ナイスプレイができた瞬間、新しい戦術がはまった時、仲間と連携が取れた時など、過程の楽しさに目を向けてみましょう。
何故なら強制的に戦場に参加してるわけじゃないですからね。自分が生身で死なないと理解してるから簡単に「勝利至上主義」になれるわけです。
- 自分なりの「ルール」を作る:
「負けが3回続いたらその日は止める」「暴言は絶対に吐かない」といった、自分を律するマイルールを設定するのも有効です。 - 完璧を求めすぎない:
ゲームは、予測不可能な要素や他プレイヤーの行動が常に絡むものです。自分の思い通りにならないことがあっても、「そういうものだ」と受け入れる柔軟性を持つことも大切です。
そして、もしあなたが他のプレイヤーの感情的な行動に遭遇して嫌な思いをしたら、迷わずミュート機能やブロック機能を活用し、必要であればゲーム運営に通報しましょう。誰もが気持ちよくプレイ出来る環境は、一人ひとりの意識と行動から作られます。
わざわざ子供相手に感情的になる大人なら尚更です。
ゲームは、私たちに多くの喜びや興奮を与えてくれる素晴らしいエンターテイメントです。その魅力を最大限に享受する為にも、自分の感情と上手に付き合い、健全なゲームライフを送っていきましょう。

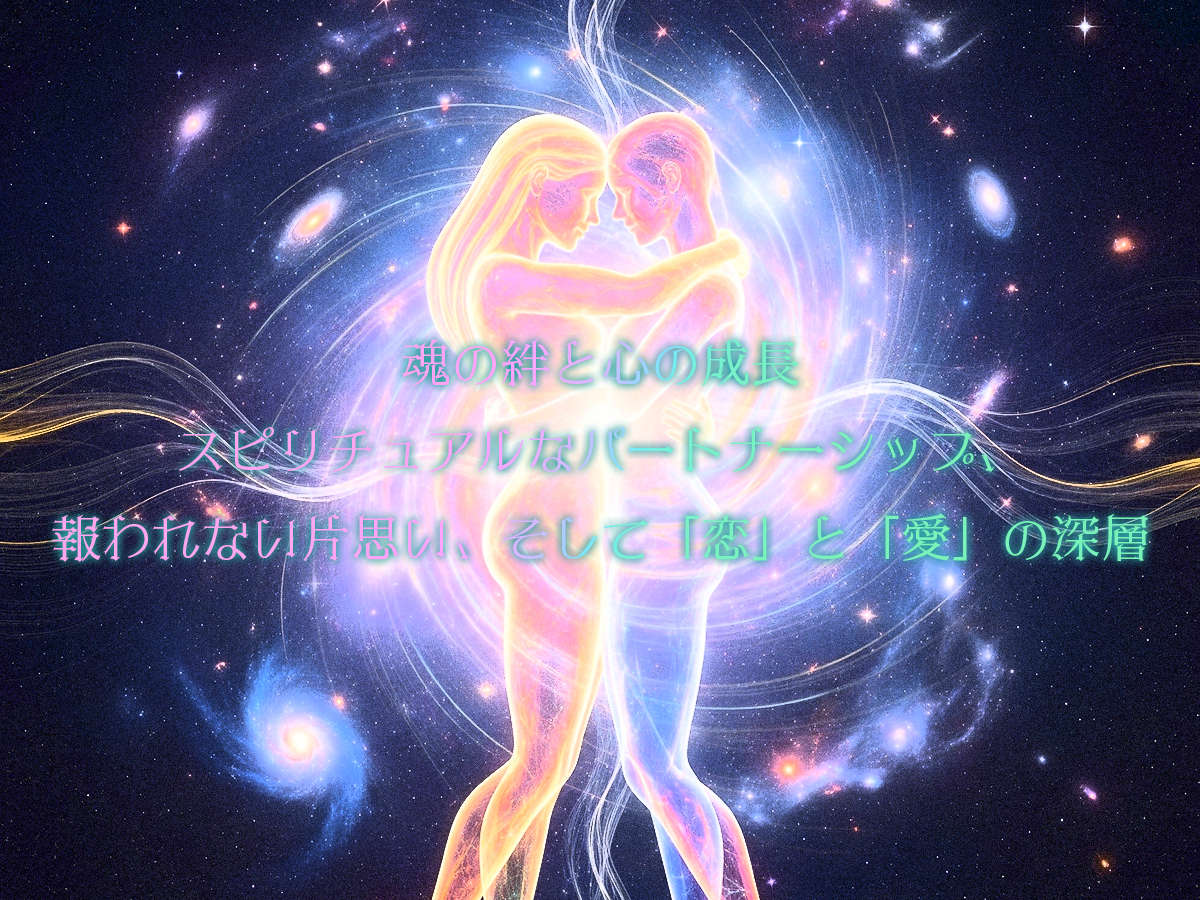
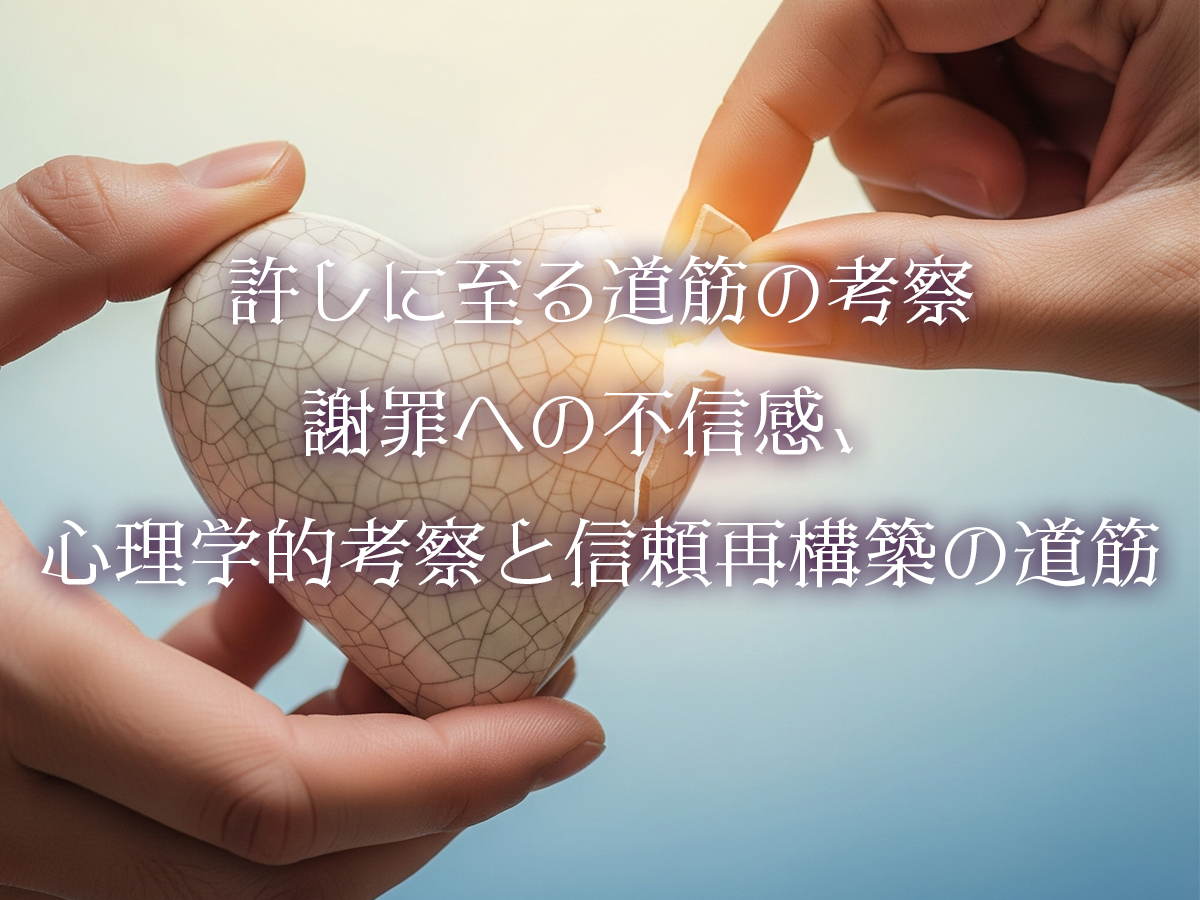
コメント