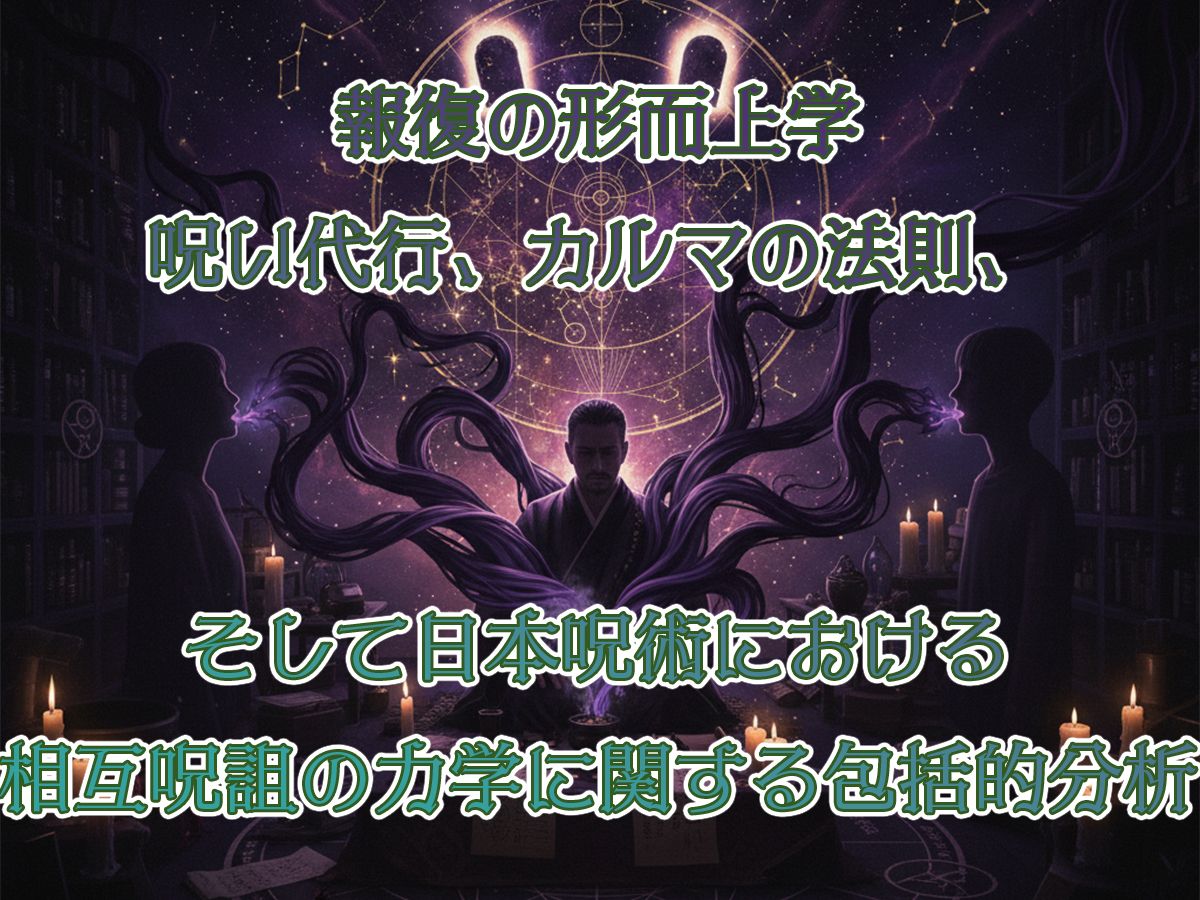― SNS社会における自己演出とアイデンティティの変容 ―
| 概念 | 意味 | 現象例 |
|---|---|---|
| デジタル多重人格 | 一人が複数の人格を使い分ける適応行動 | 本アカ・裏アカ・創作アカ等 |
| オンライン・パフォーマティヴィティ | 「演じることで存在する」SNS的自己 | 投稿・いいね・コメント文化 |
1. はじめに
現代のSNS空間では、一人の人間が複数の人格を使い分けて活動する現象が日常的に見られる。
本名アカウントと匿名アカウント、創作専用アカウント、交流用サブアカウント等、
人は状況と目的に応じて複数の自己を構築している。
このような「デジタル多重人格(Digital Multiplicity)」は、
もはや異常ではなく、社会的適応の一形態として理解されつつある。
同時に、SNS上での存在が「演じる行為」によって成立するという
オンライン・パフォーマティヴィティ(Online Performativity)の概念も注目されている。
本稿では、これら2つの現象を社会心理学的観点から考察する。
2. デジタル多重人格:適応的自己分化としての多面性
2.1 定義と構造
「デジタル多重人格」とは、一人の個人がオンライン空間で複数の社会的自己を演じ分ける状態を指す。
それは病理的な解離ではなく、役割行動(role behavior)の拡張である。
現実世界でも、人は家庭・職場・友人関係等で役割を変化させている。
SNSはその切り替えを更に容易にし、人格のスイッチングを可視化した。
2.2 動機と心理的背景
複数人格の運用は、主に次の心理的要因によって支えられている。
- 自己防衛欲求:
批判や攻撃から自分を守る為の匿名性の確保 - 承認欲求:
他者からの「いいね」「フォロー」による社会的承認の獲得 - 表現欲求:
現実では抑圧された自我を創作・発信という形で解放 - ストレス対処:
本音を吐き出す裏アカの存在による心理的カタルシス
これらはいずれも、社会的圧力や期待の高い現代社会において
「自分を保つ為の戦略的行動」として機能している。
3. オンライン・パフォーマティヴィティ:演技としての存在
3.1 理論的背景
哲学者ジュディス・バトラー(Judith Butler, 1990)のパフォーマティヴィティ理論によれば、
アイデンティティは行為を通じて生成される。
哲学者ジュディス・バトラーはこう言いました。
「人は、行為によって自分になる。」
SNS空間では、投稿・写真・コメント・絵文字といった一連の行為が
「自己表現」であると同時に「自己生成」のプロセスとなる。
3.2 SNS文化における演技性
SNSの設計自体が、演技的行動を促進するよう構成されている。
アルゴリズムは「共感を得る発言」や「映える画像」を優先的に拡散し、
ユーザーは次第に“反応される自分”を最適化していく。
この過程で人は、無意識のうちに「観客(フォロワー)」を意識し、
現実の自己ではなく、“評価される自己”を演じる傾向を強めていく。
4. 社会的影響と心理的リスク
4.1 自己概念の分裂
複数の自己を同時に運用することで、
「どれが本当の自分か」が曖昧になり、自己同一性の揺らぎが生じる。
特に、裏アカ等で表現する“本音の自分”が
社会的自己と乖離しすぎると、内的葛藤や孤立感を引き起こす。
4.2 集団同調と共鳴の罠
SNSの「同質化アルゴリズム」は、似た意見や感情を持つ人々を集め、
「周波数が合う」小集団を形成する。
これは安心感をもたらす一方で、他者理解の欠如や分極化を助長する。
結果として、演じる人格が“界隈”に依存し、
現実社会との心理的乖離が拡大する危険がある。
4.3 感情の商品化
SNSでは、感情すら「いいね」や「拡散」によって市場価値を持つ。
その為、悲しみ・怒り・可愛さ・セクシュアリティ等が
演技的に生産・演出される感情商品となる。
これは「存在の経済化(economization of being)」とも呼ばれる現象である。
5. 結論:演技と真実の間に生きる
デジタル社会において、人は常に誰かの視線の元に存在し、
その視線を意識すること自体が「生き方」となっている。
「デジタル多重人格」は、その圧力の中で生まれた心理的防衛装置であり、
「オンライン・パフォーマティヴィティ」は、
その環境に適応する為の文化的演技形式である。
私たちは今、「本当の自分を見せる」ことよりも、
「どの自分を生きるか」を選択する時代に立っている。
私たちは今日も、画面の向こうで何かを演じながら、
その演技の中にほんの少しの“本当”を探しているのかもしれません。
ここからは私の本音。
SNSの時代、私たちは一つの身体にいくつもの人格を宿すようになった。「アカウント」という分身は、現実の自我とは異なる感情表現や言葉遣いをもつ。それは時に演技的で、時に防衛的で、時に癒しの場でもある。
社会心理学の観点から見ると、こうした「デジタル多重人格」は集団内での承認欲求と同調圧力の相互作用から生まれる。 他者の反応が“自己の輪郭”を作り出し、クリック一つで人格が切り替わる時代に、私たちは“演じること”を通して自分を確認しているのだ。
しかし、問題は“演技”が永続化し、現実の自我と乖離を起こす瞬間にある。 オンライン・パフォーマティヴィティとは、「見せる自分」が「感じる自分」を上書きしてしまう構造である。その時、共感の形は「感情」ではなく「アルゴリズム」によって制御される。
スピリチュアルな視点から見れば、これは「エネルギーの分散」とも言える。 本来一つであるはずの意識が、承認欲求と情報過多によって分裂し、魂の中心軸がブレていく。“フォロワー数”という数値の中で、私たちは何を信じ、何を演じているのだろうか。
デジタル社会において必要なのは、人格の統合である。オンラインの自分と現実の自分を切り離さず、どのアカウントにおいても「心の本質」が反映されていること。それが、これからの時代における真のスピリチュアル・パフォーマティヴィティだと言えるだろう。
参考文献(主要理論)
- Butler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity.
- Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life.
- Turkle, S. (2011). Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other.
- Boyd, D. (2014). It’s Complicated: The Social Lives of Networked Teens.