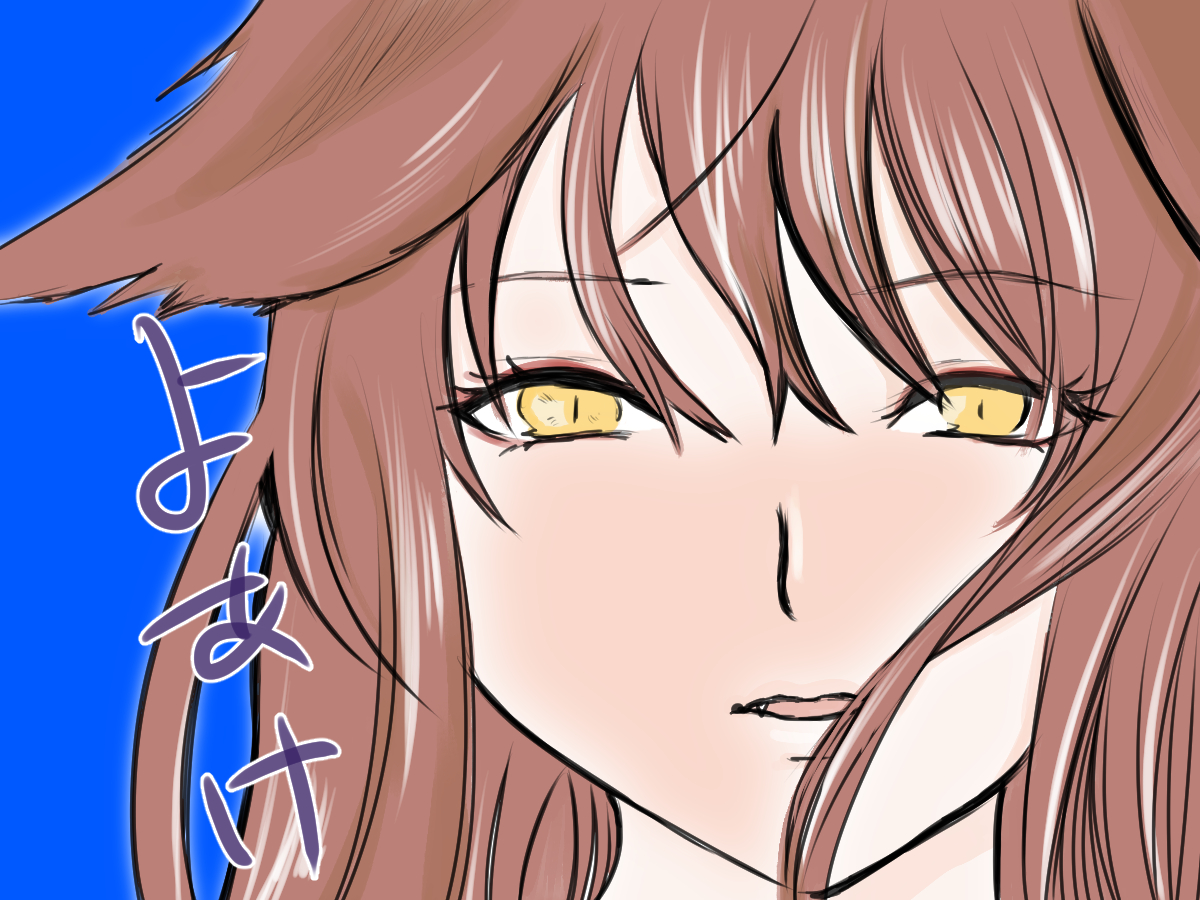・・・というタイトルは何ともあれですが、すっかりAIと共存する時代になりました。元々人工知能としての概念は1950年代頃から存在してましたが現在のような生成AIや創作支援ツールとしてのAIが本格的に一般に普及し始めたのは、ここ数年の話なんですってね。
あくまでAIという言葉を前面に出すものではなく、裏方の「スマート機能」としての存在だったんですよ。さて、本題に参ります。
絵師とAI絵師の違いとは?
一言で言うと、絵柄で勝負するかそうじゃないかの違いなんだけど。
しかし中には、プロンプトを駆使してクォリティの高いものを制作してる方もいます。絵を描くのは得意ではないけど、こういうものに特化して得意に回せる人といいますか。
そもそもよくあるAI絵師の良くないところって?
AIは「創作の道具」、人間が「意図」を持たなければ意味をなさないものだ。
あくまで人間の創造性・意図・判断力を増幅する為の装置なんですよ。
⭐️「どんな世界を描きたいのか」
⭐️「どんな感情を表現したいのか」
⭐️「何を伝えたいのか」
といった人間側の主体性や創作意図がないと、AIはただの確率出力マシンになってしまいます。
創作意図を持たずにAIをただ動かしているだけなら、それは創作者とは言えないと思います。何のビジョンもなく「とりあえず可愛い女の子」等と指示するだけでは、AIが生み出したものに反応している消費者になってしまうので。(均一に整えられた美しさを出す傾向が強い)
脳死で使えば、AIに「使われている」だけになる。
アップデートされない限り、出力の質や傾向は変わらない。それと生成物に責任を持つ主体が曖昧で、「誰の作品か」がはっきりしないことがありますね。
右脳を使った活動をしているか否か
ユーザーがAIに「色鮮やかさ」や「印象的な画」を求めて指示し、それに感動や満足を感じるのであれば、それは確かに右脳的な活動=感性の働きだと言えます。
AIは左脳的な模倣である。
AI自体は感覚や直感を持たないので、右脳的な働きをしているわけではありません。(直感・創造・情緒)ただ、人間が右脳的な発想で思い描いたものを、AIが技術的に再現することは出来ます。
では、AIを使う人間はきちんと右脳を使っているのか?
YES!(?)プロンプトの工夫、想像力、構図のひらめき、色の選び方に感性を使っていれば、それは右脳的活動です。
一方で、AIに任せっぱなしで、ただ「それっぽい」ものを機械的に選んでいるだけなら、それはむしろ左脳的処理に近いです。
AIを使うこと自体が右脳的かどうかはその人の使い方にかかっているし美的判断・感覚的意図が介在していれば、それは右脳を使っている創作行為だと言える。
| 左脳 | 右脳 |
| 言語・論理・分析・数値など | 空間認識・イメージ・芸術・直感など |
AIは人間の右脳のように「意味は分からないけど美しい」とか「無意識的に好き」といった情緒判断をしません。
ただし、人間がどう感じるかに寄り添うよう設計されている為、ユーザーの右脳を補助するツールになり得るものです。
単なる模倣ではなく、数理モデルに基づいた「推測」や「予測」をしている
AIは学習データに含まれていないものを推測が出来、模倣ではなく数理モデルの推測が出来ます。
しかしそれが人間の「創造的思考」や「直感」と同じかというと、決してそうではないです。
学習データ(大量のテキスト)を丸暗記して「そのまま再生」しているのではなく、その中のパターン・関連性・文脈の確率分布を学習しています。
つまり、
「このような文脈なら、次に来るもっともらしい言葉は何か?」
という問いに対して、統計的・確率的にもっともありそうな次の語を推測して文章を生成しているのでこれらを踏まえて、「新しいけれど、もっともらしい」応答を出すよう設計されています。
ChatGPTだと「Transformer」と呼ばれる構造を持った大規模言語モデル(LLM)で単語や文の意味、文脈の流れをベクトル(数値の集まり)として捉え、数百万~数十億のパラメータ(重み)を通じて、意味的・文脈的な推測を行っています。
正確には「切り貼り」や「過去データの組み合わせ」ではなく、学習した「統計的な法則(=関数モデル)」を通じて、推測・予測・生成を行っている
AIは「この文と似た文を丸ごとどこかから持ってきている」のではなく、「こういう文脈ではこういう語彙や構文の傾向が強い」という確率分布の関数モデルを学んでおり、そのモデルを通じて新しい文や画像を出力している。
ーーーつまり、出力結果は「どこにも存在しない」ことが多くそれは統計モデルを通じた再創造や生成の結果です。難しいですね(°ω。)
結論は学習した数理モデル(法則)に基づいて予測・生成しているということ。組み合わせではないのです。(だから過去と似ていない未来の出力も可能)
じゃあ似たようなものが多く出るのはどうして?
それは人間が求める出力(プロンプト)が、過去の傾向に寄っていることが多いためであり、またモデルが「もっとも確率の高い=もっともありそうな」出力を選ぶ性質があるからです。
なのでユーザーによって新しいトレンドや既存にない構造も生まれうる。AI時代の創作は、「使い手」で決まるのだ。
もう「昔のやり方」には戻らない理由
アナログで行われていた時代があったがおそらくあの「手間と時間と労力」を前提にした命を削る創作スタイルには、もう完全には戻らないでしょう。
アニメ制作も、イラスト制作も、かつては一枚一枚、手で描いて、レイヤーを重ねて、表現の限界を工夫で乗り越えていた時代でした。
その技術と美学は今でも尊いし、過去の名作たちは「人間の極限の集中力と努力」の結晶です。
しかし現代は、AI補助や自動補間、3Dモデルや自動彩色などが入り込み、時間や工数、資金の問題を技術で解決する時代になりました。
技術は「戻らない」よりアップデートによって「変わってしまった」。
現在は効率化が進み、
3Dモデル、リギング、AIによる線画補助や彩色、自動アニメーション生成等、あらゆる領域で「時短・省力」が当然の時代に。
かといって別にだからといって、終わりではないです。
表現の選択肢が広がったってだけで、新しいツールの中で別の形に進化したってだけで昔のような熱量やその魂が失われたわけではない。
AIがいかに進化しても、「何を作りたいか」を考えるのは人間の役割です。
ていうか今のアニメーションも何やかんや言っても時間がかかってますけど・・・・
| 昔 | 今 |
|---|---|
| 手作業が膨大 | 演出・密度が膨大 |
| 書いて→撮って→放送 | 書いて→作って→盛って→直して→動かして→仕上げる |
超高品質のアニメは、むしろ以前よりも密度・工程が増えている側面で2〜3年置きに放送されるようになりましたよね・・・(コロナ以降から・・・。)
技術が進んだ分、「時間短縮」ではなく表現力の拡大に使われている、というのが実情なので良いんだか悪いんだか・・・・。※早く呪術廻戦が観たい
まぁそんなこんなで、
結局原理的には「クライアントに対して企画やビジュアルを提案する行為」とほとんど同じ構造なのでユーザー側の「自分は何を表現したいのか」によって、
AIだけでの能動的なアートディレクションとして成立します。
まとめ
AIに使われるのではなく、AIを使って、自分の中の世界を形にする。それが、AI時代における本当の創作なのだと思います。
ってことで、ミャクミャクを擬人化したものを更にアレンジしてみましたが・・・。↓









・・・・何だかミャクミャクの原点に戻ったような感じになりましたね。赤を追加したかったけどずっと青のままでした。完。