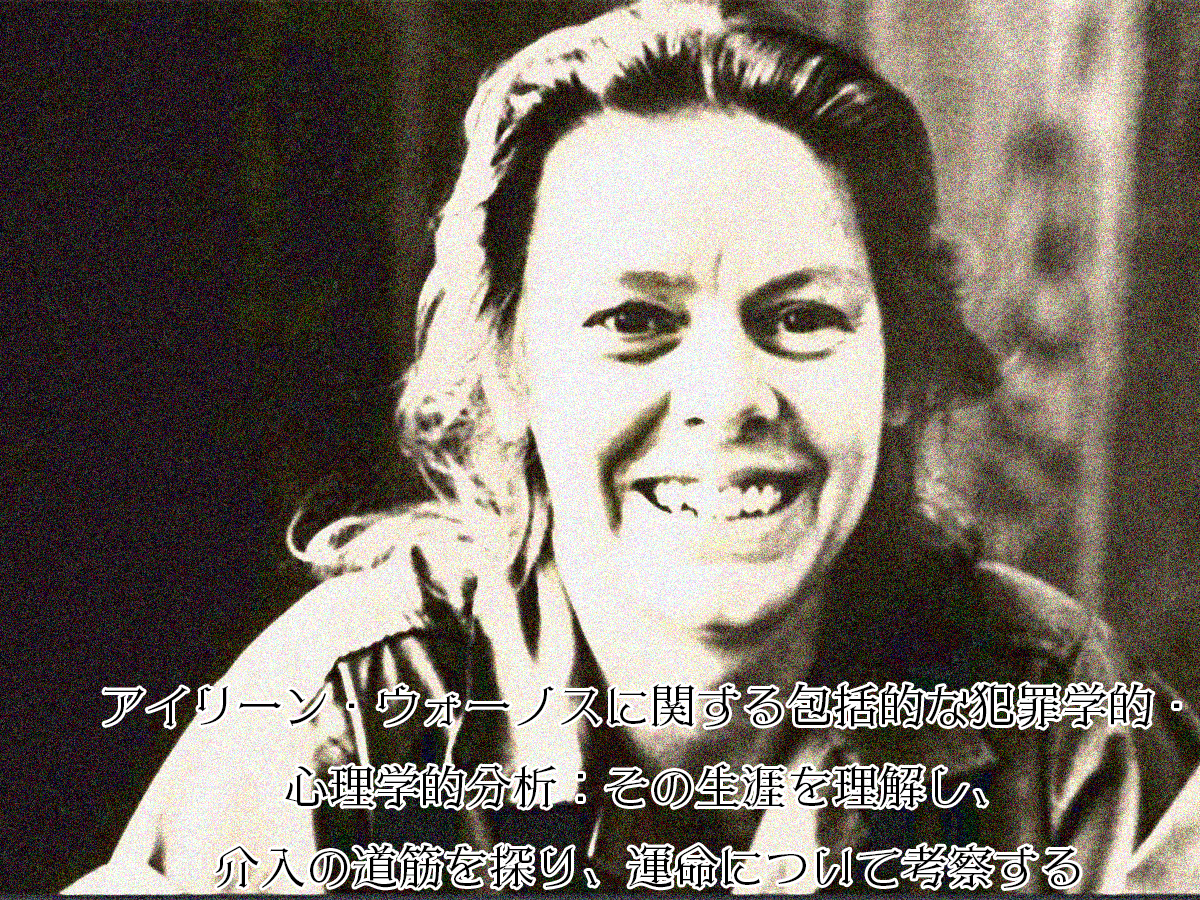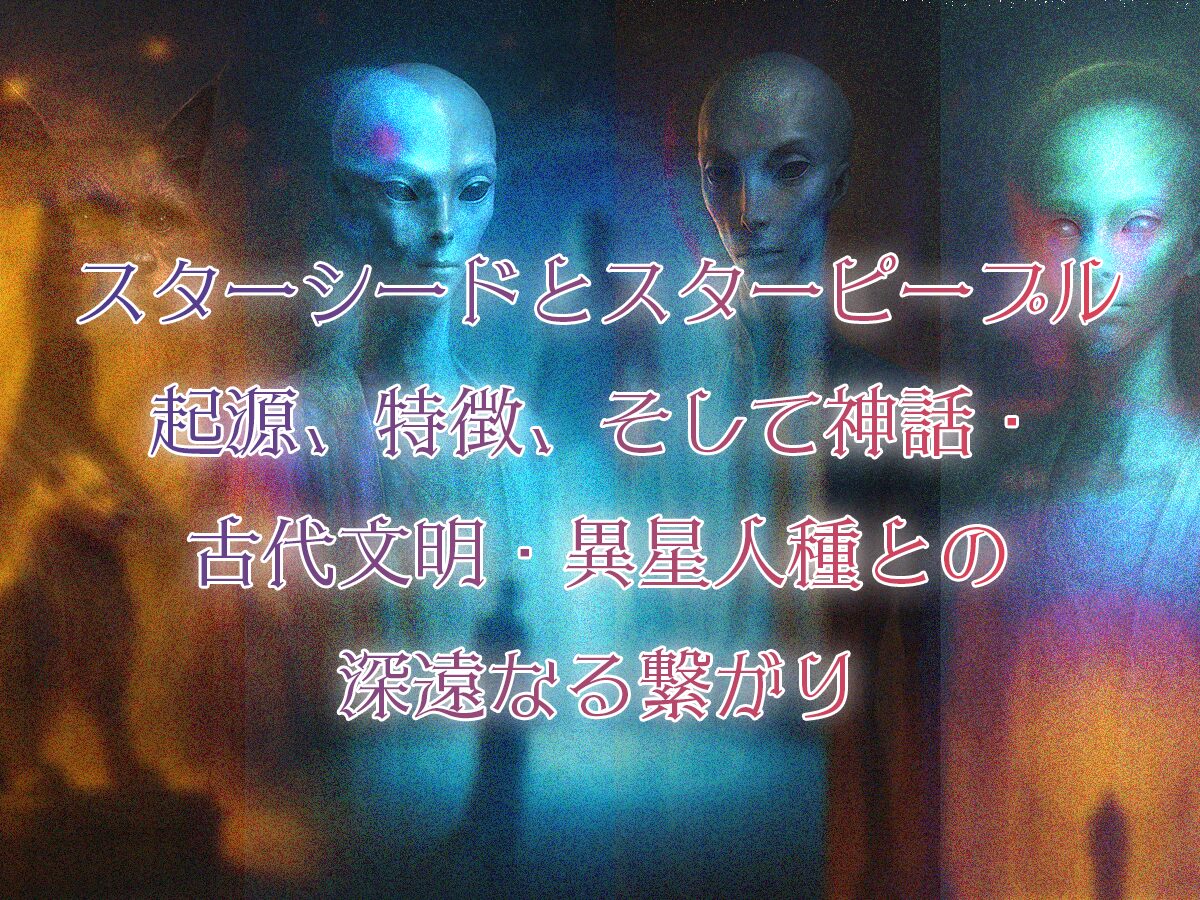I. はじめに:深刻化する人間とクマの軋轢

A. 問題の背景と現状認識
近年、日本全国でクマの市街地への出没が急増し、それに伴う人身被害や農作物被害が深刻な社会問題となっています。この現象は単なる偶発的な出来事ではなく、人間社会と自然環境の複雑な相互作用の結果として生じています。特に、2023年度はクマによる人身被害が過去最多を記録する等、その緊急性は高まる一方です。この問題は、単なる野生動物管理の範疇を超え、人身被害、農作物被害、地域経済への打撃、そして社会的な分断という多層的な複合危機を形成しています。特に、秋田県における農作物被害の記録的な増加は、食料安全保障や地域農業の持続可能性にも影響を及ぼす可能性を示唆しており、単に「怖い動物」という認識を超え、地域社会の存続に関わる広範な課題であることを示しています。
過去10年間の全国のクマ被害状況を見ると、驚くべき変化が起きています。2016年には人身被害が101件、被害者105人、死亡者4人であったものが、2023年には人身被害198件、被害者219人、死亡者6人と、統計のある2006年以降で最多を記録しました。2024年度に入っても、7月までに55人の死傷者が確認されており、これは2023年度とほぼ同水準で推移しています。
この継続的な被害の増加は、問題が一時的な現象ではなく、新たな常態として定着しつつあることを強く示唆しており、抜本的な対策の必要性を浮き彫りにしています。特に東北地方は「最激戦区」と化しており、2023年度には秋田県で62件、岩手県で46件の人身被害が発生し、この2県だけで全国の半数以上を占めました。このような特定地域での被害集中は、その地域で何らかの根本的な環境変化や管理上の課題が顕著に表れていることを示唆しています。
B. 本報告書の目的と構成
本報告書は、クマ出没問題の現状を詳細に把握し、その根本原因を多角的に分析します。特に、気候変動、森林環境の変化、人間活動(太陽光パネル設置、森林伐採)、そして社会構造の変化(過疎化、高齢化)といった要因に焦点を当て、全国的な視点から考察します。その上で、「人間優先」の原則を前提としつつ、人間とクマが平和的に共存する為の具体的な方法を提案します。
C. 人間優先の原則と共存の倫理的基盤
クマ問題における議論は、「クマ擁護派」と「クマ殺す派」という二項対立に陥りがちであり、感情的な対立が深まる傾向にあります。クマ駆除をめぐっては、自治体に対して「クマ殺し。人間が駆除されるべき」「何でもかんでもクマを殺すな」「クマの命も大切だ」といった強い批判の声が殺到し、中には2時間にわたる長電話や暴言も報告されています。一方で、「人間にとって危険を排除すべき」「被害増加の為駆除は仕方ない」という意見も多数存在します。
このような対立の背景には、都市部に住む人々が抱く「理想化された自然」観が深く関与していると指摘されています。彼らはクマを「癒やしの存在」や「悪者ではない」と捉え、その駆除に強い抵抗を示す傾向があります。しかし、この認識はクマによる直接的な被害に直面する地方住民の現実とは大きく乖離しており、このギャップが感情的な対立と非建設的な批判を生み出しています。この乖離は、都市と地方の間に存在する情報格差と経験格差に根ざしており、効果的な問題解決には、双方の視点を理解し、対話を促進する努力が不可欠であることを示唆しています。
本報告書は、いかなる状況においても人間の生命と安全が最優先されるべきであるという原則を明確に掲げます。この原則は、人間の生存権という根源的な倫理に基づいています。人間は生きる為に他者を消費する存在であり、その倫理的責任は複雑です。その上で、クマもまた生態系の一員であり、その生命を不必要に奪うことは避けるべきであるという共存の倫理的基盤を追求します。クマの駆除は、人命を守るという直接的な必要性と、野生生物の命を尊重するという広範な倫理との間で揺れ動く倫理的ジレンマを内包しています。このジレンマは、一時的な「対症療法」としての駆除と、根本的な「原因療法」としての共存策のバランスをいかに取るかという、より深い哲学的な問いを内包していると言えるでしょう。
II. クマ出没の現状と被害の実態

A. 全国的な出没件数と人身被害の推移
近年、日本におけるクマの出没件数および人身被害者数は、憂慮すべきペースで増加しており、これは単年度の異常な事象ではなく、数年にわたる明確なトレンドとして認識されるべきです。過去10年間の全国クマ被害状況を見ると、顕著な変化が確認出来ます。2016年には人身被害が101件、被害者105人、死亡者4人であったものが、2018年には一時的に落ち着きを見せ、人身被害51件、被害者53人、死亡者0人となりました。
しかし、2020年には再び増加に転じ、人身被害143件、被害者158人、死亡者2人を記録しました。そして、2023年には過去最多となる人身被害198件、被害者219人、死亡者6人を記録しました。
この明確な増加トレンドは、クマによる人身被害が一時的な現象ではなく、もはや「新常態」として認識すべきであることを示唆しています。特に、2023年度の記録的な被害と2024年度の同水準での推移は、この問題が構造的な要因によって引き起こされている可能性が高いことを裏付けています。この「新常態」は、従来の偶発的な対応では不十分であり、より予測的かつ予防的な管理戦略への転換が急務であることを意味します。
クマの出没には季節性も関係しています。通常、奥山の食料が少なくなる夏になると、一部のクマは山を下りて人里等に出没し、奥山に果実が実りだす秋になると出没は収まる傾向があります。しかし、近年では秋になっても人里への出没が収まらず、平常の年の数倍のクマが出没する「大量出没」が社会問題となっています。また、北海道のヒグマの事例では、積雪が少ない年はヒグマが早く冬眠から覚め、春先の食料不足から人里近くをうろつくことが増えるという報告もあります。これは、気候変動がクマの季節的な行動パターンを変化させ、人里への出没時期や頻度を拡大させている可能性を示唆しており、従来の季節ごとの対策だけでなく、年間を通じた監視と対応の必要性を強調しています。
B. 地域別被害状況と「最激戦区」の分析
クマの被害は全国的に増加していますが、その発生には地域的な偏りが見られます。特に、東北地方の一部が「最激戦区」と化しており、その背景には地域特有の環境要因や社会構造の変化が影響していると考えられます。2023年度は秋田県で62件、岩手県で46件の人身被害が確認され、この2県だけで全国件数の半数超を占めました。福島県でも会津地方を中心にクマ被害が拡大しており、2024年6月16日時点で目撃件数が237件と、前年同期比で85件増加しています。
特定の地域での被害集中は、これらの地域がクマの生息環境と人間活動域の境界が曖昧になりやすい、あるいはクマの誘引物が多く存在する等の地域固有の脆弱性を抱えていることを示唆しています。この脆弱性は、地理的条件、植生、人口構造、地域経済活動等、多岐にわたる地域固有の要因によって形成されている可能性があり、画一的な対策ではなく、地域ごとの詳細な分析に基づいたオーダーメイドの対策が求められます。
C. 農作物被害と経済的影響
クマによる農作物被害は、人身被害と並び、地域住民の生活に直接的な影響を与える深刻な問題です。特に、果樹園や畑が狙われやすく、その被害額は増加の一途を辿っています。秋田県では2023年に1億6,665万1千円の農作物被害が発生し、これは県史上最大(従来の十数年平均の3倍超)という状況でした。
放置された農地や果樹園は、クマにとって魅力的な食料源となることが知られています。一度果樹を利用することを覚えたクマは、放置された里山や耕作放棄地を通って現在人が住んでいる集落まで近づき、そこの果樹に被害を与えるようになります。特に柿や栗等の果樹、生ゴミ、コンポスト、ペットフード等がクマを引きつける誘引物となります。
農作物被害の増加は、クマが人里の食料源に「学習」し、その味を覚えることで、より積極的に人里に出没するようになる悪循環を生み出しています。これは、単に被害を減らすだけでなく、クマに人里の食料源への依存を断ち切らせる為の、より戦略的な誘引物管理の必要性を示唆しています。農作物被害による経済的損失は、農業生産者の経営を圧迫し、離農や耕作放棄地の増加に繋がる可能性があります。これらの放置された土地は、更にクマの誘引物となり、被害を拡大させる悪循環を生むことになります。この問題は、特に高齢化や過疎化が進む中山間地域において、地域経済の持続可能性を脅かす多重的な影響を及ぼしていると言えるでしょう。
Table 1: 全国クマ出没件数と人身被害者数の推移 (2016-2023年度)
| 年度 | 人身被害件数 | 被害者数 | 死亡者数 |
| 2016 | 101 | 105 | 4 |
| 2018 | 51 | 53 | 0 |
| 2020 | 143 | 158 | 2 |
| 2023 | 198 | 219 | 6 |
| 2024 (7月暫定値) | 55 (死傷者) | – | – |
この表は、クマによる人身被害が単発的な現象ではなく、明確な増加傾向にあることを視覚的に示しています。特に2023年度の記録的な数字と2024年度の継続的な被害水準は、問題の深刻化と「新常態化」を裏付ける強力な証拠となります。これにより、読者は問題の緊急性と規模を瞬時に理解できます。
2016年以降の人身被害の推移を見ると、単年度の変動ではなく、明確な増加トレンドが見て取れます。特に、2023年度の過去最多記録と2024年度の同水準での推移は、この問題が一時的な異常ではなく、何らかの構造的変化によって引き起こされている「新常態」であることを強く示唆しています。このことは、従来の「出没時対応」だけでなく、長期的な視点に立った「事前予防」の重要性を強調するものです。
D. 「クマ擁護派」と「クマ殺す派」の対立構造と社会的分断
クマの出没問題は、その対応を巡って社会内で深刻な意見対立を生んでいます。この対立は、都市と地方の間に存在する自然観のギャップに起因しており、問題解決に向けた統一的なアプローチを困難にしています。北海道福島町でクマが駆除された後、道に抗議が殺到しましたが、その多くは北海道外からだったと報告されています。抗議の内容は「何でもかんでもクマを殺すな」「クマの命も大切だ」「麻酔銃を使う等もっと方法はあるはずだ」といった駆除反対意見から、「お前らがクマの駆除をしっかりしないからまた人が殺されたじゃねーか」「無能集団が!」といった駆除推進意見まで多岐にわたります。北海道ヒグマ対策室の職員は、長いものでは2時間にもわたる電話や誹謗中傷に近い暴言に疲弊していると報じられています。
駆除に抗議する都市部の女性は「みんな野生の生き物って、癒やしてるわけじゃない。クマは怖い汚い恐ろしいというイメージを植え付けられている。悪者じゃないよ、そう思わない?」とコメントし、「理想化された自然」観が都市と地方の対立を生むと指摘されています。実際、ある調査では「人間にとって危険を排除すべき」が20.8%、「被害増加の為駆除は仕方ない」が20.4%と、駆除を容認する意見が多数を占める一方、「熊も気の毒だが、人類が招いた自然破壊のしっぺ返しの一つ」という声も聞かれます。
都市住民が抱く「理想化された自然」観は、クマを「癒やしの存在」や「悪者ではない」と捉え、その駆除に強い抵抗を示す傾向があります。しかし、これはクマによる直接的な被害に直面する地方住民の現実とは大きく乖離しており、このギャップが感情的な対立と非建設的な批判を生み出しています。この乖離は、都市と地方の間に存在する情報格差と経験格差に根ざしており、効果的な問題解決には、双方の視点を理解し、対話を促進する努力が不可欠であることを示しています。
感情的かつ非建設的な批判やハラスメントは、クマ対策を担う自治体職員の士気を低下させ、業務遂行を著しく困難にしています。これにより、必要な対策が遅れたり、適切な判断が下されにくくなるリスクがあります。この状況は、クマ問題が単なる生態学的・管理学的課題に留まらず、社会心理学的・ガバナンス上の課題を内包していることを示しており、政策の実行力を確保する為には、こうした社会的摩擦への対処が不可欠であると言えます。
III. クマが人里に出るようになった根本原因の多角的考察

クマが人里に出没するようになった背景には、単一の原因ではなく、自然環境の変化、人間活動による直接的な影響、そして社会構造の変化が複雑に絡み合っています。これらの要因を全国的な視点から多角的に分析することで、問題の根源を理解し、効果的な共存策を導き出すことが可能となります。
A. 自然環境の変化とクマの生態系への影響
1. 気候変動の影響:食料源の不安定化と冬眠パターンの変容
地球温暖化は、クマの生態系に深刻な影響を与え、人里への出没を増加させる間接的な要因となっています。気候変動は、クマの主要な食料源の供給を不安定化させ、また冬眠のサイクルにも変化をもたらしています。気温の上昇が早まり、春の訪れが早まることで、冬眠から目覚めたクマが自然界で食料を見つけるのが難しくなるという報告があります。研究によると、生息地の平均気温がわずか1度上昇するだけで、食物連鎖に重大な変化が生じるとされています。ホッキョクグマの事例では、温暖化による海氷の溶解が狩猟期間を短縮させ、栄養不足を招いていることが示されています。氷の解け始めが1週間早まると、クマの体重が10kgも軽くなるという調査結果もあり、これはツキノワグマにも同様の食料不足リスクがあることを示唆しています。
温暖化に伴う食物源の変動により、クマは冬眠前に必要な栄養摂取が出来なかったり、適切なタイミングで食べ物を確保出来なかったりするリスクを抱えています。また、気温上昇は冬眠中のクマのエネルギー消費を通常以上に増加させる傾向があり、春が早く来た際にエネルギー不足に陥り、餓死する個体が出る可能性も指摘されています。冬眠期間が短縮されることで、クマの体力や健康に関わる問題が生じかねず、生態系バランスの崩壊を引き起こす可能性が高まっていると考えられます。
クマの出没は直接的には食料不足や生息地減少が原因と認識されがちですが、その背景には気候変動というより広範で、時には「見えない」要因が深く関与しています。温暖化は、クマの食料供給の不安定化、冬眠サイクルの乱れ、そしてそれに伴うエネルギー消費の増加と健康状態の悪化という形で、クマの生存戦略を根本から揺るがしています。これにより、クマが人里に食料を求めるリスクが高まり、人間との遭遇が増加している状況が生まれています。クマの冬眠パターンの変化や食物源の不安定化は、クマ個体群の健康だけでなく、クマが担う種子散布等の生態系内の役割にも影響を与え、生態系全体のバランスを崩壊させる可能性があります。このことは、クマ問題が単なる「害獣」対策ではなく、より広範な生物多様性保全の課題として捉えられるべきであることを示しています。
2. 森林環境の変容:生息地の縮小と質の低下
クマの本来の生息地である森林が、人間の活動によってその面積を縮小され、また質的な変化を遂げていることも、クマが人里に出る主要な原因の一つです。クマの生息域である森林が都市開発やスギの植樹によって縮小され、食料源を求めて人里に降りてくるという現象が報告されています。針葉樹であるスギを植えることで広葉樹が中心であった自然の森林が縮小し、クマの食料源であるどんぐり等の木の実や昆虫が不足しているとされます。過去10年で20%の森林が失われた地域では、クマの出没頻度が40%増加したという研究報告もあります。
ツキノワグマの大量出没に大きな影響を与えるのが、秋の食料不足、特にブナ類やナラ類等の堅果類の豊凶です。広葉樹林がスギ等の針葉樹林に転換されることは、クマにとっての食料源を大幅に減少させ、生息地の「緑の砂漠化」を引き起こしていると考えられます。この食料基盤の脆弱化は、堅果類の凶作年に特に顕著にクマを人里に押し出す要因となります。これは、森林管理の在り方がクマの行動に直接的な影響を与えていることを示しており、生物多様性を考慮した森林再生の必要性を強調するものです。
また、昔ながらの薪炭林が人の手で管理されなくなったことにより、秋に多くのドングリを実らせるようになり、ツキノワグマの良い生息地になりつつあるという側面もあります。これにより、クマの生息地と人間の生活域が近付いている状況が生まれています。これは、里山がかつて持っていた人間と野生動物の間の「緩衝地帯」としての機能が失われつつあることを示唆しています。里山の適切な管理は、クマの行動範囲を制限し、人里への侵入リスクを低減する上で極めて重要であると言えるでしょう。
B. 人間活動による生息環境への直接的影響
1. 大規模太陽光パネル設置による森林伐採と生息地分断
再生可能エネルギーへの転換は喫緊の課題ですが、その為の大規模太陽光パネル(メガソーラー)の設置が、クマの生息環境に深刻な影響を与えているという指摘があります。特に、山間部での無秩序な開発は、クマの生息地を直接的に破壊し、分断しています。東日本大震災以後、国は太陽光発電パネルを全国に普及させようと、固定価格買取制度を作り、建築基準法の適用外にして推進した結果、奥まった山の中にソーラーパネルが林立している状況が生まれています。
日本熊森協会のデータによると、2022年までに太陽光発電の為に切り倒された森林は2万3千ヘクタールに上り、これは東京ドーム3万個分に相当するとされています。日本の国土面積に占めるソーラーパネル設置率と発電量は世界一であり、パネル面積の合計は1400平方キロメートルにも及びます。太陽光発電を巡るトラブルとしては、土砂崩れ、濁水、景観悪化、反射光等が懸念されており、野生生物の生息地を奪うことへの懸念が表明されています。実際に、太陽光パネル周辺でクマが出没し、施設の安全性にも危険があった事例が報告されています。市街化調整区域内に設置された大規模太陽光パネルが生態系を破壊した結果、クマが里に下りてきているという指摘もあります。
太陽光発電はクリーンエネルギーとして推進されていますが、その大規模設置が森林伐採を伴う場合、クマの生息地を直接的に破壊し、生態系に負の影響を与えているという矛盾を抱えています。特に、2万3千ヘクタールという広大な森林が伐採された事実は、この「グリーン」な取り組みが、野生動物にとっては「ダーク」な現実をもたらしていることを示唆しています。これは、エネルギー政策と環境保全政策の統合的な視点と、より厳格な環境アセスメントの必要性を浮き彫りにしています。メガソーラーの林立は、単に生息地を減少させるだけでなく、クマの行動圏(オスで70km²、メスで40km²程度)を分断し、移動経路を遮断する効果を持つと考えられます。これにより、クマが新たな食料源や繁殖相手を求めて、これまで利用していなかった人里に迂回せざるを得なくなる可能性が高まると考えられます。
2. その他の森林伐採と開発行為
太陽光パネル設置以外にも、都市開発や林業活動における広葉樹林の伐採は、クマの生息環境を悪化させる要因となります。森林の減少はクマの生活圏に深刻な影響を及ぼしており、クマを都市部に押し出し、人間との遭遇を増やす原因になっていると指摘されています。
昔のクマは警戒心が強く、沢沿いを歩くにも身を隠せる藪の中を歩いていましたが、今や沢沿いにクマの足跡や糞を見つけることが珍しくなくなり、「クマ道」と化している荒廃林道も存在するようになりました。森林伐採や開発は、クマが身を隠して移動できる「藪」や「見通しの悪い場所」を減少させています。これにより、クマはより開けた場所や、かつては人間が利用していた林道・杣道を移動経路として利用せざるを得なくなり、結果として人との遭遇リスクが高まっています。これは、人間の活動がクマの「警戒心」という本来の行動パターンを変化させ、人馴れを促進する間接的な要因となっている可能性を示唆しています。
C. 社会構造の変化と人間活動域の拡大・曖昧化
1. 過疎化・高齢化による里山管理の放棄
日本の中山間地域では、人口減少と高齢化が深刻化しており、これにより里山の管理が放棄されるケースが増えています。この管理放棄は、人間とクマの生活圏の境界を曖昧にし、クマが人里に近付く誘引となっています。過疎化が進む地域では、クマの出没が増加する傾向にあることが報告されています。林業や農業に従事する人の高齢化により、手入れされずに放置された森林や耕作放棄地が増え、人間の野生動物の住処の境界線が曖昧になっているとされます。特に過疎化により放置された農地や果樹園は、クマにとって魅力的な食料源となります。離農や廃村により、収穫されない果樹がクマに利用され、一度果樹を利用することを覚えたクマは、放置された里山や耕作放棄地を通って集落まで近付くようになるという状況も生まれています。
手入れされずに伸びた草に隠れて消えつつある杣道は、既に「クマ道」と化していると指摘されています。過疎化・高齢化による里山管理の放棄は、放置された果樹園や耕作放棄地をクマにとっての「コンビニエンスストア」に変え、人里への誘引力を高めています。また、手入れされない里山はクマが身を隠す場所を提供し、かつての「緩衝地帯」が「クマの通り道」へと変貌していることを示唆しています。これは、社会構造の変化が直接的に生態系サービスの低下と人獣コンフリクトの増加に繋がるという、社会生態学的システムの脆弱性を示しています。
更に、少子高齢化が深刻な中山間地域では、「対策をしたくても出来ない」という声も多く、クマ対策への人的資源や予算の不足が深刻な課題となっています。このことは、問題の根本原因が地域社会の構造的弱点に深く根ざしていることを示唆しており、効果的な対策には、地域外からの人的・財政的支援や、新たな地域連携モデルの構築が不可欠であることを意味しています。
2. 不適切なゴミ管理と人馴れ個体の発生
人間が排出するゴミや放置された食物は、クマにとって容易に手に入る高カロリーな食料源となり、クマを人里に誘引する強力な要因です。一度人里の食料に味を占めたクマは「人馴れ」し、警戒心を失って繰り返し出没する「問題個体」となるリスクが高まります。人間の食料品やその臭いに馴れさせてはいけないとされており、生ゴミ等に触れる機会が増えることによって、クマは人里にまで生ゴミ等を探しに来るようになります。生ゴミ、コンポスト、ペットフード等がクマを引きつける代表的な誘引物であるとされています。
不適切なゴミ管理は、クマに人里の食料源の「味」を覚えさせ、人間への警戒心を低下させる「人馴れ」を急速に進行させます。一度人馴れしたクマは、人身被害のリスクが格段に高まる「問題個体」となり、最終的には駆除せざるを得なくなる可能性が高いです。このことは、ゴミ管理が単なる衛生問題ではなく、人命に関わる野生動物管理の最前線であることを示唆しており、予防的な対策の徹底が極めて重要であることを意味します。
ゴミは屋内で保管し、収集日当日の朝に出すようにすることが推奨されています。また、クマ対策ゴミ箱の設置や、頑丈なコンテナ、錠付きゴミ箱の導入が有効であるとされます。海外(カナダ、ルーマニア、アメリカ)では、クマが開けられないベアプルーフタイプのごみ箱が設置されており、カナダのキャンプ場では、クマ対策された食料ボックス(ベアキャニスター)やフードロッカーが設置されています。これらの海外事例は、クマに人里は「危険な場所」「食料がない場所」と学習させる「負の学習」が有効であることを示しています。これは、クマの行動を変容させる為には、単に誘引物を除去するだけでなく、積極的に人里への侵入を「不快な経験」と結びつける管理手法が有効であることを示唆しています。
IV. 人間とクマが平和的に共存する為の全国的な提言

人間とクマの平和的な共存を実現する為には、単一の対策に依存するのではなく、多角的かつ統合的なアプローチが必要です。ここでは、「人間優先」の原則を堅持しつつ、クマの生態を理解し、その行動変容を促す為の具体的な提言を行います。
A. ゾーニング管理と緩衝地帯の整備
人間とクマの生活圏を明確に区分し、それぞれの領域での管理方針を定める「ゾーニング管理」は、共存の基盤となります。人とクマ類との住み分けは、人の生活圏とクマ類の生息域を区分することで実現を図るとされています。特に、「コア生息地」(健全な個体群維持)、「防除地域」「排除地域」(人間活動優先)、そしてその間の「緩衝地帯」を地域の実情に合わせて設定する「ゾーニング管理」が重要とされています。この管理方法は、クマの生息状況が把握しにくいという課題に対し、地域個体群の安定維持と人身被害軽減という二つの目標を両立させる為の戦略的枠組みを提供します。これにより、不必要な捕獲を避けつつ、人命優先の原則を担保できる為、単なる対症療法ではなく、長期的な視点に立った持続可能な管理モデルへの転換を意味します。
里山に人間の手が入らなくなった現在、生長した雑木林を適切に整備し、クマが利用する頻度と身を隠す場所を減らし、人間との軋轢を減らすことが求められています。クマの通り道になりやすい川沿いや、森林と農地、宅地、通学路との間にクマが出没しにくい空間を作る「緩衝帯の設置」が有効であるとされます。具体的な緩衝帯整備としては、栗や柿等の果樹類の全伐採、スギ林の強度間伐、下草刈り、川沿い両サイドの刈り払い、耕作放棄地の解消、ヤギや牛を使った除草等が挙げられます。
緩衝地帯としての里山の機能回復は、単なる環境整備に留まらず、過疎化・高齢化で手入れが滞る地域社会の活性化と密接に結びつくものです。地域ぐるみでの緩衝帯整備は、住民間の協力体制を強化し、共通認識を醸成する機会となるでしょう。このことは、クマ問題の解決が、地域コミュニティの再構築とレジリエンス向上に貢献する可能性を示唆しています。しかし、少子高齢化が深刻な中山間地域では、「対策をしたくても出来ない」という声も多く、継続的な取り組みには予算だけでなく、人的支援も不可欠です。この為、地域社会全体で取り組む仕組み作りが、緩衝地帯の持続的な維持管理に不可欠であると言えます。
B. 誘引物管理の徹底と地域連携
クマを人里に誘引する食料源を徹底的に管理することは、出没を抑制し、人馴れ個体の発生を防ぐ上で最も直接的かつ効果的な対策です。これは、個人の意識改革と地域全体の協力が不可欠です。クマを引きつけてしまう誘引物として、柿や栗等、街中の果樹、生ゴミ、コンポスト、ペットフードが挙げられます。利用しなくなった道端や庭の果樹は伐採するか、実がついたらすぐに収穫することが重要です。コンポストは屋内で使うタイプを利用するか、においを抑える工夫をする(肉や魚、果物等強いにおいを放つものは控える)ことが推奨されます。生ゴミは屋内で保管し、収集日当日の朝に出すようにし、クマ対策ゴミ箱や頑丈なコンテナ、錠付きゴミ箱の導入が有効です。
クマの出没の多くは、人里にある容易な食料源、特に放置された果樹や不適切なゴミ管理に起因します。これらの誘引物を徹底的に除去・管理することは、クマに人里は「食料がない場所」と学習させ、人馴れを防ぐ上で最も効果的な「負の学習」となります。これは、人間の生活習慣の変革が、野生動物の行動変容を促す直接的な手段であることを示唆しています。
畑や果樹園には電気柵のような罠を周辺に設置して、クマの侵入を防ぐ必要があります。電気柵は、クマの侵入防止に非常に効果的であり、クマに「この場所は恐い」と学習させる強力なツールとなります。WWFジャパンと島根県のプロジェクトでは、柿園でのクマ防除対策として電気柵の導入とクマに柿の味を覚えさせない工夫が成功しています。しかし、その設置には初期費用、維持管理の手間(草刈り、電圧チェック、充電)、そして地域全体での協力が不可欠であり、特に高齢化地域ではこれが課題となります。このことは、技術的な解決策だけでなく、それを支える社会的な仕組みや支援体制の重要性を示唆しています。
Table 2: 電気柵の効果的な設置・運用ポイント
| ポイント | 詳細な運用方法と効果 | 関連データソース |
| 通電時間 | 日中も電源ONにする。日中活動するクマもいる為、電源を切らずに通電し、一度侵入して味を占めたクマが痛みに動じず侵入するのを防ぐ。電源入れ忘れ防止にもなる。 | 🐻 |
| 設置範囲 | 隙間なく、畑や果樹園全体を囲む。クマは学習能力が高く、隙間や弱点を見つけるとそこから侵入を試みる為、徹底した囲い込みが重要。 | 🐻❄️ |
| 漏電防止と維持管理 | 定期的な下草払いと電圧チェックが重要。柵に雑草等が大量に触れていると電圧が大幅に低下し、効果がなくなる。バッテリーの定期的な充電も必要(ソーラー式も検討)。 | 🧸 |
| 周辺環境の整備 | 電気柵に触れずに園内に侵入出来るような、柵周辺の木は伐採や枝落としをする。クマが滑って登れないように、立ち木にトタンを巻きつけることも有効。 | 🐻 |
| 柵の高さと段数 | クマは電気柵の下をくぐろうとする為、1段目は地上高10~15㎝程度が効果的(2段目からは20㎝程度)。2重張りも穴掘り防止や学習に役立つ。 | 🐻❄️ |
| 対策時期の絞り込み | 収穫前から収穫終了までの期間のみ電気柵を張るだけでも効果がある。ただし、通電しない期間は撤去し、「電気柵は恐くない」と学習させないようにする。 | 🧸 |
| 農家間の協力 | 集落等で話し合い、協力して、隣接した農園全体を囲うようにする。これにより、維持管理の省力化にも繋がる。 | 🐻 |
| 誘引エサの工夫 | 周辺に容易に利用出来る果実があると、危険を冒してまで捕獲檻には入らない。捕獲の為の誘引エサには、果実以外の物(例:はちみつ)を使うことを推奨。 | 🍯 |
この表は、電気柵がクマ対策として有効であるだけでなく、その効果を最大限に引き出す為の具体的な設置・運用ノウハウを体系的に提示しています。単に「電気柵を設置する」というだけでなく、クマの生態や学習能力を考慮した運用が不可欠であることを明確にし、実践的なガイドラインとして機能します。電気柵は「6,000~9,000ボルトの高圧な電気を流し、柵に触れたヒグマにショックを与え、侵入を防ぎます」とあり、クマに「この場所は恐い」と学習させる効果が確認されています。これは、クマの学習能力を逆手に取った効果的な物理的障壁であり、人身被害や農作物被害の軽減に大きく貢献します。しかし、その設置と維持管理には継続的な労力と費用が必要であり、特に「少子高齢化が深刻な中山間地域では、『対策をしたくても出来ない』という声も多い」という課題があります。この為、電気柵の普及には、行政による補助だけでなく、人的支援や地域住民間の協力体制の構築が不可欠であることを示唆しています。
C. クマの行動変容を促す対策
人里に出没するクマの行動を変容させ、人間への警戒心を回復させることは、駆除に頼らない共存の重要な柱です。これには、積極的な追い払いと、人間側の適切な行動が求められます。クマは人の気配に敏感で、人間と出会わないよう用心しながら活動しており、人の気配に先に気付いて隠れる場合が多いとされます。この為、クマから早く気付いてもらえるよう、また、人間もクマに出会わないよう用心することが、不用意なクマとの出会いを回避することに繋がります。
山中ではクマ除け用の鈴の携帯、ラジオで音を出す、手を叩く、声を出す(「おーい!」等)などが有効です。見通しの悪いところ、藪や沢、山際の林、洞穴等、クマが隠れていそうな場所に注意を払う必要があります。山菜採りやきのこ狩りなどで夢中になりがちですが、時々周囲に注意し、藪の中等見通しのきかない場所には不用意に入り込まないことが推奨されます。なるべく一人で行動せず、二人以上で行動するべきであり、人数が多いほどクマの側から警戒してくれる傾向があります。子グマを見つけても近付かず、近くに母グマがいる可能性が高い為、速やかにその場所を離れるべきです。襲われそうになったら撃退スプレーを噴射することは最終手段であり、遭遇しないための対策が重要です。クマの攻撃は人間の頭部に集中する傾向がある為、撃退スプレーがない場合は、首の後ろで両手を組みうつ伏せになる等防御姿勢をとることが推奨されます。
クマは学習能力が高く、人間との遭遇を「不快な経験」と結びつけることで、人里への出没を抑制できることが知られています。軽井沢では、ベアドッグ(クマの匂いを察知し追い払う訓練を受けた犬)がクマ対策で活躍しており、2004年の導入後、人間活動エリアでの人身事故は起きておらず、商業地・住宅地での目撃も大幅に減少しています。ベアドッグによる追い払いは、クマが人間を「近付いてはいけないもの」と学習した為と考えられています。また、捕獲したクマにベアドッグの力を借りながら人の怖さを学ばせる「学習放獣」も実施されています。これらの手法は、クマを単なる「害獣」としてではなく、学習可能な動物として捉え、その行動を管理するというパラダイムシフトを示唆し、駆除以外の選択肢として共存の可能性を広げています。
クマとの遭遇を避ける為の人間側の予防行動は、最も基本的ながら最も効果的な対策です。多くのクマは人間を避ける傾向がある為、人間の存在を事前に知らせることが重要となります。このことは、共存が技術や政策だけでなく、個々人の意識と行動にかかっていることを示唆しており、継続的な啓発活動の重要性を強調するものです。
D. 生息環境の保全と回復
クマが人里に出没する根本原因の一つが生息地の質の低下と分断であることから、その生息環境を保全・回復させることは、長期的な共存戦略において不可欠です。クマの生息域である森林が都市開発やスギの植樹によって縮小され、食料源を求めて人里に降りてくるという問題が指摘されています 。針葉樹であるスギを植えることで広葉樹が中心であった自然の森林が縮小し、クマの食料源であるどんぐり等の木の実や昆虫が不足しているとされます。
森林生態系の保護を図る為、希少な野生生物の生息地等を保護・管理する保護林を中心にネットワークを形成する「緑の回廊」が設定されています。緑の回廊は、分断された動植物の生息地を繋ぎ、生態系の連結性を強化し、生息地の拡大と保護、遺伝的多様性の確保に役立つとされています。海外ではタンザニアのセレンゲティ国立公園やドイツで緑の回廊が設定され、野生生物の移動を促進する成功事例があります。日本でも秩父山地や四国剣山系でツキノワグマに注目して「緑の回廊」が設定されていますが、ツキノワグマの実態を伴っていないという指摘や、生息域の拡大が必要という課題も存在します。
緑の回廊は、分断されたクマの生息地を連結し、遺伝的多様性を確保することで、個体群の健全性を維持し、結果的にクマが人里に下りる必要性を低減する潜在力を持っています。しかし、日本の緑の回廊は必ずしもクマの実際の行動圏と一致しておらず、実効性に課題があることが指摘されています。このことは、単に「回廊」を設定するだけでなく、科学的な調査(発信機追跡等)に基づき、クマの行動実態に即した設計と継続的なモニタリングが不可欠であることを示唆しています。
スギ等の針葉樹林の拡大は、クマの主要な食料源である堅果類を減少させ、生息地の質を低下させています。広葉樹林の再生は、クマの食料基盤を強化し、人里への出没動機を根本的に低減する長期的な解決策となります。このことは、林業政策が単なる木材生産だけでなく、生態系保全の視点を統合する必要があることを示唆しています。
また、大規模太陽光パネル設置による広範な森林伐採(2022年までに2万3千ヘクタール)は、クマの生息地を直接的に破壊し、分断しています。このことは、再生可能エネルギー開発が環境に与える負の影響を最小限に抑える為、より厳格な環境アセスメントと、生態系への影響を考慮した設置規制が不可欠であることを示唆しています。特に、水源地に近い山間部での設置は、土砂崩れや水質汚染のリスクも伴う為、慎重な検討が求められます。
V. 課題と今後の展望:持続可能な共存社会を目指して
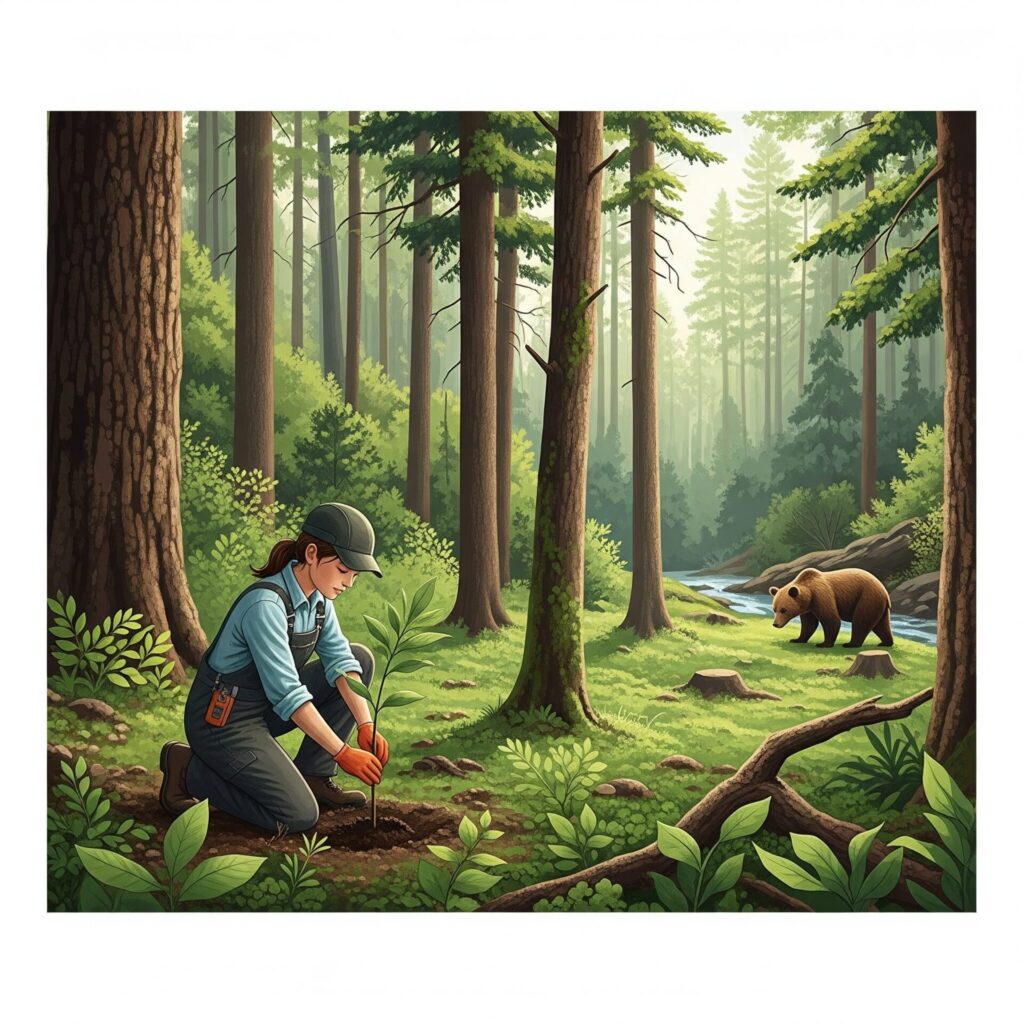
人間とクマの共存は、短期的な対症療法では解決出来ない複雑な問題であり、長期的な視点に立った継続的な取り組みと、社会全体の意識変革が不可欠です。
A. 対策実施における課題:人的資源・予算・継続性
効果的なクマ対策の実施には、多大な人的・財政的リソースと、長期的な継続性が求められますが、特に地方ではこれらの確保が困難な状況にあります。少子高齢化が深刻な中山間地域では、「対策をしたくても出来ない」という声も多く、実施には予算だけでなく、人的支援も必要であるとされます。クマ対策に関わる人員の配置や、日常からの関係機関による合同研修や意識の共有が必要であり、クマの出没は夜間、早朝、休日等予測不能な時間に発生する為、あらゆる可能性を考えた連携体制の構築とシミュレーションが不可欠です。クマ対策員の増員により地域に密着した対応が必要であるとされており、人口減少や狩猟者不足が進む中、効果的な対策としてガバメントハンターの導入も検討されています。
地方における人口減少と高齢化は、クマ対策に必要な人的資源と予算の不足を招き、これが対策の継続性を困難にしています。このリソース不足は、問題の根本原因である里山管理の放棄を更に加速させ、クマの出没を増加させる悪循環を生んでいます。このことは、クマ問題の解決が、地方創生や地域活性化といったより広範な社会課題と密接に連携する必要があることを示唆しています。
クマの出没が予測不能な時間帯に発生するという特性は、自治体の緊急対応体制に大きな負荷をかけています。人員不足の中で、24時間体制での対応や迅速な現場確認、住民への情報周知を行うことは極めて困難であり、これが被害拡大のリスクを高めています。この状況は、平時からの訓練、関係機関との連携強化、そして地域住民の協力体制の構築が不可欠であることを示唆しています。
B. 地域住民と都市住民の意識ギャップの解消
クマ問題における「クマ擁護派」と「クマ殺す派」の対立は、主に都市住民と地方住民の間に存在する自然観やリスク認識のギャップに起因しています。このギャップを解消し、共通理解を醸成することが、持続可能な共存社会への第一歩となります。「理想化された自然」観が世間に浸透しており、ここに都市と地方の根深い二項対立が入り込んでいると指摘されています。都市部は第三次産業が中心で人口が集中し、多様なサービスが揃う一方、地方は第一次産業が中心で人口が少なく、自然環境に恵まれるが不便さもあるという違いがあります。自治体への批判の多くが道外(都市部)から寄せられているという事実は、この意識ギャップを裏付けています。町民からは「クマをかばうならクマの近くに掘っ立て小屋を建てて、住んでごらんと言いたくなりました」といった憤りの声も聞かれます。
都市住民は自然を「癒やしの対象」や「保全すべきもの」として遠隔的に捉える傾向がある一方、地方住民は自然を「生活の場」であり、時には「脅威」として直接的に経験しています。この経験と価値観の乖離が、駆除をめぐる感情的な対立の根源となっています。このギャップを埋める為には、地方の現実を都市住民に伝え、都市住民の自然観を地方住民が理解するような、双方向の対話と教育の機会が不可欠です。
メディア報道はクマ問題に対する世論形成に大きな影響を与えますが、感情的な側面や断片的な情報が先行することで、対立を煽るリスクがあります。正確でバランスの取れた情報提供に加え、市民が多様な視点から情報を評価出来るメディアリテラシーの向上が、建設的な議論を促進する為に重要であると考えられます。
C. 先進技術の活用:GPS追跡、AIによる早期発見システム
クマの生態把握と出没予測の精度向上は、効果的な対策を講じる上で不可欠です。先進技術の導入は、この分野において大きな可能性を秘めています。クマの生息状況が把握しにくいという課題がある中で 、赤外線カメラ搭載ドローンによる個体位置把握や、AI技術を活用した早期発見システムが今後期待される対策として挙げられています。ソーラーパネルとGPS追跡の統合は、野生動物保護と監視に多くの利点をもたらし、動物の位置や生息地の変化を把握し、保護活動を効果的に計画・実施出来るとされます。GPS追跡は野生動物の移動パターンや生態を詳細に把握する為に必要であり、エネルギーの供給が安定することで、監視システムの連続稼働やオンラインデータの送信にも寄与します。軽井沢では、発信器を付けたクマをベアドッグと共に追い払い、市街地でのクマの出没数を減らすことに成功しています。
クマの生息状況が把握しにくいという課題に対し、GPS追跡やドローン、AI技術の活用は、クマの行動パターン、移動経路、生息地の利用状況をリアルタイムで「可視化」する画期的な手段となります。これにより、より科学的根拠に基づいたゾーニング管理や緩衝地帯の整備が可能となり、効果的な予防策を講じることが出来ます。これは、野生動物管理におけるデータ駆動型アプローチへの転換を示唆しています。
AIを活用した早期発見システムは、クマの出没を迅速に検知し、被害が発生する前に追い払い等の対応を可能にします。これにより、人身被害のリスクを低減し、クマが人馴れする前に山へ返す「学習放獣」の機会を増やすことが出来ます。このことは、被害発生後の「対症療法」から、被害を未然に防ぐ「予防」へと管理の重心を移す上で不可欠な要素となり、人命の安全確保とクマの不必要な駆除回避の両立に貢献します。
D. 国際的な共存事例からの学びと日本への適用
日本と同様にクマと人間が共存する課題を抱える海外の国々では、様々な対策が講じられています。これらの成功事例から学び、日本の状況に合わせて適用することは、効果的な共存戦略を構築する上で有益です。
アメリカ(コロラド州)では、クマがゴミを漁らないようにベアプルーフタイプのゴミ箱が置かれ、窓やドアに鍵をかけるよう呼びかけられています。コロラド州では、市街地に近寄るクマをゴム弾で退散させ、安易に殺さずに解決する姿勢が見られます。ただし、何度も捕獲されたり市民の安全を脅かしたりすると安楽死処分となることもあります。ルーマニアでは、クマが開けられないゴミ回収容器や、民家に設置されたクマよけの電気柵が導入されています。カナダのキャンプ場では、クマ対策された食料ボックス(ベアキャニスター)や、分厚い金属で覆われたフードロッカーが設置されています。街中のゴミ箱もクマ対策が施され、開けられないようになっています。
これらの海外事例は、人間側の行動変容と、クマに人里での食料獲得が困難である、あるいは人里は不快な場所であると「学習」させることの重要性を示唆しています。特に、クマの学習能力を逆手に取り、「負の学習」を促すことで、人里への出没を抑制する効果的な戦略が構築されています。日本においても、誘引物除去の徹底に加え、人里への侵入を「不快な経験」と結びつける積極的な追い払い(ベアドッグの活用等)や、ゴミ管理の徹底による食料源の遮断が、クマの行動変容を促し、人馴れを防ぐ上で不可欠であると考えられます。
国際的な事例から学ぶべきは、共存が単なる「保護」ではなく、人間と野生動物双方の行動を管理し、調整する動的なプロセスであるという点です。これには、地域社会、行政、研究機関、そして市民が一体となって取り組む、多角的なアプローチが求められます。
VI. 結論と提言
日本におけるクマ出没問題は、気候変動による生態系への影響、大規模太陽光パネル設置や広葉樹林の減少といった人間活動による生息地の破壊と分断、そして過疎化・高齢化に伴う里山管理の放棄や不適切なゴミ管理といった社会構造の変化が複合的に絡み合って深刻化しています。この問題は、人身被害や農作物被害の増加、地域経済への打撃、更には都市と地方の間に存在する自然観のギャップによる社会的分断といった多層的な課題を内包しています。
本報告書は、「人間優先」の原則を堅持しつつ、クマとの平和的な共存を目指す為の以下の具体的な提言を行います。
- ゾーニング管理の徹底と緩衝地帯の整備:
- クマの「コア生息地」、人間活動を優先する「防除地域」「排除地域」、そしてその間の「緩衝地帯」を明確に区分し、地域の実情に応じた管理方針を策定すべきです。
- 里山の適切な整備(果樹の伐採、スギ林の間伐、下草刈り、耕作放棄地の解消等)を通じて、人間とクマの生活圏の境界を明確化し、緩衝機能を回復させる必要があります。これは、地域コミュニティの再構築と連携強化の機会ともなり得ます。
- 誘引物管理の徹底と地域連携:
- クマを人里に誘引する食料源(放置果樹、生ゴミ、コンポスト、ペットフード等)の徹底的な除去と管理を、個人レベルおよび地域レベルで推進すべきです。
- 電気柵の設置を積極的に補助・推奨し、クマの学習能力を活かして人里への侵入を「不快な経験」と結びつける運用を徹底すべきです。特に、高齢化が進む地域では、設置・維持管理への人的・財政的支援が不可欠です。
- クマの行動変容を促す対策の強化:
- 人間側の予防行動(クマ鈴の携帯、複数人での行動、見通しの悪い場所への不用意な立ち入り回避等)の徹底を、継続的な啓発活動を通じて促すべきです。
- ベアドッグの導入や「学習放獣」といった、クマに人間への警戒心を回復させる積極的な追い払い手法を、全国的に普及・展開すべきです。これは、駆除以外の選択肢を広げ、共存の可能性を高めます。
- 生息環境の保全と回復:
- 広葉樹林の再生を推進し、クマの主要な食料源である堅果類の供給を安定させることで、人里への出没動機を根本的に低減すべきです。
- 「緑の回廊」の実効性を高める為、クマの実際の行動圏に基づいた科学的な調査・設計を行い、継続的なモニタリングと見直しを行うべきです。
- 大規模太陽光パネル設置においては、より厳格な環境アセスメントを義務付け、生態系への影響を最小限に抑える為の設置規制を強化すべきです。特に、水源地に近い山間部での無秩序な開発は避けるべきです。
- 社会的な合意形成とリソースの確保:
- 都市住民と地方住民の間に存在する自然観やリスク認識のギャップを埋める為、双方の視点を理解し、対話を促進する教育プログラムや地域間交流の機会を創出すべきです。
- クマ対策を担う自治体職員の負担を軽減する為、国や都道府県による人的・財政的支援を強化し、緊急対応体制の構築と訓練を継続的に実施すべきです。ガバメントハンターの導入も検討されるべきです。
人間とクマの共存は、一朝一夕に達成出来るものではありません。しかし、多角的な視点から問題の根本原因を理解し、科学的根拠に基づいた長期的な戦略を、社会全体で粘り強く実行していくことで、人間と野生動物が調和して暮らせる持続可能な社会の実現は可能であると確信します。
一人ひとりが共存の為の知恵と行動を模索していくことが求められている〜。
【引用・参考文献】
▶︎ 2025年最新版|全国のクマ出没データ、過去10年で何が変わったのか?
▶︎ 「熊を殺すな!」「可哀想だ!」…北海道でヒグマによる事件が発生→駆除もクレーム殺到。安全圏の遠方からクレームを入れる人々の心理とは?
▶︎ 「無能集団が!」「命を何だと思っている」クマ駆除めぐり暴言などが明らかに 北海道に苦情殺到
▶︎ クマとの共生は可能?みんなの意見は【アンケート結果発表】