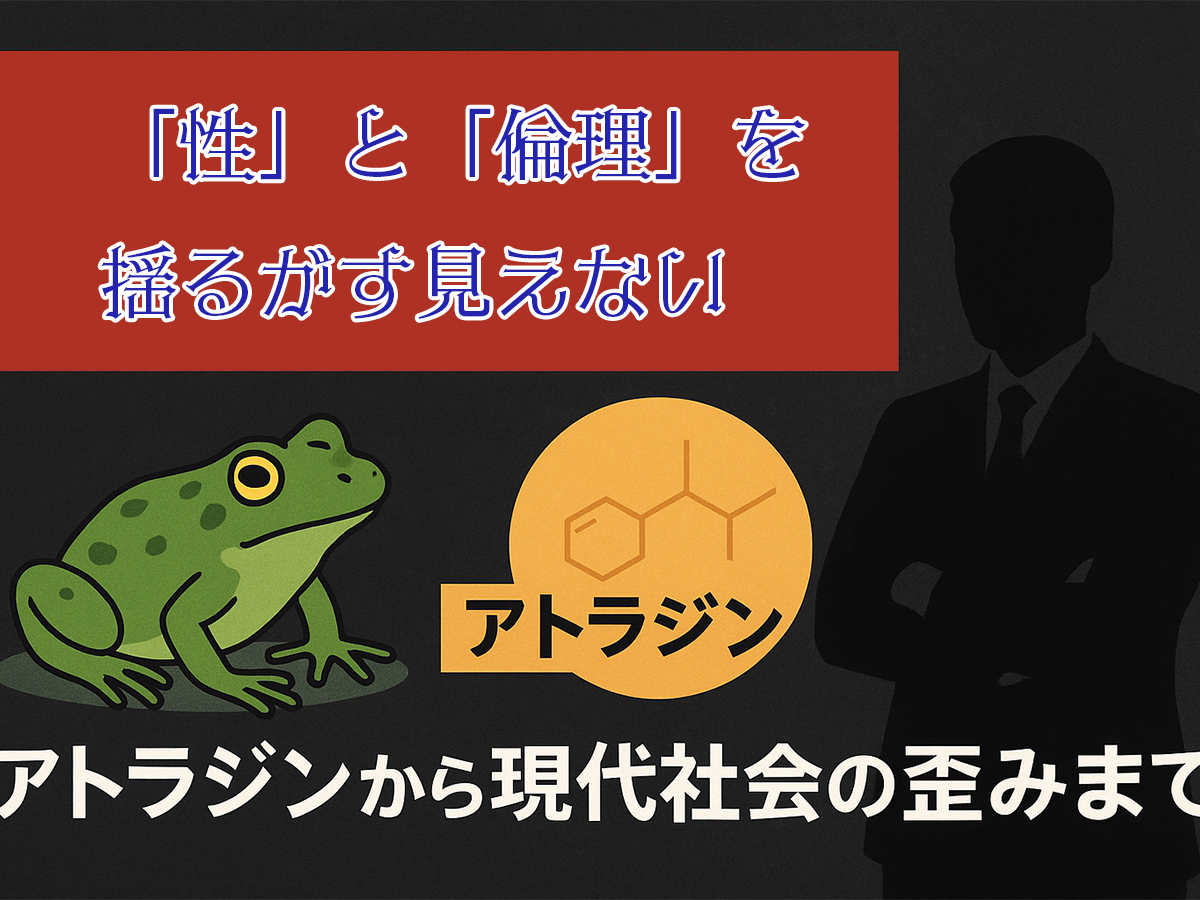エリザベート・バートリについて記事を書こうと思った理由。たまたまその人の物語を描いた歌というものがあって拝見したのですが、妙にイライラしてしまい、そのイライラが不快だったからなのかはわからないのですが(何かキャッチした?)、
世間のイメージ=必ずしもそうではない為調べた結果こうなりました。
はじめに:歴史の闇に堕ちた肖像 — エリザベート・バートリを巡る多角的な考察

本報告書は、16世紀のハンガリーに実在したとされる「血の伯爵夫人」エリザベート・バートリについて、多角的な視点からその人物像と伝説の真相を解明する。歴史的記録、政治的文脈、そして現代の文化における再解釈に至るまで、様々な側面を包括的に検証することで、広く知られる伝説の裏に隠された複雑な物語の核心に迫る。
なお、オーストリア皇妃として知られるエリザベート(愛称:シシィ)とは、時代も国も異なる全くの別人である。両者は歴史上の著名な女性という共通点を持つが、今回の主題であるエリザベート・バートリは、16世紀末から17世紀初頭にかけて生きたハンガリー王国の貴族であり、世紀を越えて語り継がれる残虐な伝説の当事者である。大衆文化においてしばしば混同される両者を冒頭で明確に区別することは、歴史的正確性を担保する上で極めて重要である。
エリザベート・バートリ(1560年-1614年)の生涯は、単なる残虐な犯罪者の物語として片付けられるにはあまりに複雑である。彼女の肖像を深く理解するには、彼女が生きた16世紀末のハンガリー王国の不安定な社会、政治、そして法的な枠組みを無視することは出来ない。この時代は、彼女の運命と伝説が形成される上で決定的な背景となった。
彼女の父親はジョージ6世・バートリ。
父親が吸血鬼であるという説は、歴史的事実ではなく、彼女の残虐な行為から生まれた伝説や、後世の創作物によって作られたものだ。
※バートリ氏はハンガリーのバートリ家の「バートリ」であり、イギリスのジョージ6世とは関係がありません。
表記・呼称について
彼女の名前は表記・呼称が複数存在します。
ハンガリー語: バートリ・エルジェーベト(Báthory Erzsébet)
ドイツ語: エリゼベート・バートリ
英語: エリザベス・バソリー
ハンガリー語では姓が先にくる為、「バートリ・エルジェーベト」が最も正確な表記と言えます。
第1章:歴史の舞台:名門バートリ家と時代の背景
1.1. 名門バートリ家の系譜と生い立ち
エリザベート・バートリは、中世ハンガリー王国の有力貴族であるバートリ家と、もう一つの権力であるナーダシュディ家の血を引く、極めて恵まれた特権階級に生まれた。彼女の叔父はポーランド王ステファン・バートリ、兄はハンガリーの王室判事という、当時の欧州貴族社会でも屈指の地位にあった。
彼女が生まれた時代は、1526年のモハーチの戦いを経て、ハンガリー王国がオスマン帝国とハプスブルク帝国によって分割支配されるという、社会と政治が著しく不安定な時期であった。この混乱の中、貴族たちは広大な領地を独立的に支配し、法が及ばない「法の灰色の領域」で自らの権力を振るっていた。こうした環境は、貴族間の暴力的な報復行為や、農奴に対する残虐な振る舞いが常態化する土壌を作り出した。
幼少期に公開処刑を目撃する等の暴力的な光景に晒されたことが、彼女の心理形成に影響を与えた可能性も指摘されている。
エリザベート・バートリの一族は近親婚を繰り返しており、それが彼女の精神状態に影響を与えたのではないか、という説は広く知られています。
近親婚と精神疾患の関係
バートリ家は、中世のヨーロッパ貴族によく見られたように、血統と財産を守る為、親戚同士で婚姻を繰り返していました。エリザベートの両親も従兄妹でした。
歴史家や心理学者の間では、近親婚は遺伝的な疾患や精神的な問題を抱えるリスクを高めると考えられています。バートリ家には、てんかんや奇行を示す者が多かったとされ、エリザベート自身も幼い頃にてんかんの発作を起こしていたという記録が残っています。
しかし、これらの事実が彼女の残虐な行為の直接的な原因であったと断定することは出来ません。近親婚による遺伝的な問題が彼女の行動に影響を与えた可能性はありますが、それだけが彼女を「血の伯爵夫人」にしたわけではない。
彼女が本格的に凶行に走るようになったのは黒騎士とあだ名された夫ナーダシュディ・フェレンツ2世との死別の後で(一説では夫が彼女に加虐性をもたらしたとも言われている)、それ以前は生まれながらのエキセントリックな性格と上述の家庭の狂気でおかしな点こそあったものの、それなりの慈善事業も行っていたという。
当時の貴族社会の閉鎖的な環境等、複数の要因が絡み合っていたと考えられています。
1.2. 夫ナーダシュディ・フェレンツとの結婚生活
1575年、彼女は15歳でハンガリー軍司令官のフェレンツ・ナーダシュディと結婚した。夫婦仲は良好で、5人の子供をもうけたとされている。彼女は結婚の際、化粧料としてチェイテ城を与えられた。夫がオスマン帝国との戦争で長期にわたり城を空けることが多かった為、彼女は事実上、自身の広大な領地を管理する実質的な支配者となった。夫の死後、彼女の行為は一層エスカレートしたとされるが、一部の資料は残虐行為の兆候が夫の存命中から始まっていたことを示唆している。また、彼女が幼少期からてんかん発作に苦しんでいたという説もあり、当時の民間療法として行われた非患者の血を体に擦り付けるという治療法が、後の彼女の「血」への執着の遠因になった可能性も示唆されている。
映画のあらすじでは、若くして軍司令官と結婚したエリザベートが、不安定な精神状態から次第に残虐な性格を現し始めると描かれているが、これはフィクションにおける人物描写である。歴史的には、夫フェレンツが戦場で長期にわたり不在であったことが、彼女のその後の人生に何らかの影響を与えた可能性が指摘されている。
1.3. 政治的陰謀説の真実性
エリザベートによる残虐行為の噂は、夫の死後、特に顕著になったとされる。当初、被害者は領地の農奴の娘たちであったが、次第に「礼儀作法を教える」という名目で誘い出された下級貴族の娘にも及ぶようになった。これにより、事件は貴族社会の注目を集めるようになり、1610年に彼女は遂に逮捕された。彼女の逮捕に至るまでには、300人以上の証人が拷問や殺害に関する証言を行ったとされ、中には虐殺された被害者や投獄された少女の存在も報告されている。
しかし、エリザベート自身は生涯、正式な裁判にかけられることはなかった。その代わりに、彼女の共犯者とされる使用人たちが裁判にかけられ、処刑されたのである。この出来事は、彼女がその莫大な富と政治的影響力によって法から保護されていたことを明確に物語っている。彼女の特権階級としての地位が、彼女を告発から守る強固な盾として機能したことは明白である。当時のハンガリーの法慣習書『トリパルティトゥム』は、農奴の権利をほとんど認めず、貴族の搾取を保護していた事実も、この状況を裏付けている。彼女の莫大な富と、ハプスブルク帝国にとっての政治的な脅威が、告発の背景にあるという説も存在する。
彼女の没落は、貴族階級が平民の告発から保護される一方で、より大きな権力構造の中での政治的な駆け引きの犠牲となったことを示している。真の恐怖は、彼女のサディズムだけでなく、それを可能にし、処罰の在り方を決定付けた体制的な不平等にこそあると言える。
エリザベートの逮捕と終身刑が、ハプスブルク家とバートリ家の政治的対立に起因する政治的陰謀であったという説は、広く語られてきた物語である。この説は、彼女を権力闘争の犠牲者として描くことで、悲劇のヒロインとしての物語に説得力を持たせる。ハプスブルク家とドイツの領邦君主との間には、宗教対立や政治的優位性を巡る争いがあり、この時代背景が俗説の温床となったと考えられる。
しかし、学術的な検証は、この通説に疑問を投げかけている。ある論文によれば、彼女の逮捕時にはすでに彼女の財産や権力は以前より大幅に減少しており、当時の未亡人の地位がハプスブルク家にとって脅威とみなされることはなかったと結論付けられている。このことから、彼女の逮捕は権力や富を巡る陰謀ではなく、残虐行為そのものによるものであった可能性が高いと示唆されている。
広く信じられている俗説は、必ずしも歴史的事実を反映しているわけではなく、むしろ、時代の人々が歴史に何を求めていたかを映し出す鏡であると考えることが出来る。悲劇のヒロインという物語は、単なる連続殺人鬼の物語よりも、権力構造や人間の不条理という普遍的なテーマを語る上で、より深く人々の心に響くからである。
第2章:血塗られた伝説の虚実:600人伝説と吸血鬼伝承の真相
歴史の闇に葬られたエリザベートの肖像は、時を超えて様々な物語によって蘇り、独自の生命を与えられてきた。特に、18世紀以降、彼女の物語は吸血鬼伝説と融合し、「血の伯爵夫人」という不滅の悪女像を確立するに至る。
彼女の物語は、18世紀にヨーロッパで広まった吸血鬼伝説と自然に結びついた。この融合は、トゥーロツィの記述が広く知られるようになったことで加速した。ブラム・ストーカーの小説『ドラキュラ』のインスピレーション源の一つとなったという説は、彼女の物語がヴラド・ツェペシュと並んで、吸血鬼という恐怖のアーキタイプを形成する上で重要な役割を果たしたことを示唆している。
彼女の行為が「吸血鬼的」な性質を持つと見なされた結果、彼女は「血の伯爵夫人」の異名で知られるようになった。この伝説は、彼女の残虐性を単なる犯罪ではなく、超自然的な力や欲望と結びつけることで、より大きな物語的インパクトを獲得した。この物語の変容は、歴史上の複雑な事件を、社会が理解しやすい倫理的な枠組みへと再構成する文化的メカニズムでもある。権力を振るい、人々の想像を絶する怪物的な行為を成した女性の存在は、単なる「貴族のサディズム」では説明しきれない。彼女を「美への執着に取り憑かれた魔女」や「吸血鬼」として描くことで、社会は彼女の行為に理由を与え、それを寓話的な教訓として受け入れることを可能にしたのである。
伝説の核心にある「若さと美への執着」という普遍的なモチーフは、現代においても人々を魅了し続けている。彼女の物語は、このテーマを核に、文学、映画、漫画といった様々なメディアで繰り返し再解釈されている。
例えば、ある評伝は彼女を「哀れさ」を感じさせる存在として描き出し、単なる悪女ではない心理的な側面を掘り下げようとしている。また、日本の伝奇漫画では、呪われた血脈や半陰陽の巫女といった、より猟奇的で幻想的な要素が付け加えられ、歴史的伝記というよりもダークファンタジーのジャンルとして再構築されている。このように、彼女の物語は、単一の静的な肖像ではなく、時代や文化の鏡として多様に変化し続けている。
2.1. 「600人」という数字の神話性
エリザベート・バートリは、「600人以上の若い女性を拷問の末に殺害した史上最悪の連続殺人鬼」として知られている。この数字は、彼女の伝説を特徴付ける最もセンセーショナルな部分である。
しかし、歴史的記録と照らし合わせるとこの数字は大きく乖離していることが明らかになる。裁判における正式な認定被害者数は80人であり、共犯者の拷問による自白では、その数は36人から51人と幅がある。また、ハンガリー王マーチャーシュ2世の手紙では、被害者数は300人と認識されていたとされている。
伝説における被害者数の根拠となった可能性が指摘されているのは、彼女の記録に650人と記載されていたという一つの証言である。しかしこの証言は伝聞であり、その情報を直接見たという人物の証言ではない。これは、伝説がどのようにして特定の数字を取り込み、誇張されていったかを示す典型的な例である。
以下の表は、伝説と歴史的記録における被害者数の違いを整理したものである。
| 情報源 | 被害者数 | 特記事項 |
| 伝説/民間伝承 | 600人以上、650人 | 広く知られる最も有名な数字 |
| 裁判の公式認定 | 80人 | 裁判における正式な認定数 |
| 共犯者の自白 | 36人〜51人 | 拷問下での証言であり信頼性は低い |
| エリザベートの記録の噂 | 650人 | 裁判で証言された伝聞情報 |
この比較から、「600人」という数字が歴史的事実ではなく、あくまで伝承・風聞に過ぎないことが一目瞭然となる。歴史が彼女を罪に問う一方で、伝説は彼女を不滅の怪物へと仕立て上げたと言える。
2.2. 「血の入浴」伝説の起源と文化的意味
エリザベートの物語が今日に至るまで語り継がれている最大の理由は、その残虐性だけではなく、史実と伝説の間に存在する曖昧な境界線にある。後の世に広く知られる「若さを保つ為に処女の血を浴びた」という伝説は、当時の裁判記録や同時代の資料には存在しない。
この「血の風呂」のモチーフが初めて活字化されたのは、彼女の死から1世紀以上後の1729年、イエズス会士ラースロー・トゥーロツィの『悲劇の物語』においてであった。この物語の付加は、彼女の残虐行為が、時代を経るにつれて、より猟奇的で超自然的な「吸血鬼」の伝説へと変容していった過程を明確に示している。この変化は、単なる歴史的事実を、より劇的で魅力的な物語へと昇華させる効果を生んだ。彼女の行為の動機が、複雑な心理的要因から、単なる「美への執着」という、より単純で理解しやすい、そして家父長制的な価値観に沿ったものへと置き換えられたのである。こうした物語の再構築は、単なる娯楽的な再解釈に留まらず、歴史上の複雑な人物像を、社会的な規範や偏見に合致する「典型的な女性の悪」として単純化する役割も果たした。
若さと美貌を保つ為に「処女の生き血を浴びたり飲んだりしていた」という伝説は、彼女を吸血鬼のイメージと結びつけ、吸血鬼ドラキュラや女吸血鬼カーミラのモデルになったと広く伝えられている。
しかし、1983年の学術的な分析により、この「血の入浴」伝説は1729年に発見された裁判記録には一切記載がないことが証明された。これは、後世の創作やゴシック小説家による誇張が、彼女の物語の核心として定着したことを示している。
この伝説の起源として、拷問によって血まみれになった彼女の姿が、あたかも血を浴びたかのように見えたという説が提示されている。この考察は、単なる残虐行為の事実が、どのようにして人々の想像力を掻き立てる強烈なメタファーへと変換されていったかを示唆している。彼女の物語は、約100年間にわたり公的な記録から忘れ去られ、その空白を口承や創作が埋めていった結果、真実がより誇張された形で拡散するという、歴史の逆説的なプロセスを物語っている。
エリザベート・バートリが若い女性の血を浴びて若さを保とうとしたという話は、歴史的事実としての信憑性は非常に低いです。この話は、後の時代に形成された伝説やフィクションが大きく影響しています。
政治的陰謀説
彼女の逮捕と裁判には、政治的な意図があったという説も存在します。
彼女の一族は当時のハンガリーで絶大な権力を持っており、ハプスブルク家と対立していました。彼女の逮捕は、その財産を没収し、一族の勢力を削ぐ為の政治的陰謀だったのではないか、という見方です。
この説が正しいかについては歴史家の間でも意見が分かれていますが、彼女の物語が単なる殺人事件ではなく、複雑な政治的背景を持つ可能性があることを示唆しています。
第3章:精神の闇と無垢な少女:バートリの心理分析
3.1. 伝承と大衆文化が描く人物像
YouTubeで公開されているエリザベートを物語にしたとある歌詞では「精神年齢は無垢で知らない少女のようだった」という印象は、現代のフィクションや書籍が描く人物像と深く共鳴している。多くの作品では、彼女の少女時代が「美しさと清らかさを併せ持つ美少女」として描かれ、その後の転落との劇的な対比が物語の中心となっている。
こうした描写は、エリザベートを単なる「悪女」ではなく、呪われた宿命や虚無的な結婚生活によって精神が荒廃し、内なる悪魔を目覚めさせてしまった「悲劇のヒロイン」として再定義している。これらを抱いた感情は、このように現代の文化が提供する人物像と深く共鳴するものであり、その背後には、悪行にも人間的な動機や弱さを探り出そうとする現代の物語の潮流があると考えられる。
3.2. 現代心理学から見る心の荒廃
歴史上の人物に安易な診断を下すことは危険であるが、彼女の行動パターンを現代の精神医学的知見から考察することは可能である。若さと美貌への強迫的な執着や、虚しい結婚生活、夫の死といった背景は、心の荒廃を招く大きな要因となり得る。
彼女の残虐行為や不安定な人間関係、満たされない虚無感といった要素は、「境界性パーソナリティ障害(BPD)」や「自己愛性パーソナリティ障害(NPD)」の診断基準の一部と示唆的に一致する可能性がある。例えば、BPDは対人関係や自己像の不安定性、極度の気分変動、そして衝動性を特徴とする。また、NPDは誇大な自己像と共感性の欠如を特徴とする。彼女の行為は、これらの障害の側面を反映していると解釈することも出来る。
この種の心理的考察は、彼女の行為を単なる悪として片付けるのではなく、人間の内面に潜む病理や苦悩の結果として理解しようとする試みである。これにより、彼女の物語は、単なる猟奇的な記録を超え、より深く、普遍的な人間の心の闇を探るテーマへと昇華されるのである。
第4章:魂の行方:成仏と輪廻転生の探求
4.1. バートリの死とチェイテ城の幽霊伝説
エリザベートは、窓も扉も塗り塞がれたチェイテ城の部屋に約3年半幽閉された後、1614年に孤独な死を迎えた。
彼女の居城であったチェイテ城には、数多くの幽霊伝説が語り継がれている。しかし、その多くは彼女自身の幽霊ではなく、彼女に拷問され殺害された650人以上の犠牲者の幽霊、あるいはその他の城にまつわる幽霊伝説であるとされている。これは、民間伝承が彼女を「救われざる悪」として固定し、その魂が安らぎを得ることを許さなかった可能性を示唆している。
4.2. 「成仏」と「輪廻転生」という概念の解説
「成仏」や「輪廻転生」という問いは、仏教やヒンドゥー教といった東洋思想に由来する概念であり、西洋の歴史的人物に直接適用されるものではない。これらの思想では、「カルマ(業)」によって行為の結果が次の生に影響し、苦痛に満ちた輪廻から解放されること(解脱)が究極の目的とされている。
4.3. 魂は安らぎを得たのか?:歴史的・文化的考察
歴史が彼女を幽閉し、死後100年以上にわたり記録を封印した(歴史的な「成仏し得ない状態」)一方で、彼女の物語はゴシック小説によって「吸血鬼」として再誕した。これは、安らぎを得るどころか、人々の記憶の中でより恐ろしく不滅な存在として「再生」されたと比喩的に解釈出来る。伝説は彼女を罪に縛り付けたまま、永遠に語り継がれる運命を与えたのである。
4.4. フィクションにおける「魂」の転生
現代のフィクションは、この「成仏し得ない魂」というテーマを大胆に再解釈している。ゲーム『Fate』シリーズに登場するエリザベート・バートリは、歴史的な「血の伯爵夫人」のイメージとはかけ離れた、アイドルを目指す「無垢な少女」として描かれている。

これは、単なるキャラクター化を超えた文化的現象である。彼女の残虐な逸話は「無辜の怪物」というスキルとして具現化され、人々のイメージが彼女の存在を歪めたという設定になっている。これにより、彼女の罪は、ある種の悲劇的な運命として捉え直される。この現代的な「転生」は、これは実際彼女に関与した意見であった「無垢な少女」というイメージに直接応えるものであり、極悪非道の人物にも、その背後に隠された「人間性」や「無垢な願い」を探り、第二の機会を与えるという、現代社会の物語欲求を反映している。伝説が彼女を罪に縛り付けたのに対し、フィクションは彼女を罪から解放し、新たな魂を与えたのである。
第5章:現代に生きるエリザベート:フィクションとキャラクターとしての影響
5.1. 文学・映画・音楽における多様な描かれ方
エリザベートの物語は、小説、映画、漫画等、様々なメディアで独自の解釈が加えられている。ジュリー・デルピーが監督・主演を務めた映画『血の伯爵夫人』は、彼女の恋愛と狂気の狭間にある人間的な心情を描き出し、猟奇的なホラーというよりも、心理的な悲劇として捉え直している。一方、『アイアン・メイデン 血の伯爵夫人バートリ』のような作品は、吸血鬼伝説のモデルとしての彼女を歴史スペクタクルとして描いている。これらの作品は、彼女の物語を単なるグロテスクな事件としてではなく、心理的なドラマや歴史的な悲劇として再構成し、観客に新たな視点を提供している。
日本の漫画においても、この傾向は見られる。『まんがグリム童話』等の作品は、歴史的資料と想像力を巧みに組み合わせ、「呪われた血脈」や「愛欲と血に飢えた女」といったより幻想的な要素を加えて、物語を再構築している。これらの多様な表現は、エリザベートの物語が、単なる歴史の再現ではなく、時代を超えた普遍的なテーマを語る為のキャンバスとして機能していることを示している。
5.2. ゲーム・アニメにおけるキャラクター化の意義
現代のフィクション、特に日本のゲームやアニメの世界では、エリザベート・バートリは更に大胆な再解釈が施されている。ゲーム『Fate/EXTELLA LINK』や『Fate/Grand Order』における彼女は、「美しくある事」を基本骨子とするアイドルであり、その精神年齢は無垢な少女のようである。
最も顕著な例は、『Fate/Grand Order』シリーズに登場するエリザベート・バートリである。この作品において、彼女は罪を犯す前の14歳の姿で召喚され、自らを「アイドル」と称するキャラクターとして描かれている。彼女の能力は、「無辜の怪物」というスキルによって、バートリ家の家紋(ドラゴンの歯)に由来するドラゴンの角や尾を備えている。また、伝説通りの「嗜虐のカリスマ」を持つ一方で、彼女は根は小心者であり、仲間を助けるといった「反英霊」らしからぬ行動も取る。更に、成人後の彼女が「カーミラ」として別のサーヴァントとして登場し、若い彼女がその未来の自分を嫌悪するという設定は、彼女の伝説を解体し、善悪の二元論を超えた複雑な自己像を提示している。
この再解釈は、現代のメディアにおけるメタ物語的な傾向を反映している。歴史的な怪物を無邪気でドラゴンの角を持つアイドルとして描き出すことで、シリーズは「英雄」「悪女」「伝説」という概念そのものを解体する。このアプローチは、彼女の物語を静的な悪女の物語から、伝説という呪縛からの解放を求める動的で喜劇的なキャラクターへと変容させている。彼女の肖像は、吸血鬼、魔女、そして悲劇の悪女といった複数のゴシック的なアーキタイプを融合させたものであり、その物語の力は、歴史的な正確さではなく、その驚くべき再創造性にこそあると言える。
以下の表は、主要なフィクション作品におけるエリザベート・バートリの人物像を比較したものである。
| 作品 | 媒体 | 人物像の焦点 | 特記事項 |
| Carmilla | 文学 | 女吸血鬼としての原型 | 吸血鬼伝説のモデルとして描かれる |
| 『アイアン・メイデン 血の伯爵夫人バートリ』 | 映画 | 歴史スペクタクル | 精神が不安定になり残虐性を現す歴史劇 |
| 『血の伯爵夫人』 | 映画 | 心理劇 | 若い恋人との悲恋が狂気の原因と描かれる |
| 『まんがグリム童話』 | 漫画 | 呪われた家系 | 呪われた血筋が狂気の原因と描かれる |
| 『Fate』シリーズ | ゲーム | 転生したアイドル | 「無辜の怪物」として無垢な少女の側面が強調される |
この表は、彼女の物語が時代やジャンルに応じて、いかに柔軟に再解釈されてきたかを視覚的に示している。彼女は、単なる歴史的殺人鬼ではなく、創作によってその存在意義を変化させ続けている文化的シンボルなのである。
現代のエンターテイメントは、エリザベートの歴史と伝説を組み合わせ、更に新たな物語的要素を加えて、彼女の肖像を再創造している。映画、漫画、そしてビデオゲームといったジャンルを超えたこの再解釈は、彼女が単なる歴史的人物ではなく、文化的アイコンへと昇華したことを示している。
『Fate/Grand Order』におけるエリザベートの変容
| 史実・伝説の要素 | ゲーム内での再解釈 |
| 残虐行為、拷問 | スキル「嗜虐のカリスマA」、特攻ダメージ |
| 呪われた血脈、吸血鬼伝説 | スキル「無辜の怪物」、竜の角・尾を持つデミドラゴン化 |
| 「血の伯爵夫人」の異名 | 自称「アイドル」、ライブステージを宝具とする |
| 美への執着、不老不死の探求 | 若い姿で召喚、未来の自分(カーミラ)を嫌悪 |
5.3. 何故「血の伯爵夫人」は現代でも人々の心を捉えるのか
エリザベート・バートリの物語が現代に至るまで人々の心を捉えて離さない理由は、単なる歴史的事実の恐ろしさにあるのではない。それは、事実と虚構が織りなす複雑な層に、普遍的なテーマが深く刻まれているからである。
若さと美への強迫観念、権力と狂気、悲劇のヒロインへの共感、そして人間の内なる闇への探求。彼女の物語は、これらの問いを投げかけ、読者や観客に自身の内面を見つめる機会を与えている。
結論:伝説と真実の境界線
エリザベート・バートリの物語は、歴史的記録、風聞、そして創作が複雑に絡み合い、時代ごとにその姿を変容させてきた。
最も広く知られる「600人」という被害者数や「血の入浴」といったセンセーショナルな伝説は、歴史的記録には存在せず、後世の想像力が生み出したものであった。これは、公的な記録が封印された空白の期間に、真実が口承やゴシック小説によって誇張され、やがて定着していった過程を物語っている。
エリザベート・バートリは、歴史の暗闇に埋もれた単なる残虐な貴族であったが、時代を超えて様々な物語の中で再創造され、現代の文化的アイコンへと変貌を遂げた。彼女の物語は、歴史的真実、貴族の特権、政治的陰謀、そして家父長制的な偏見が複雑に絡み合ったものである。
「血の風呂」の伝説が、史実の残虐なサディズムに後から付け加えられたことは、物語がより魅力的で分かりやすいものへと変容していく過程を示している。この伝説は、単なる事象を、美への執着という普遍的で、家父長制的な価値観に沿った動機に帰着させることで、彼女の悪を解釈可能なものへと作り変えた。現代のメディアは、この伝説を単に繰り返すだけでなく、彼女の物語を解体し、吸血鬼や悲劇のヒロイン、そして無邪気なアイドルといった多様なアーキタイプと融合させることで、新たな物語を創造している。エリザベート・バートリの肖像は、単一の静的な像ではなく、人類が恐怖、欲望、そして歴史をどのように再解釈してきたかを示す、絶えず変化するキャンバスなのである。
歴史は彼女を「悪女」として幽閉し、伝説は彼女を「吸血鬼」として不滅の存在にした。そして、現代の文化は、彼女の魂を罪から解放し、「アイドル」として新たな人生を与えた。エリザベート・バートリの物語は、人間の想像力がいかに歴史を再構築し、普遍的な問いを探求してきたかを雄弁に物語る、生きた文化的ドキュメントなのである。
「血の伯爵夫人」伝説の真相
- 貴族の価値観:
当時の貴族は、領民に対する残虐行為が悪趣味程度にしか考えられていませんでした。彼女が裁かれたのは、貴族の娘にまで被害が及んだから、というのが有力な見方です。 - 「血の風呂」の逸話:
若さを保つ為に血を浴びたという話は、科学的根拠がなく、後の創作物によって広まったと考えられています。輸血や飲血の概念は当時の彼女の時代には一般的ではありませんでした。 - 政治的陰謀説:
彼女の逮捕は、ハプスブルク家による政治的陰謀だったという説が有力です。彼女の莫大な財産や、ハンガリー独立運動での影響力を恐れたハプスブルク家が、拷問によって使用人から虚偽の証言を引き出し、彼女を陥れたと考えられています。
拷問器具「鉄の処女」について

「鉄の処女(アイアン・メイデン)」は、エリザベート・バートリが使用したとされる有名な拷問器具ですが、これはフィクションの創作物であり、彼女が使ったという事実は確認されていません。
- 存在の有無:
現在世界各国に展示されている「鉄の処女」は、当時使われていたものではなく、後の時代に作られた再現品です。 - 拷問の目的:
いただいた情報にあるように、この器具は殺傷能力が低く、拷問器具としての実用性も疑問視されています。
政治的陰謀説の要点
- 権力闘争:
バートリ家は当時、ハンガリーで絶大な権力と財力を誇っていました。彼らはカトリックのハプスブルク家とは異なるプロテスタントに属しており、ハプスブルク家支配からのハンガリー独立運動に強い影響力を持っていました。その為、ハプスブルク家はバートリ家を危険視し、エリザベートの逮捕をきっかけに一族の勢力を削ごうと画策したとされています。 - 裁判の不公正さ:
エリザベートの裁判は、公正なものではありませんでした。- 証言の信憑性:
使用人たちの証言は、拷問によって引き出されたものであり、信憑性が低いと考えられています。 - 証拠の欠如:
多くの殺人があったとされるにも関わらず、具体的な証拠は不十分でした。一方で、彼女の領地であったチェイテ城が、病人や負傷者の為の診療所としても機能していたという事実は、死体が多数あったという証言が誇張であった可能性を示唆しています。
- 証言の信憑性:
- 目的と結末:
当初は彼女を修道院送りにする計画があったものの、情報が漏れることを恐れ、最終的には自宅(チェイテ城の塔)に軟禁されました。彼女の裁判は秘密裏に行われ、彼女自身が尋問されることもありませんでした。これは、彼女を犯罪者として断罪し、その罪を盾に財産を没収するというハプスブルク家の目的を物語っています。
これらのことから、エリザベート・バートリは「血の伯爵夫人」という残虐な殺人鬼であると同時に、当時の政治的対立の犠牲者でもあった、という側面が見えてきます。
エリザベート・バートリが「血を浴びて若返った」という伝説には科学的根拠がなければ彼女が輸血を行ったという説もありません。輸血という概念が確立されるのは彼女の死後のことでした。
しかし、以下の二つの観点から、この伝説の背景にある人々の考えを読み解くことが出来ます。
- 同物同治(Sympathetic Magic)の思想:
- これは「体の悪い部分を治すには、同じ部分を食すと良い」という古代から続く思想です。
- 健康な若い女性の血液を摂取すれば、その若さや生命力を自分に取り込めると考えるのは、この思想からすると不自然ではありません。
- 実際に、ヨーロッパには血液を食べる食文化(例:ブーダン)が存在することも、この思想が文化的に根付いていた傍証と言えます。血液は鉄分を豊富に含み、栄養学的な効果も否定出来ません。
- 現代科学における血液研究:
- 「若い血液が若返りに効果がある」という言説は、SFのような話に聞こえますが、ご提示いただいたように、実際にスタンフォード大学やハーバード大学の研究者が実験している「真面目な学説」です。
- 若いマウスと老いたマウスの血管系を繋いで血液を共有させる実験(パラバイオシス)では、老いたマウスの老化が抑制されるという結果が出ています。
- この研究は、老化の原因となるタンパク質や因子が血液中に存在し、それを調整することで老化をコントロールできる可能性を示唆しています。
歴史の裏付けと注意点
勿論この現代の研究成果がエリザベートの伝説を裏付けるものではありません。彼女の行動は、科学的な知識に基づいたものではなく、当時の民間信仰や思想に由来するものだったと考えられます。
また、飲血を含む食人行為は、プリオン病等の非常に危険な感染症を引き起こす可能性があり、決して安易に試すべき健康法ではありません。
エリザベート・バートリの物語は、単なる残虐行為の記録ではなく、人々の若さや不死への願望、そしてそれにまつわる民間信仰や科学的な探求心が時代を超えて交錯する、非常に興味深い事例と言えます。