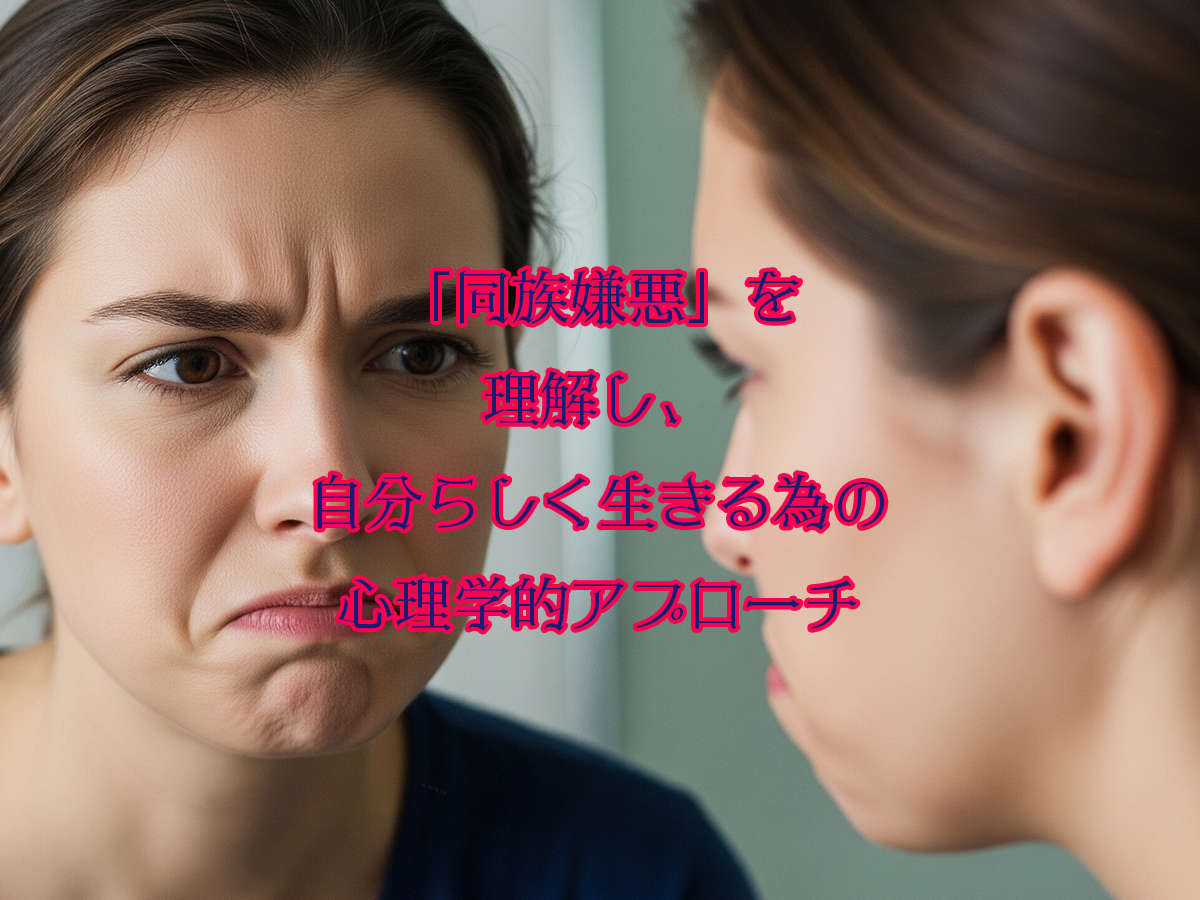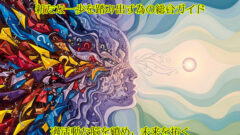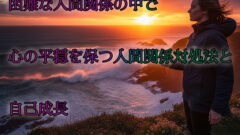はじめに:あなたの感じている「同族嫌悪」とは
「こういうタイプほど、同じようなタイプと友達になれないことが多い」という印象は、まさに「同族嫌悪」と呼ばれる心理現象と深く関連しています。この報告書では、その現象の深層にある心理メカニズムを解き明かし、個人が自分らしく、より豊かな人間関係を築く為の具体的なアプローチを提案します。
「同族嫌悪(どうぞくけんお)」とは、自分と似た性質や境遇を持つ人に対して、かえって嫌悪感を抱いてしまう心理現象を指す言葉です。これは、いわば「自分自身の弱点や苦手な要素を相手に見出し、その部分に強く反応してしまう」状態であると説明されています。類義語には「近親憎悪」があり、これは親族や同僚・友人等、近い関係の人を憎むことを指しますが、「同族嫌悪」はより広範な「似た者同士」への嫌悪を含みます。
通常、人間は自分と似た特徴や要素を持つ人に対して好意を抱く「類似性バイアス」という心理が働くことが知られています。しかし、同族嫌悪の場合はその逆で、似ているが故に嫌悪が生じるという矛盾を抱えています。この現象は、単なる類似性ではなく、その類似性の中に「何」が認識されているのかが重要であることを示唆しています。嫌悪感は無作為に生じるものではなく、深く個人的な内面の葛藤に根ざしていると考えられます。このことから、同族嫌悪の人が言及する「このタイプ」が単なる一般的な性格タイプではなく、自身が内面に抱える、あるいは認識しているものの、受け入れたくない特定の特性や弱点を含んでいる可能性が高いことが示唆されます。
したがって、経験されているのは、まさに「同族嫌悪」という心理現象です。これは多くの人が経験しうる複雑な感情であり、そのメカニズムを理解することが、対処への第一歩となります。
「同族嫌悪」の深層心理:何故似た者同士は反発し合うのか
同族嫌悪は、単なる好き嫌いといった表面的な感情に留まらず、私たちの深層心理に根ざした複雑なメカニズムによって引き起こされます。自分と似た他者に嫌悪感を抱く背景には、主に以下の心理的要因が働いています。
自己投影と自己嫌悪のメカニズム
同族嫌悪の最も重要な心理的要因の一つは、「自分の嫌な部分を相手に投影してしまう」ことです。これは「鏡嫌い」とも表現され、鏡に映る自分の姿(特に嫌な部分)を他人を通して見てしまう心理現象です。例えば、仕事でミスをしがちな自分を認めたくない人が、同じようにミスをする仲間を見ると、「自分と同じ失敗をしている、恥ずかしい」と感じ、過剰に相手を責めたり距離を置いたりすることがあります。
興味深いことに、嫌悪感を抱いている本人は、自分自身も同じようなことをしていることに気付かないまま、相手を嫌っていることが多いと指摘されています。これは、自分の嫌いな部分や弱点を相手に投影することで、無意識のうちに嫌悪感を増幅させてしまう現象です。
このメカニズムは、心が自己を守る為の「防衛」として機能することがあります。つまり、「自分で自分を嫌う」状態になるよりも、「自分が相手を嫌う」状態の方が、一時的に心が安定し、楽に感じられることがあるのです。
「自分で自分を嫌うよりも他人を嫌う方が楽」という考え方は、同族嫌悪の根底にある重要な自己防衛メカニズムを浮き彫りにします。もし個人が強い同族嫌悪を経験しているなら、それは彼ら自身の内面に深く根ざした葛藤や自己批判が、外部に投影されている可能性が高いことを示唆します。この嫌悪は単に特定の特性が嫌いなのではなく、その特性が「自分自身の一部」であることへの嫌悪感である可能性があります。同族嫌悪の強さは、個人の自己嫌悪や未承認の欠点に対する内面の抵抗の強さを直接的に反映している可能性があります。外部への嫌悪感に対処する為には、まず内面の自己拒絶と向き合うことが不可欠である、というより深い意味合いがここには含まれています。
競争心と嫉妬の心理
似た者同士は、自然と比較対象になりやすい傾向があります。その中で、自分が劣っている部分に目が向いたり、相手が自分より上手くやっているように見えたりすると、「嫌だ」という感情や腹立たしさを持ちやすくなります。特に、同じ環境にいるからこそ「自分はもっと認められるはずなのに、相手の方が上司に評価されている」といった不満が募ると、いわゆる「嫉妬」が同族嫌悪へと発展するリスクがあります。ビジネスシーンでは、同じ部署や入社時期が近い社員間で競争が激化し、お互いに苦手意識を持ち合う現象は珍しくありません。自己の価値を相対的に引き上げようとする心理も、同族嫌悪を引き起こす理由の一つです。
幼少期の経験と自己肯定感の影響
同族嫌悪の背景には、自己への自信のなさ、コンプレックス、そして「完璧主義/理想主義」といった心理が潜んでいるケースが多いとされています。自己肯定感が低いと、自分の短所やコンプレックスと重なる部分を他者に見出した際に、無意識のうちに嫌悪感を増幅させてしまうことがあります。自己肯定感の低さには、幼少期の親子関係(過保護、過干渉、放任、兄弟姉妹との過度な比較)が大きく影響することが分かっています。自分に自信がない人は、周囲の評価や常識、世間体に左右されやすく、これが同族嫌悪の一因となる可能性もあります。また、「自分は生きていていい」という感覚が希薄だと、自己犠牲的になり、自分より他人を優先しがちで、これが対人関係のムラに繋がることもあります。
これらの情報を統合すると、明確な因果関係の連鎖が見えてきます。高い理想や完璧主義は、現実とのギャップから自己肯定感の低下や自己嫌悪を引き起こしやすくなります。この自己嫌悪が強いと、他人の中に自分を嫌うべき部分を見出し、結果として同族嫌悪が強化されるというサイクルが生まれます。このサイクルを認識することは非常に重要です。同族嫌悪を克服する道は、単に外部の人間関係を管理するだけでなく、根本的に内面の基準を見直し、自己への慈悲を育むことにあるという、より深い意味合いが読み取れます。
Table 1: 「同族嫌悪」の心理メカニズムと要因
| メカニズム/要因 | 説明 | 具体例 | 関連する感情 |
| 自己投影 | 自分の嫌な部分や未熟な側面を相手に見出し、それを相手の欠点として認識する心理現象。無意識の自己防衛。 | 仕事でミスをしがちな自分を認めない人が、同じようにミスをする同僚を過剰に責める。 | 自己嫌悪、恥、不快感 |
| 競争心と嫉妬 | 似た者同士が比較対象となりやすく、相手が自分より優れていると感じたり、認められていると感じたりすることへの不満や妬み。 | 同じ部署の同期が自分より評価されていると感じ、苦手意識を持つ。 | 嫉妬、不満、劣等感 |
| 自己肯定感の低さ | 自分に自信がなく、自身の短所やコンプレックスを受け入れられない状態。他者の中にそれらを見つけると嫌悪感が増幅する。 | 幼少期の親子関係や比較経験が自己肯定感を低下させ、他者への嫌悪に繋がる。 | 不安、自信のなさ、自己嫌悪 |
| 完璧主義/理想主義 | 高すぎる理想や完璧を求める傾向。自分自身の不完全さを受け入れられず、他者の不完全さにも冷酷になる。 | 常に100点を求める完璧主義者が、失敗した自分や不完全な他人を嫌悪の対象とする。 | ストレス、自己批判、不寛容 |
| 共感の過剰 | 共通点が多い相手に対して共感しすぎるあまり、自身の乗り越えたい過去や隠したい恥ずかしい一面が投影され、辛くなる。 | 過去の苦労を知る同郷の友人と会うのが辛くなる。 | 疲弊、不快感、過去の傷 |
「同族嫌悪」が人間関係に与える影響
同族嫌悪は、個人が抱える内面的な感情に留まらず、友人、家族、職場等、あらゆる人間関係に具体的な悪影響を及ぼす可能性があります。これは、本来であれば繋がりを深めるはずの「類似性」が、かえって分断を生み出すという皮肉な結果をもたらす為です。
友人関係・職場関係における具体例
仕事のスタイルや価値観、出身地、経歴が似ているのに、些細な違いで相手を毛嫌いしてしまうケースが頻繁に起こります。これは、自分の短所やコンプレックスと重なる部分を他者に見出すと、無意識のうちに嫌悪感を増幅させてしまう現象です。特に職場では、同じ部署で入社時期が近い社員同士で競争が激化し、何故かお互いに苦手意識を持ち合ってしまう現象は珍しくありません。企業としては、こうした関係性が生産性を下げないよう、リーダーや上司が適切に介入しサポートする必要があります。友人関係においても、以前はとても楽しく付き合っていた似たような仲間と、数年後に距離を置きたくなることがあります。
その理由の一つに、自分と似た仲間と関わり続けることで、仲間の言動から自分が隠したい恥ずかしい一面が投影され、辛くなることが挙げられます。
孤立感と孤独感の悪循環
同族嫌悪が強まると、似たタイプの人との関係を避けるようになり、結果的に人間関係が狭まり、孤立感や孤独感を感じやすくなります。これは「類は友を呼ぶ」とは対照的に、似ていることがネガティブな感情を引き起こす為、本来なら共感し合えるはずの相手との繋がりが断たれてしまう可能性があります。
自己嫌悪が強い場合、他人の中に自分を見出して嫌悪感を抱く為、人との関わりを避け、結果的に孤独感を深める悪循環に陥ることがあります。この連鎖は、更に自己肯定感を低下させ、同族嫌悪を強化する要因となり得ます。同族嫌悪は、自分に似た人々を避ける行動に繋がります。これは、本来であれば繋がりを築けるはずの相手(類似性バイアス )を遠ざけることになり、結果的に社会的ネットワークを狭めます。この自己選択的な孤立は、孤独感を増幅させ、更に自己肯定感を低下させ、同族嫌悪の根底にある自己嫌悪を強化する悪循環を生み出す可能性があります。
この悪循環を断ち切る為には、単に嫌悪感を管理するだけでなく、例え最初は不快であっても、積極的に人との繋がりを求め、維持することが必要です。
そして、同族嫌悪の根源にある自己嫌悪に根本的に対処することが、孤立を防ぐ鍵となります。
「同族嫌悪」を乗り越え、自分らしく生きる為の実践的アプローチ
同族嫌悪は不快な感情であり、人間関係に困難をもたらしますが、それを乗り越えることは自己理解を深め、自分を大きく成長させる貴重な機会となります。相手を否定して関係を断つのではなく、その感情が自分に何を気付かせてくれるのかを洞察し、自分の成長に繋げていくことが重要です。
自己受容を深める:マインドフルネスとセルフ・コンパッション
自分自身の負の側面も含めて「あるがまま」に受け入れる心のありようを育むことが「セルフ・コンパッション」です。セルフ・コンパッションは、マインドフルネスによって困難な体験(ネガティブな思考や感情、身体感覚)に暖かな気付きを向け、苦しみの中にある自分自身に愛情のこもった気付きを向けることから始まります。
具体的な実践方法として「慈悲の瞑想」があります。これは「私が幸せでありますように」「私の悩み苦しみがなくなりますように」といったフレーズを、まず自分自身に向けて繰り返すことから始め、慣れてきたら恩人、親しい人、中性の人、そして「嫌いな人」へと対象を拡張していきます。深い悲しみや怒りを感じる場合にも、その感情を「あるがまま」に受け入れ、慈しみのフレーズを用いることで、自己批判を手放し、心の平穏を育むことが出来ます。
同族嫌悪は、自分の嫌いな部分を他者に投影することから生じます。セルフ・コンパッションは、自分の「あるがまま」の姿を受け入れることを目指します。慈悲の瞑想は、この自己受容を深める実践であり、特に「嫌いな人」に慈悲を向けるステップが含まれています。これは、同族嫌悪の根源である投影を直接的に打ち破る行為です。
もし個人が、自分自身の嫌いな特性を映し出す相手に対して意図的に良い願いを向けることが出来れば、それは相手だけでなく、自分自身に対する評価も再構築することに繋がります。この実践は、嫌悪感を抱く対象への見方を変えるだけでなく、自己批判的な内面を和らげる効果があります。それは、単に相手を好きになることを強制するのではなく、自己判断の厳しさを和らげ、結果として同族嫌悪を緩和する道となるでしょう。
自己肯定感を高める具体的な習慣
自己肯定感を高めることは、同族嫌悪の根底にある自己嫌悪や自信のなさを和らげる上で非常に重要です。
- 小さな成功体験を積み重ねる:
達成出来そうな小さな目標を設定し、それをクリアする経験を積むことで、着実に自信を育むことが出来ます。例えば、「今日は食器を洗う」「寝る前に5分だけ部屋を片付ける」といった、普段当たり前に行っている行動も意識的に評価し、自分を褒めることが大切です。 - ポジティブな言葉の「クセ」に変える:
心理学では、言葉のクセが思考のクセを変えると言われています。「~しなくちゃいけない」といった義務的な言葉を、「~したい」「~したほうがいい」といった能動的で前向きな言葉に置き換えることで、自己へのプレッシャーを減らし、思考パターンをより肯定的なものに変えていくことが出来ます。 - ポジティブな日記をつける:
1日の終わりに、自分の頑張りや感謝出来ることを手書きで記録する「褒め日記」は、自己肯定感を高める非常に効果的な方法です。手書きは脳の複数の部位を刺激し、重要な情報として認識させる為、自己認識を促し、モチベーションを高めます。 - 運動する:
心理学者の内藤誼人氏も推奨するように、筋トレやウォーキング等の運動は、体力や筋力と自己肯定感が密接に関係しており、自信を高める効果があります。体を動かすことは気分転換になり、ストレス解消にも繋がります。 - 自分と他者を比較しない:
SNS等で他者の「キラキラした部分」だけを見て自分と比較し、劣等感を感じて落ち込むことを止めることが重要です。「人は人、自分は自分」と割り切り、自分のペースと価値観を大切にすることで、自己嫌悪の感情を軽減出来ます。
完璧主義は、高い基準を満たせない時に自己批判に繋がります。同族嫌悪は、これらの自己嫌悪する特性が他者に見られるときに発生します。「小さな成功体験」を積み重ね、「ポジティブなセルフトーク」を実践することは、意図的に自己肯定の機会を作り出し、完璧主義による内面のプレッシャーを軽減します。これにより、内面の物語が「自分は不十分だ」から「自分は進歩している」へと変化し、自己嫌悪の基盤、ひいては他者への投影を直接的に弱体化させます。
これらの些細に見える変化は、同族嫌悪を維持する中核的な認知行動パターンをターゲットにする為、非常に強力です。自己受容への段階的で持続可能な道を提供します。
認知の歪みを修正する:認知行動療法の視点
認知行動療法(CBT)は、自動的に浮かぶネガティブな思考(自動思考)の歪みを認識し、より現実的で柔軟な思考にバランスを整えることで、心の苦痛を和らげる心理療法です。同族嫌悪を感じる際の思考パターンを分析し、「何故その人に嫌悪感を抱くのか」を深掘りすることで、自分の嫌な部分やコンプレックスが投影されていることに気付くことが出来ます。
- 自他の境界線を意識する:
他人の言動にイライラする場合、自分と相手の境界線を意識し、自分がコントロール出来る範囲と相手の自由・責任の範囲を区別することが有効です。これにより、他者の行動に過度に反応することを防ぎ、心の負担を軽減します。 - リフレーミング:
物事の捉え方を変える「リフレーミング」は、ネガティブな要素も視点を変えることでポジティブに捉え直すことを可能にし、自己批判を建設的な思考に転換するのに役立ちます。例えば、「神経質」という短所を「几帳面」「計画性がある」と言い換えることで、その特性に対する見方を変えることが出来ます。 同族嫌悪は、しばしば自分の「嫌な部分」を他者に投影することから生じます。リフレーミングは、ネガティブな特性をポジティブな視点から捉え直すことを可能にします。もし個人が、自分も持っている他者の嫌いな特性をリフレーミング出来るなら、それは同時に二つの効果をもたらします。一つは、他者に対する否定的な判断を減らすこと。もう一つは、自分自身の中にあるその特性に対する自己批判を減らすことです。これにより、リフレーミングは同族嫌悪の外部的な現れと内部的な根源の両方に対処する為の強力かつ効率的なツールとなり、対人関係の調和と自己受容の両方を促進します。 - 問題解決思考への転換:
同じことを繰り返し考えてしまう「反芻思考」に陥った場合、具体的な解決策を考える方向へ思考を切り替えることが重要です。問題を明確にし、自分がコントロール出来る部分と出来ない部分を分け、コントロール出来る部分について小さく具体的な行動ステップを立てることで、建設的な行動へと繋げられます。
多様な人間関係の構築と適度な距離感
同族嫌悪を感じる相手は、自分の「鏡」となる存在であり、自己成長の機会を与えてくれる貴重な存在です。
- 相手をよく観察し、学ぶ:
嫌悪感を感じる相手のプラス面やマイナス面を客観的に観察し、共通する嫌な部分が自分にもあると認識することで、そこから学ぶことが出来ます。相手の行動を反面教師として、自身の改善点を見つける視点を持つことが重要です。 これこそが似たタイプの人と友達になるのが難しいというものでした。これは課題ですが、利用可能な情報は、「同族嫌悪」が、嫌悪感を抱く相手を観察し、自分自身にも共通する「嫌な部分」を認識することによって、自己成長の機会となり得ることを明確に述べています。これは、同族嫌悪を引き起こすまさにその人々が、単なる障害ではなく、潜在的な「教師」になり得ることを示唆しています。似たタイプの人を単に避けるのではなく、「鏡から学ぶ」という考え方を取り入れることが出来ます。これにより、ネガティブな感情体験を建設的なものに変え、個人的な成長を促進し、更には嫌悪感から相互理解(たとえ距離があっても)の関係へと変化させる可能性を秘めています。 - 適度な距離を保つ:
相手との距離が近すぎると、常に自分の不快な面を見せられているようで辛くなる為、適度な距離を保つことが大切です。これは関係を断つことではなく、健全な境界線を設定し、互いがストレスなく付き合える関係性を模索することです。 - 異なるタイプの人との交流:
異なる文化や考え方を理解しようと努め、多様な背景を持つ人々と積極的に交流することは、視野を広げ、共感力を向上させる上で非常に有効です。これは、自分と異なる視点を受け入れ、他者への理解を深める練習にもなります。
Table 2: 「同族嫌悪」を乗り越える為の実践的アプローチ
| アプローチ | 説明 | 具体的な実践方法 | 期待される効果 | ||||
| 自己受容 | 自分の良い面も悪い面も「あるがまま」に受け入れること。 | ・マインドフルネス瞑想:呼吸に意識を集中し、思考や感情をありのままに受け止める。 | ・セルフ・コンパッション:苦しみの中にある自分自身に愛情を向ける。 | ・慈悲の瞑想:自分や嫌いな人を含む他者の幸せを願うフレーズを繰り返す。 | 自己批判の軽減、心の平穏、自己肯定感の向上 | ||
| 自己肯定感の向上 | 自分には価値があると感じ、自信を持つこと。 | ・小さな成功体験を積む:達成可能な目標を設定し、クリアする。 | ・ポジティブな言葉遣い:口癖を「~しなくちゃ」から「~したい」に変える。 | ・ポジティブ日記:自分の頑張りや感謝を記録する。 | ・運動習慣:ウォーキングなど体を動かす。 | ・他者との比較を止める。 | 自信の回復、内面的な安定、自己嫌悪の軽減 |
| 認知の歪み修正 | ネガティブな思考パターンを認識し、より現実的で柔軟なものに変える。 | ・自他の境界線を意識する:自分と相手の責任範囲を明確にする。 | ・リフレーミング:ネガティブな特性をポジティブな側面として捉え直す。 | ・問題解決思考:反芻思考を具体的な行動計画に転換する。 | 感情のコントロール、対人関係の改善、建設的思考 | ||
| 人間関係の再構築 | 健全な対人関係を築き、孤立感を解消する。 | ・嫌悪感を覚える相手から学ぶ:相手の言動を観察し、自身の成長のヒントにする。 | ・適度な距離を保つ:相手との距離が近すぎず遠すぎない関係を意識する。 | ・多様な人との交流:異なる価値観や背景を持つ人々と積極的に関わる。 | 孤立感の軽減、視野の拡大、共感力の向上 |
おわりに:あなたの「同族嫌悪」を成長の糧に
あなたが感じている「同族嫌悪」は、一見するとネガティブで避けたい感情かもしれません。しかし、心理学的な視点から見れば、それはあなた自身をより深く理解し、自己成長を促す為の貴重な「鏡」となり得ます。この感情は、あなたがまだ受け入れられていない、あるいは向き合えていない自分自身の側面を教えてくれるサインなのです。
同族嫌悪が自己投影、自己嫌悪、自己肯定感の低さ、完璧主義と一貫して関連していることを考慮すると 、同族嫌悪の存在と強さは、個人の内面の心理的状態を診断する為の貴重な指標となり得ます。これは単なる人間関係の問題ではなく、より深い内面の葛藤の症状であると言えます。したがって、個人にとって、これは似たタイプの人々との相互作用を変えることだけに焦点を当てるのではなく、同族嫌悪を、重要な自己反省と自己改善の作業に取り組むべき信号として捉えるべきであることを意味します。外部の対立は、内面の対立の現れなのです。
同族嫌悪を乗り越える鍵は、自分の内面と向き合い、自己嫌悪の感情を自己受容へと転換していくプロセスにあります。マインドフルネスやセルフ・コンパッションの実践は、この内面の変革を支える強力なツールとなるでしょう。自分自身に優しさを向け、完璧でなくても良いと受け入れることで、他者への嫌悪感も自然と和らいでいきます。
また、同族嫌悪を引き起こす相手との「適度な距離」を保つことの重要性が強調されます。これは、孤立に繋がる回避とは異なり、自己反省の為の安全な空間を作り出すことを目的としています。もし相手が「鏡」であるならば 、鏡に近付きすぎると圧倒され、苦痛を感じる可能性があります。これは人間関係に対するニュアンスのあるアプローチを示唆しています。関係を断ち切るのではなく、内面的な作業を行いながら、相手との接触を管理することです。これにより、個人は常にトリガーされることなく感情を処理し、自己受容に取り組むことが出来、癒しのプロセスをより管理しやすく、持続可能なものにすることが出来ます。これは、恒久的な後退ではなく、戦略的な距離の取り方と言えるでしょう。
このプロセスは一朝一夕に完了するものではありません。しかし、継続的な自己観察と、今回紹介した実践的なアプローチを日々の生活に取り入れることで、個人はより健全な自己肯定感を育み、他者との関係性を改善し、最終的には自分らしい、より豊かな生き方を築くことが可能です。もし、これらのアプローチを一人で実践するのが難しいと感じたり、感情の苦痛が日常生活に大きな影響を与えている場合は、迷わず心理カウンセリングや専門家のサポートを検討してください。専門家は、個人の内面を深く探求し、個別の状況に合わせた具体的な支援を提供してくれます。
あなたが感じている「同族嫌悪」は、あなたがより深く、より豊かに生きる為の、そして自己との調和を見つける為の重要なサインです。この感情を否定するのではなく、その奥にあるメッセージに耳を傾け、それを自己成長の機会として捉えていきましょう。
【引用・参考文献】
forbesjapan.comforbesjapan.com
あなたが嫌いなタイプの人は、なぜ〇〇なのか | 井上太一/ラクに生きるための心理学
同族嫌悪について – 銀座泰明クリニック
だれかを「嫌い」を思う時、見るべき相手は自分かも?!
マインドフル・セルフ・コンパッション – Centers for Integrative Health
「同居人がいない」「資産が少ない」と孤独感が増す ? 心の孤立を防ぐには – 大和ネクスト銀行
自己嫌悪と投影は地続き – 尼崎カウンセリング研究所
あなたを苦しめる、幼少期の「13の禁止令」【書籍オンライン編集部セレクション】
周囲に気を遣いすぎてしまう…生きづらさの根本にある「幼少期の親子関係」 | PHPオンライン
【心理士監修】自己肯定感が低い人の特徴と原因、感情に振り回されないための方法を解説
同僚や後輩、上司…職場にいる「どうしても嫌いな人」への意識を変える方法
企業が取り組むべきマインドフルネス方法とは?導入のポイントや企業事例を解説 – バヅクリ
自己肯定感とは?低い人の特徴や高める方法・トレーニング例をわかりやすく解説! | comotto
自己肯定感が低い原因や特徴は?高める方法4選 – STUDY HACKER …
孤立感・孤独感を1人で抱え込まないで。 精神科オンライン診療で …
セルフ・コンパッションと「あるがまま」 – 公益社団法人 日本心理 …
認知行動療法(CBT)とは – 認知行動療法センター – 国立精神・神経 …
類は友を呼ぶと同族嫌悪|[Discerning Omega Takato Ω] – note
pex.jp「自分に似ている人」に嫌悪感を抱く「同族嫌悪」の心理とは? 心理カウンセラーに聞いてみた – PeX
同じ系統や血筋を嫌悪する「同族嫌悪」が起こる原因 – @DIME アットダイム
同族嫌悪の心理4つとは? 恋愛において同族嫌悪になってしまう事例を紹介。 | 恋学[KOIGAKU]
仕事でつかえる心理学 ~その30~ あの人なんか苦手(同族嫌悪) – Aspark Media
【ネガティブな不安感から即脱却】ポジティブシンキングとは?実践方法もご紹介
リフレーミングとは?心理学的思考がビジネスにもたらす効果と実践方法を徹底解説!
心理士監修|自己嫌悪とは?陥りやすい人の特徴や10個の克服法を紹介 – Awarefy
同族嫌悪とうまく付き合う|かぬ – note
「同族嫌悪」の意味とは?正しい使い方と類義語・言い換え表現を例文付きで徹底解説
「同族嫌悪」とは…嫌いな人と自分の共通項は?感情と上手に付き合う3ポイント – オールアバウト
異文化対応力とは?高めるために必要な要素と育成方法を解説 – alue
共感力とは|高い人の特徴や鍛えるためのトレーニング方法を解説 – Schoo
質を高める他者理解!共感する力の重要性 – microsyz
考えすぎを止めたい!反芻思考の無限ループから抜け出す方法 – オンライン心療内科『メンクリ』
習慣性自責をやめる方法|自分を許し、心を軽くする考え方 – あしたのクリニック五反田院