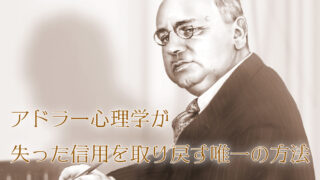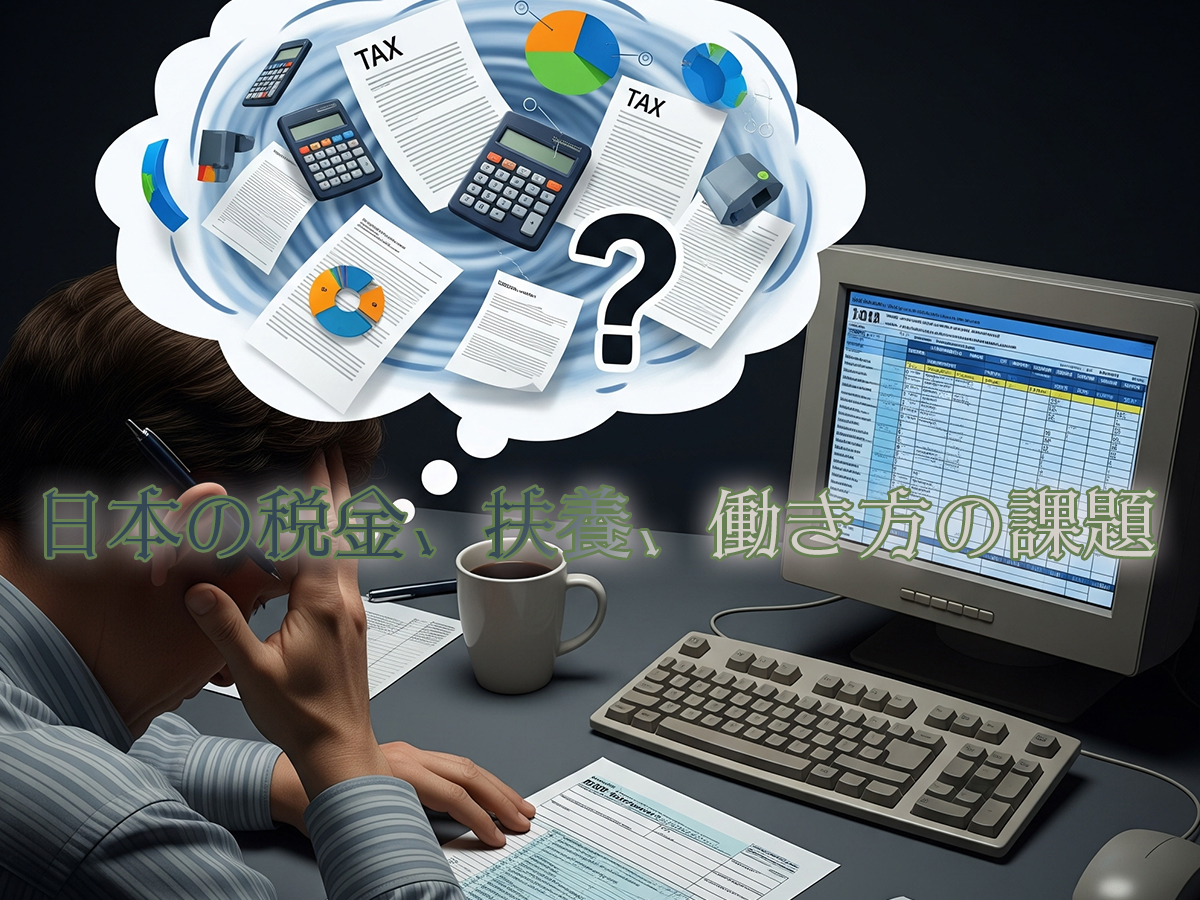オーバーシンカーとは
オーバーシンカーは、物事を過剰に考え過ぎる人を指す言葉で、「考え過ぎる人」「心配性な人」といった意味合いで使われます。英語では “overthinker” と表記されます。
「オーバーシンカー」という言葉は、特定の誰かが名付けたものではなく、英語圏で自然発生的に広まった言葉です。
元々の言葉である「overthink」(考え過ぎる)は、接頭辞の「over-」(過剰な、〜すぎる)と動詞の「think」(考える)が組み合わさって出来たもので、古くは12世紀頃には既に使われていたという記録がオックスフォード英語辞典に残っています。
その後、この「overthink」に「〜する人」を意味する接尾辞「-er」がついて、「overthinker」という言葉が生まれました。
心理学の分野では、この状態を指す専門用語として「反芻思考(rumination)」や「過剰分析(analysis paralysis)」といった言葉が使われることがありますが、「オーバーシンカー」という言葉自体は、より日常的で口語的な表現として広く使われています。
結論として、「オーバーシンカー」という言葉には特定の創始者は存在せず、英語の語彙が組み合わさって自然に形成され、一般に浸透していった言葉であると言えます。
オーバーシンカーの特徴
オーバーシンカーには、以下のような特徴が見られます。
- あらゆる可能性を考えすぎてしまう:
どんなに小さなことでも、良い面も悪い面もあらゆる可能性を掘り下げて考えます。 - 過去の失敗をいつまでも引きずる:
「あの時ああすれば良かった」と、終わったことに対して後悔の念を抱き続けます。 - 他人の評価が気になりすぎる:
「他人にどう思われているだろうか」と、必要以上に周りの目を気にして行動に影響が出ることがあります。 - 行動に移せない:
考え過ぎてしまい、結局何も行動出来なくなることがあります。 - 決断に時間がかかる:
選択肢が多すぎると、どれが良いか判断出来なくなり、決断を下すのに苦労します。
原因
考え過ぎてしまう原因は人それぞれですが、一般的には以下のようなものが挙げられます。
- 完璧主義:
失敗を恐れるあまり、完璧な結果を求めて準備に時間をかけすぎます。 - 低い自己肯定感:
自分に自信がない為、「もし失敗したら」とネガティブな想像をしやすくなります。 - トラウマや過去の経験:
過去の失敗やショックな出来事が原因で、同じことが起きないようにと過剰に考えてしまいます。
対策
オーバーシンカーであること自体が悪いわけではありませんが、考えすぎで日常生活に支障をきたす場合は、以下のような対策が有効とされています。
- 考えを書き出す:
頭の中にある考えを紙に書き出すことで、思考を整理し、客観的に見つめ直すことが出来ます。 - 時間を区切る:
「この問題について考えるのは10分だけ」のように、思考する時間を制限する練習をします。 - 瞑想やマインドフルネス:
今この瞬間に意識を集中させることで、未来や過去への思考から離れることが出来ます。 - 他者と共有する:
一人で抱え込まず、信頼出来る人に相談することで、新しい視点や解決策が見つかることがあります。
過剰な思考はストレスや不安に繋がることもありますが、慎重さや分析力といった強みにもなり得ます。大切なのは、自分の思考パターンを理解し、上手く付き合っていくことです。
オーバーシンカーが人間関係で抱えやすい悩み
1. 相手の気持ちを深読みしすぎる
相手の些細な言動や表情、声のトーンから、「もしかして怒っている?」「私のことを嫌っている?」等と、実際の意図とは違う可能性を過剰に考えてしまいます。これにより、コミュニケーションを取るのが怖くなったり、自分から距離を置いたりすることがあります。
2. 発言や行動を後悔し過ぎる
会話が終わった後、「あの時、あんなことを言わなければよかった」「変なことだと思われたかも」と、自分の発言や行動を何度も反芻して後悔します。これにより、次の会話が憂鬱になったり、自分を責めたりしてしまいます。
3. 相手に合わせ過ぎてしまう
「嫌われたくない」「波風を立てたくない」という思いが強い為、自分の意見を言えずに相手に合わせてばかりになりがちです。これにより、ストレスが溜まったり、相手と心の距離が縮まらなかったりすることがあります。
4. 孤独を感じやすい
考え過ぎてしまうことで、人間関係に疲れてしまい、積極的に人との交流を避けるようになります。その結果、「誰も自分のことを理解してくれない」と孤独を感じてしまうことがあります。
対策
人間関係の悩みを軽減するための対策としては、以下のようなことが考えられます。
- 「相手はそこまで気にしていない」と割り切る:
ほとんどの場合、他人はあなたの言動をそこまで深く考えていません。自分の中で作り上げた不安なシナリオは、現実ではないと認識する練習をしましょう。 - 完璧なコミュニケーションを求めない:
相手と完璧に分かり合うことは不可能です。多少の誤解や行き違いはあって当然だと受け入れることで、気持ちが楽になります。 - 「もし〜だったら」ではなく「今、何をすべきか」を考える:
不安な想像が頭をよぎったら、その思考を一度止めて、「今、この瞬間に出来ること」に意識を集中させましょう。 - 信頼出来る相手には自分の気持ちを話す:
考え過ぎていることを、信頼出来る友人や家族に打ち明けてみるのも一つの方法です。話すことで、客観的な視点を得られたり、気持ちが楽になったりすることがあります。
もし信頼出来る友人や家族がいない場合、一人で抱え込むのはとても辛いことです。そういった状況でも、あなたの悩みを安心して話せる場所や頼れる人は必ずいます。
専門家や公的なサポートを頼る
友人や家族がいないからといって、一人で悩みを解決しようとする必要はありません。以下のような専門家や公的な機関は、あなたの味方になってくれます。
- カウンセリング:
臨床心理士や公認心理師等の専門家は、あなたの話をじっくりと聞き、考え方の癖を客観的に整理する手助けをしてくれます。守秘義務がある為、話した内容が外部に漏れる心配はありません。 - 公的機関の相談窓口:
お住まいの地域の保健センターや、国が運営するこころの健康相談ダイヤル等、匿名で利用出来る無料の相談窓口があります。 - 産業医や産業カウンセラー:
もし会社に設置されている場合は、利用してみましょう。職場の人間関係の悩みに特化して相談出来ます。
新しいコミュニティに飛び込む
悩みを共有出来る人を見つける為に、新しいコミュニティに身を置くのも一つの方法です。
- 趣味のサークルや教室:
同じ趣味を持つ人たちと交流することで、自然と心が通じ合う仲間が見つかることがあります。 - ボランティア活動:
社会貢献を目的とした活動に参加することで、価値観の合う人たちと出会いやすくなります。
このような場所では、お互いのプライベートな部分を深く知らなくても、共通の興味を通じて穏やかな人間関係を築くことが出来ます。
大切なのは「一人ではない」と知ること
今、あなたの周りに頼れる人がいないとしても、それはあなたが一人だという証明ではありません。あなたと同じように悩みを抱え、解決策を探している人はたくさんいます。
専門家やコミュニティは、あなたが安心して自分自身と向き合い、一歩踏み出す為の大きな支えとなります。まずは一歩、小さな勇気を出して、信頼出来る人を探し始めてみましょう。
完璧な人間関係を築く必要はありません。少しずつ考え方のクセを修正していくことで、より穏やかな気持ちで人と接することが出来るようになるでしょう。
オーバーシンカーの為の、仕事での向き合い方
オーバーシンカーにとって、仕事は大きな悩みの種になりがちです。しかし、考え過ぎてしまう特性は、見方を変えれば仕事の強みにもなります。
1. 完璧主義と上手く付き合う
完璧主義は、時に仕事の質を高める原動力になりますが、過剰になると作業が停滞する原因にもなります。
- 「80点の完成度」を目指す:
まずは80点の完成度でアウトプットすることを目標にしましょう。残りの20点は、必要な場合のみ追加で改善していく、という意識を持つと、作業が進みやすくなります。 - 締切(デッドライン)を厳守する:
どんなに完璧を目指したくても、締切は絶対です。「この時間までに終わらせる」と意識することで、無駄な思考を削ぎ落とすことが出来ます。
2. 人間関係の悩みを解消する
仕事における人間関係の悩みは尽きませんが、考え方を変えることで気持ちが楽になります。
- 「職場は役割を果たす場所」と割り切る:
プライベートとは違い、職場は仕事上の役割を果たす為の場所です。無理に全員と深く仲良くなろうとせず、必要最低限のコミュニケーションを心掛けることで、余計な気疲れを減らせます。 - 報告・連絡・相談を徹底する:
「もし~だったら」と不安に思う前に、まずは上司や同僚に報告・連絡・相談をしましょう。自分の考えをオープンにすることで、相手との誤解を防ぎ、スムーズな人間関係を築けます。
3. 強みを活かす
オーバーシンカーは、「あらゆる可能性を考える力」と「慎重さ」を持っています。これらを仕事で活かすことで、大きな成果に繋がることがあります。
- リスク管理:
新規プロジェクトや企画を立てる際に、考えうるリスクを事前に洗い出すことが出来ます。 - 課題解決:
物事を多角的に捉えられる為、問題の根本原因を深く掘り下げ、的確な解決策を見つけ出すことが出来ます。 - 細部への配慮:
些細なミスや見落としを防ぎ、仕事の質を高めることが出来ます。
4. まとめ
考え過ぎは、時に自分を苦しめます。しかし、その特性を否定するのではなく、「慎重で細やかな配慮が出来る」という強みとして捉え、仕事に活かしていくことが大切です。(頭だけ過剰に動いて、メンタルもやられがちなので鬱病になりやすい)
そして、過剰な思考が始まったときは、「今、何が出来るか?」という行動に焦点を当てることで、仕事でのパフォーマンスを向上させることが出来ます。
.
.
.
みんなが通る道対策です。