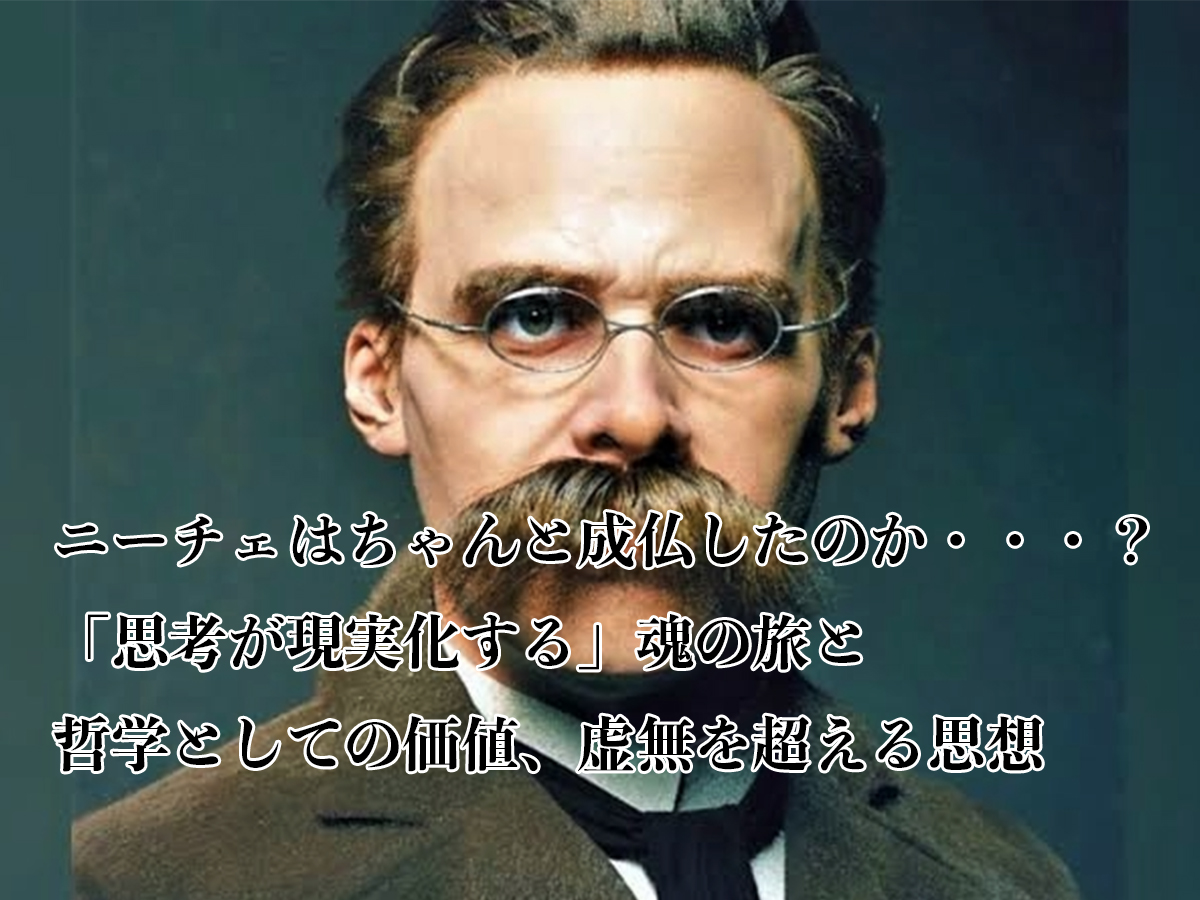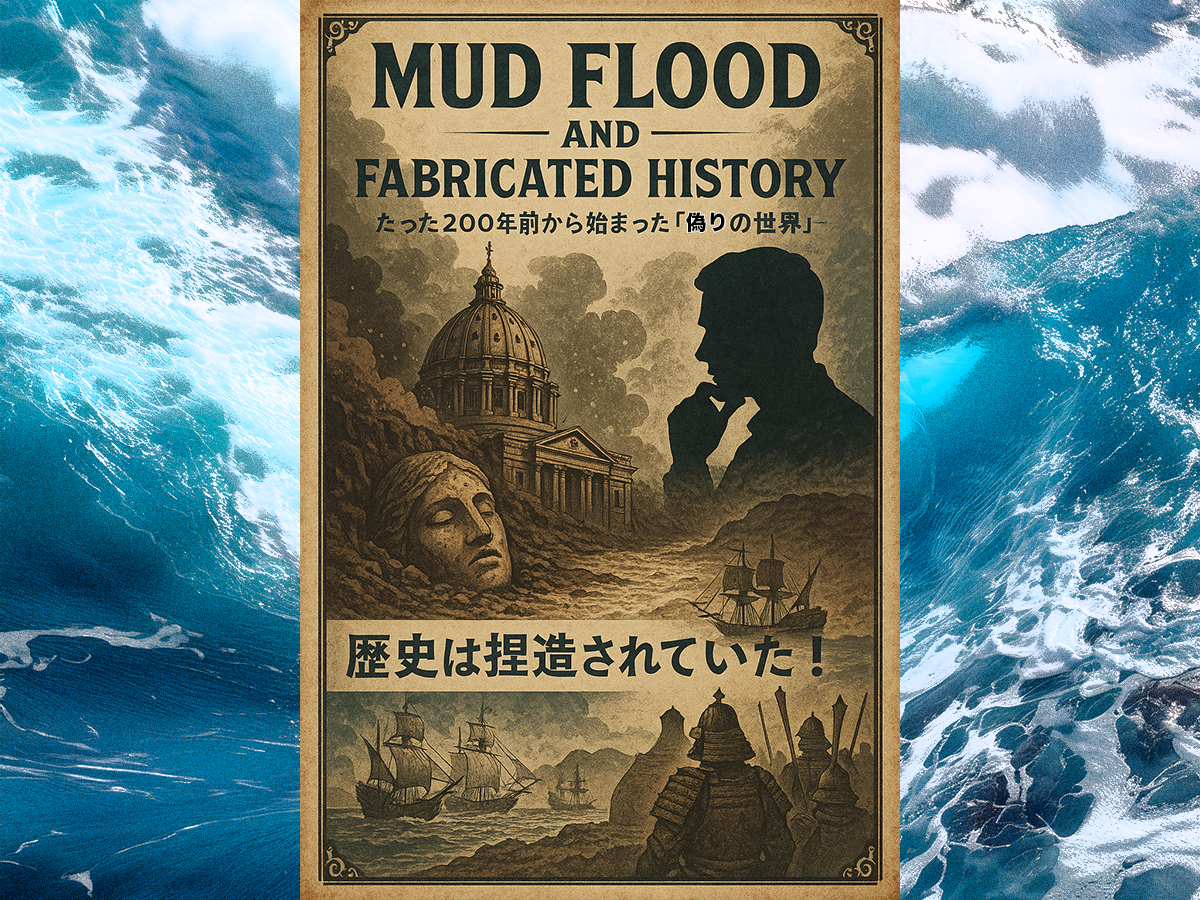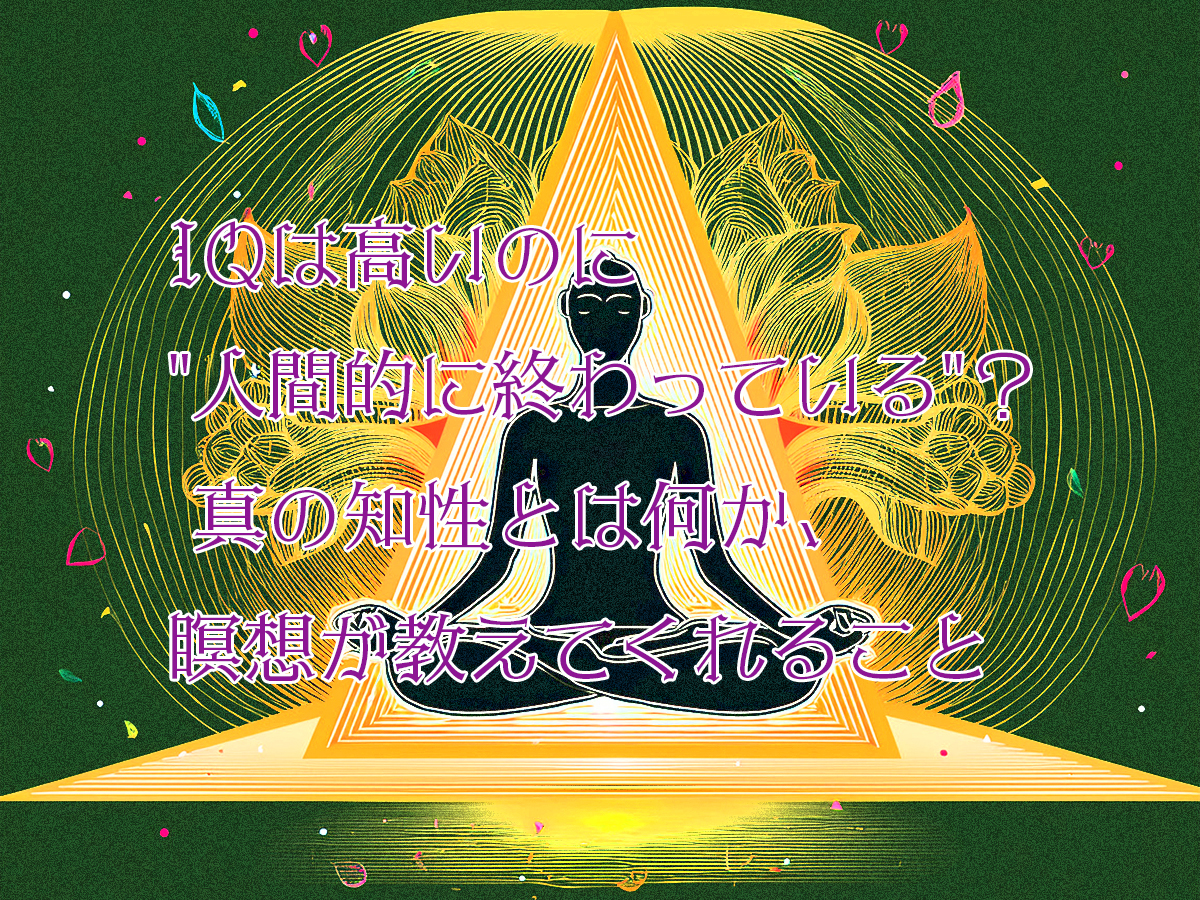ごめん、ニーチェって名前は聞いたことあってもほとんどは知らねぇんだわ。
最近改めて調べたけど。
つまり哲学の本質わかってる?・・・な人がちらほらいるので記事にしてみました。
ニーチェの基本情報
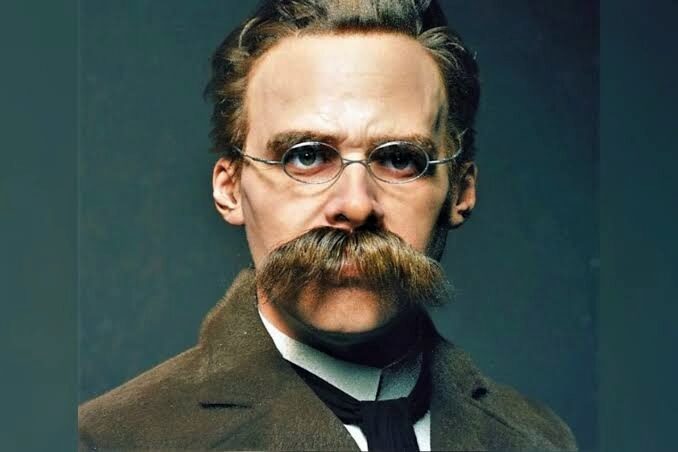
ニーチェ(Friedrich Nietzsche/フリードリヒ・ニーチェ)は、19世紀ドイツの哲学者・ philologist(古典文献学者)で、「神は死んだ」「超人」「永劫回帰」等の思想で知られる哲学界の異端児です。
生没年:1844年〜1900年
国籍:ドイツ
職業:哲学者・文献学者
代表作:
『ツァラトゥストラはこう語った』
『善悪の彼岸』
『道徳の系譜』
『悲劇の誕生』
『権力への意志(遺稿)』
どんな思想の人?
① 「神は死んだ」
キリスト教の神への信仰が近代で形骸化していく中で、
「神という価値観はもう人を導かない」
と断じました。
※これは”無神論“というより、「価値の喪失とそれにどう向き合うか」という問いです。あるいはイエス・キリストの「私たちは皆神の子である」という真意に気付いていたのか否か。
② 「超人(Übermensch)思想」
社会の道徳や常識に縛られず、自分の価値観で生きる人間像。
「超人になれ。羊のままではなく、自己を創造せよ」
③ 「永劫回帰」
「この人生が永遠に何度も繰り返されるとしたら、お前はそれを望むか?」
という仮説で、人間の生き方を根本から問う思想です。
晩年はどうなった?
1889年、イタリア・トリノで発狂状態となり、以後は母と妹に看病されながら事実上廃人として生涯を終えました。
晩年のニーチェは、「自分こそが神だ」等の言葉を残し、自我の崩壊と宗教的妄想が見られました。(悪霊に取り憑かれていた可能性もありますね)
何故今でも人気があるの?
・現代の「生きづらさ」や「虚無感」と共鳴する内容が多い
・自己肯定・自己変革を促すメッセージ性が強い
・美しい詩的な文章で、読み物としても魅力がある
ニーチェは、単なる「難しい哲学者」ではなく、
「現代人の心の闇を100年以上前に暴いた先駆者」
として、今も多くの人に影響を与え続けています。
あ〜、弱者男性・駄目人間が好みそうな人ですね(失礼&本音)
ーーーごほん、本題に入りますね。
「思考は現実化する」
最近の神経科学や心身相関理論では、次のような話がよく語られます。
・心臓は脳よりも先に”感じている”
・心臓から脳へ送られる情報は、脳から心臓に送られる情報よりもはるかに多い
・つまり「心(ハート)」が整っていないと、脳の思考も整わず、現実創造も歪む
これはスピリチュアルな表現で言えば、
「ハートを起点に現実は動く」
「思考より”在り方“が先」という意味です。
では、何故ニーチェは廃人になったのか?
ここで重要なのが、「哲学は精神を救うか?」という問い。
ニーチェは理性を徹底的に使って世界や神を批判しましたが、それによって、
・自我と世界との”ズレ“を強烈に自覚してしまった
・孤立・孤独・矛盾を内面に抱え込み過ぎた
・メンタルと肉体のバランスが崩壊した
頭(理性・知性)だけが過剰に働き、心(感性・共感・身体感覚)が置き去りになった結果とも言えます。
結局、哲学者ですら「感情」「身体」「魂」を無視すれば病む。ニーチェの悲劇は、知性の孤独に飲まれたスピリチュアルな教訓とも取れます。
「哲学とは何か?」
・哲学とは、真理を探す知的営み
・でも、知性だけでは人は救われない
・思考と感性(心)を統合してこそ、人生は整う
生きるとは何だ?ーーーーという意味、哲学とは、
「心・体・魂」を調律する行為になって初めて本当の力を持つ
【哲学批評】作品それらの真意
「神は死んだ。私たちが殺したのだ」――フリードリヒ・ニーチェ
この言葉は、単なる挑発なのか否か。
それは人間の内側に神を再発見せよという、時代の本質に対する鋭い問いかけだろうか?
「神は死んだ」「超人」「力への意志」。
ニーチェの言葉は、いつも断片で消費されています。
その鋭さ、キャッチーさが故に、SNSや自己啓発に抜き出され、
まるで”自分を正当化する札“のように使われてしまう。
しかしその言葉を吐いた本人は、
実際には思い通りにならない女に失恋して狂ってしまった、一人の不器用な男であったという・・・・。
哀しい逸話・・・
ニーチェには、哲学以外の話でも記録が残っている。
・ルー・サロメにキスされて舞い上がる
・その彼女を友人に持っていかれる
・出会ってすぐの女性に突発的に求婚してキモがられる
・最後は精神を病み、姉にコントロールされる人生・・・
・・・結構な惨めな人生だったんですね。(辛口)
人間としてのニーチェは、決して”超人“ではなかったんですね。
むしろ不器用で、現実を生きることが極めて下手だった人間だったとも言えます。
「女は無能」? ニーチェの差別的発言
著作にたびたび登場する女性蔑視の言葉。
「女は子を産むだけの存在」といった記述もあり、中島義道氏はこう切り捨てました。
「ニーチェ哲学の中で、最も読む価値のない部分だ」
・・・確かにその通りかもしれない。
現代の感覚では到底受け入れられない。
だがそれでもニーチェは”読む価値“のある存在ってことなんでしょうね。
哲学としての価値──虚無を超える思想
ニーチェの本当の功績は、「神が死んだ」後の世界をどう生きるかという価値の創造にありました。
・伝統宗教の失墜(ニヒリズム)
・生の本質を力と意志で見出そうとする哲学
・「超人」とは、既存の道徳を打ち破り、自らの価値で生きる人間像
ニーチェは「全てがどうでもいい世界」において、
それでも生きる理由を問い続けた哲学者だったようです。
「ニーチェ信者」としての”弱さ”
ネット上でニーチェの言葉を引用する人々の多くが、
現実に不満を持ち
誰かを見下し
強さを装いたいだけの「ネット弁慶」
に見えてしまうのは否めない。
「ニーチェ自身は天才だったが、彼を信奉する者は大抵馬鹿だ」
と皮肉られるのもわかる。
ニーチェの言葉を都合よく切り取り、自己正当化に使う人々は、
彼が批判した”奴隷道徳“そのものに囚われている。
もし、ニーチェの思想が音楽であるならば、それは「ノイズ」に近い。無秩序のように聴こえるが、その奥には再構築された秩序がある。
「力への意志」も「超人」も、全てはこのノイズの中でこそ響く。
彼の哲学は、”わかりやすい整理された正義“ではない。
むしろ、人間の深淵と混沌の中に潜る為の”暗号“とも言えます。
差別的な思想に反発し
現実的な人物像に失望し
それでも思想の鋭さにうならされる
こういうところがニーチェを読む価値があるのでしょう。
あえて最後まで外した、ツァラトゥストラとは?
「ツァラトゥストラ(Zarathustra)」とは、哲学者フリードリヒ・ニーチェの代表作『ツァラトゥストラはこう語った』に登場する、主人公かつ語り手の名前です。
作品の形式としては物語風の哲学書で、このツァラトゥストラはニーチェ自身の思想を語らせる為の”仮の預言者“のような存在です。
ツァラトゥストラの元ネタ、ゾロアスター教の開祖
この名前は実在の歴史上の人物、ゾロアスター(Zoroaster)=ツァラトゥストラに由来します。
ゾロアスターは、紀元前1000年頃の古代ペルシャに実在した宗教的指導者で、ゾロアスター教(拝火教)の創始者です。
ただし、ニーチェのツァラトゥストラは宗教的教祖ではなく、あくまで”新しい価値観を説く哲学的預言者“として再創造された存在です。
作品『ツァラトゥストラはこう語った』とは?
・出版年:1883〜1891年(4部構成)
・形式:物語風で詩的。章ごとに寓話・演説のように構成されている。
・キーワード:「神は死んだ」「超人(Übermensch)」「永劫回帰」「力への意志」
この作品でニーチェは、伝統的な宗教・道徳観を否定し、新しい人間像である「超人」を提唱します。
ツァラトゥストラの物語の流れ(ざっくり)
- 山で10年過ごしたツァラトゥストラが啓示を得て、人々に教えを説くために下山する → ここで「神は死んだ」という思想が語られる。
- 民衆に語りかけるが理解されない。孤独と絶望を経験しながら、自らの思想を深めていく → 「超人とは何か」「価値の創造とは何か」を探る。
- 様々な人物との対話や出来事を通じて、自身の中にあった迷いや依存を克服していく → それが「力への意志」や「永劫回帰」の思想へと繋がる。
- 最終的に、自らの運命を肯定し、自分であることを選び直す「運命愛(アモール・ファティ)」の境地に至る
何故”ツァラトゥストラ”なのか?
ニーチェがあえてゾロアスターの名を借りたのは、以下の理由が考えられます。
ゾロアスター教は「善悪二元論」を説いた最初の宗教の一つ → ニーチェはこれを転倒して、新しい善悪を作り直したかった。
ニーチェ自身が「この名前こそ最もふさわしい」と述べている。
当時の宗教(特にキリスト教)に対する挑戦的な姿勢が込められている。
現代風に言うと・・・
「ツァラトゥストラ」は、ニーチェ版”メシア”とも言えますが、その目的は救済ではなく、自立と覚醒。
「他人に救われようとするな、自分で自分を救え」
というのがツァラトゥストラの教えです。
じゃあ結局正当化の為に使われるのは違うんじゃないか?
一部の信者はここまで読んだだろうか?
スピリチュアル界隈の誤用に注意
ニーチェが本当に伝えたかったのは「苦悩を肯定し、自己を超えていく力」であり、「宇宙に委ねれば上手くいく」的な受け身の考え方とは真逆。
ただし、スピリチュアル界隈の一部には「現実を引き受け、自分で人生を創造する」というセルフ・マスタリー(自己統合)思想もある為、そこにニーチェの影響が混じる場合もあります。
ちゃんと成仏されてるの?
精神崩壊による死と未練
ニーチェは精神錯乱(おそらく梅毒による進行麻痺)で最晩年を過ごしました。
最期の10年近くは言葉も交わせず、妹に囲われ、著作とは逆に「自己表現できない地獄」にいたとも言えます。
霊的観点では、
・最期に「納得」して死ねなかった魂は、成仏までに時間がかかる
・「自己否定」「怒り」「創造性の封じ込め」=魂に重い荷を残す要因
よって、ニーチェは当初「未成仏」の状態だった可能性があります。
だが、影響力の大きさは魂が浄化される方向に働く
ニーチェの言葉・思想は死後も多くの人に読み継がれました。
特に「自己超克」「神の死」等は、後の20世紀思想・文学・アートに強い影響を与えています。
死後しばらくしてから成仏している可能性が高いという推測もできます。
誰かが本気で悩んだ時、「それでも生を肯定せよ」と囁くような彼の哲学は、時代を超えて使われてきたのです。
魂がこの世に何らかの影響を与え続けること= 霊的な役割を果たし続けている証拠
この視点から考えれば、ニーチェは死後しばらくは未成仏の状態であった可能性もありますが、
現代においては「すでに成仏している」と見る方が自然でしょう。(※必ずしも正解ではないので悪しからず)
哲学とは、「答えを持つ」ことではなく、「問い続ける姿勢」
哲学は処世術と異なり、「すぐに役立つ答え」を与えてくれるわけではありません。
しかしその代わりに、どんな時代でも通用する芯となる自分を育ててくれます。
・時代や流行に左右されない目線
・物事の本質を見極める力
・誰かの言葉より、自分の内なる声を信じる姿勢
これこそが、ニーチェが言った「超人」の精神の根底にあるものです。
哲学者、ルドルフ・シュタイナーとは対照的な人物でしたね。
最後に私からの本音ですが、哲学の意味を履き違えていたり、何かと正当化している人って通常の精神の人と異なり
ハートチャクラが上手く機能していないのと、頭のチャクラもそこまで回ってないんだと思うんですよ。ニーチェとは関係ないというかそれ以前の問題というか。終わり。
別にニーチェ自体を批判してるわけじゃないです、悪しからず。
追記(2025/11/15)

発狂の原因は遺伝性疾患故の脳腫瘍の反応とのこと。