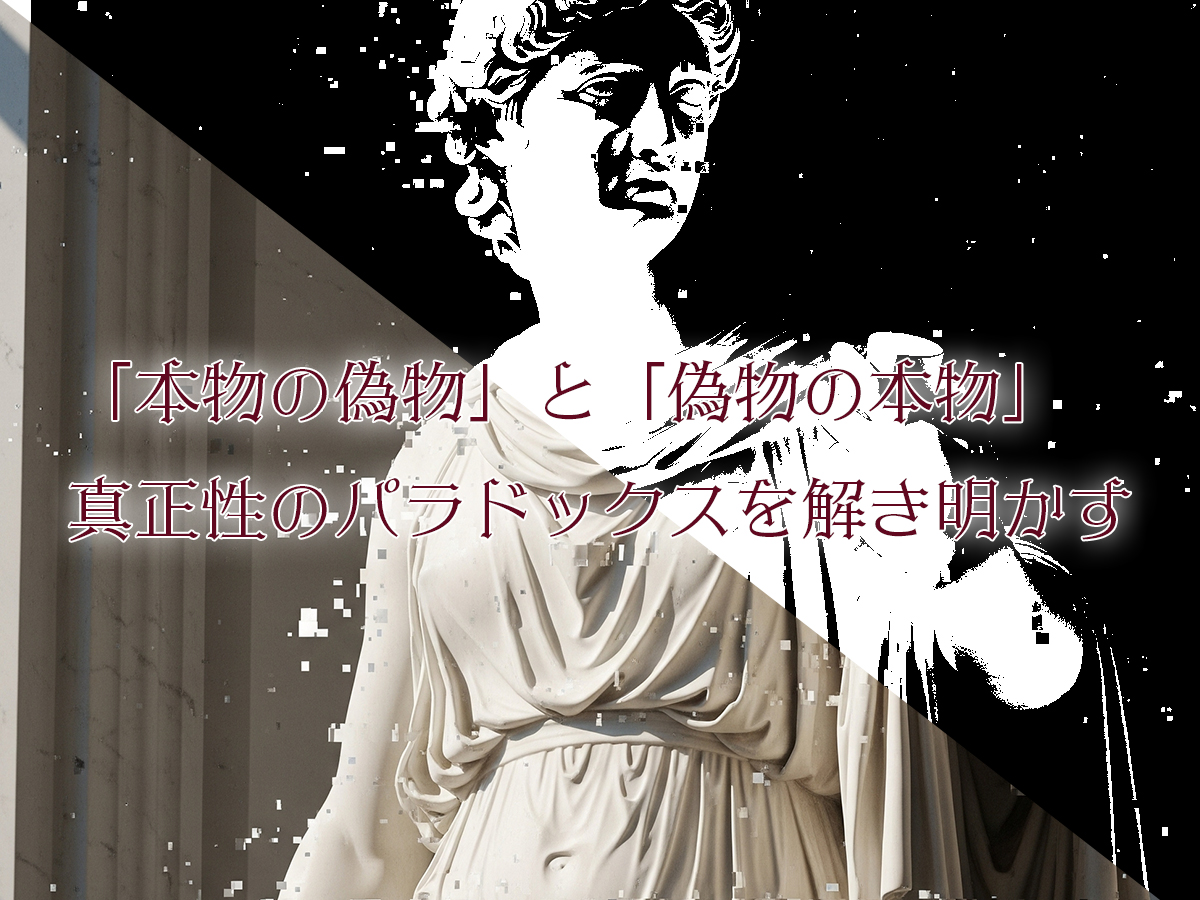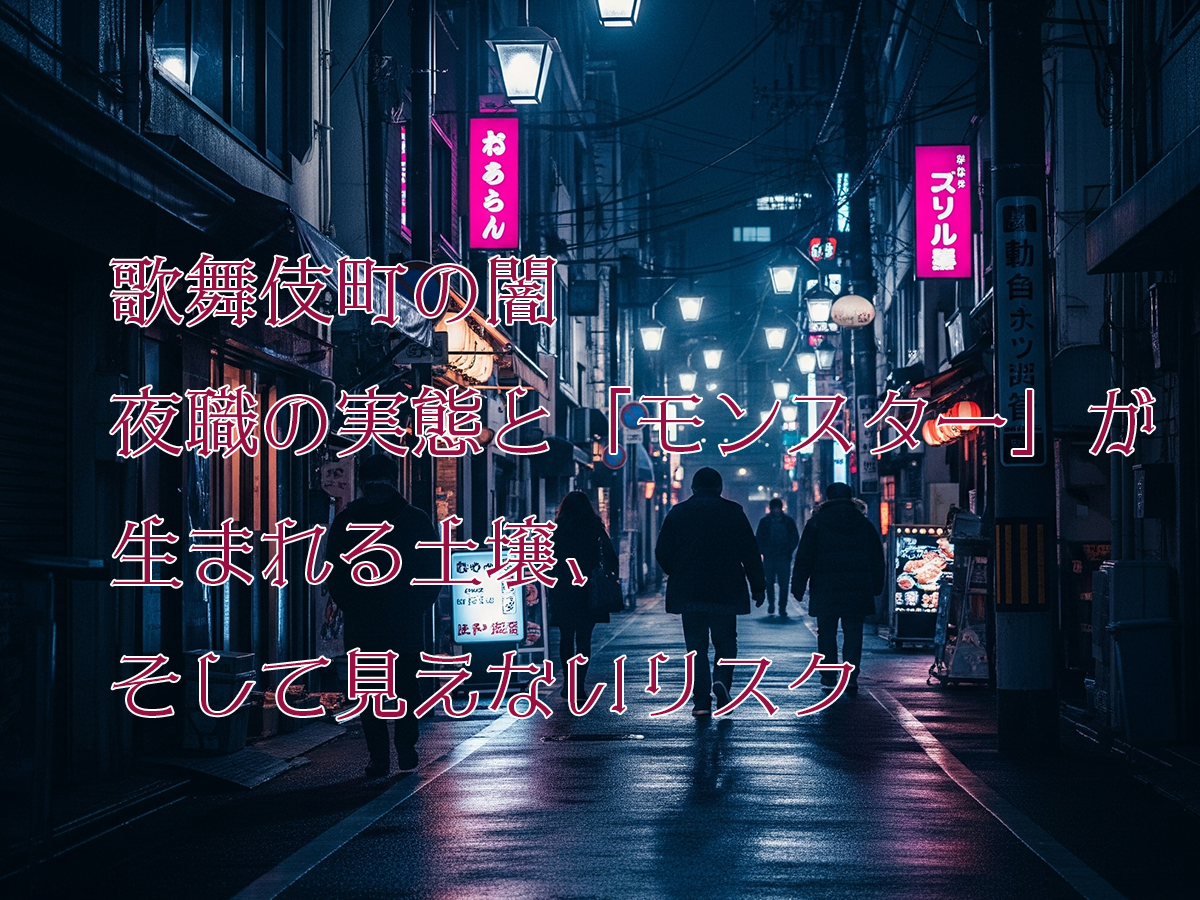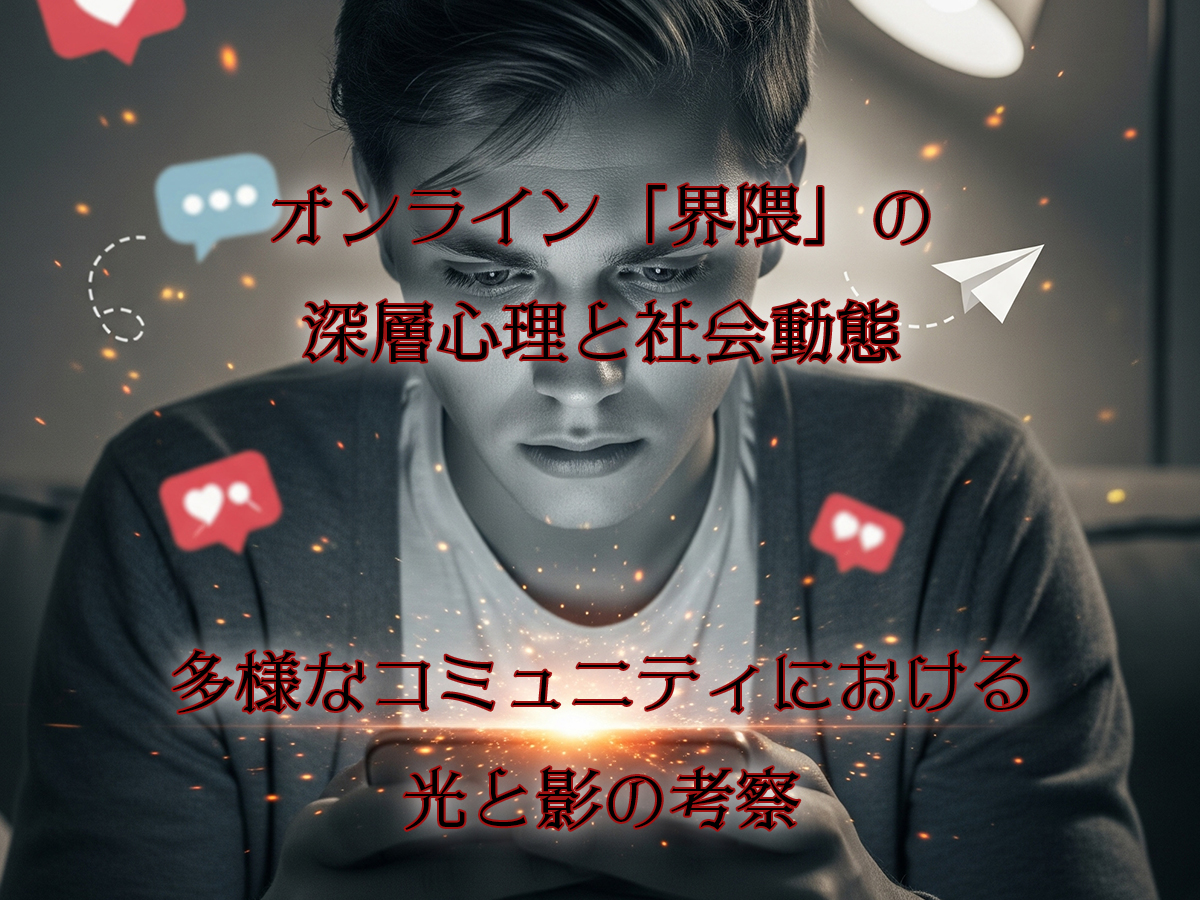1. 序論:真正性のパラドックスを紐解く
「本物の偽物」と「偽物の本物」という問いは、真正性に対する私たちの直感的な理解に根本的な挑戦を突きつける、深遠な哲学的問いかけです。これらの言葉は単なる撞着語法ではなく、オリジナルとコピー、本物と模倣の境界線が著しく曖昧になる複雑な現象を記述するものです。本報告書では、これらのパラドックス的な概念を厳密に分析し、何が「本物らしさ」や「偽物らしさ」を構成するのかを再評価します。
本報告書の目的は、芸術、商業、技術、そしてアイデンティティといった様々な領域からの事例を参照し、厳密な概念分析を提供することにあります。ボードリヤールのシミュラークル理論等の哲学的考察と具体的なケーススタディを統合する学際的なアプローチを採用します。報告書は、単純な二項対立を超え、真正性の文脈的、意図的、そして知覚的な側面を探求します。
この問いかけは、真正性という概念が絶対的で本質的なものではないことを示唆しています。むしろ、その意味は文脈、意図、知覚、そして機能との関係から導き出されるものです。「本物」と「偽物」が固定されたものであれば、これらのパラドックス的な表現は無意味となるでしょう。したがって、この問い自体が、真正性が固有の特性ではなく、外部要因や内部解釈に基づいて常に交渉され、再定義される関係性的な構築物であることを示しています。この認識は、本報告書全体の基盤となり、本質主義的な定義から、より流動的で文脈的な真正性の理解へと焦点を移します。
もし「偽物」が「本物」になり得(本物の偽物)、そして「本物」が「偽物」として暴かれ得る(偽物の本物)のであれば、単一で安定した「オリジナル」や「真正な源泉」という伝統的な概念は、ますます不安定になります。これは、オリジナルという基盤的な権威が薄れ、コピー、シミュレーション、そして構築された現実が拡散する、より広範な文化的変化を示唆しています。この現象は、ボードリヤールの思想や、デジタル複製がもたらす課題と一致します。その意味するところは、「ポスト真正性」の時代への移行であり、そこでは揺るぎないオリジナルという概念がその支配力を失い、現実に対するより流動的で、時には混乱を招く理解へと繋がります。
これらの概念を明確にする為、以下の表で「本物の偽物」と「偽物の本物」の基本的な枠組みを示します。
| 概念 | 中核的な定義 | 根底にある原則 | 初期事例 |
| 本物の偽物 | 非オリジナルであるにもかかわらず、真の価値、機能、または地位を獲得するコピーや模倣品。 | 価値は、有用性、文化的影響、再文脈化、または創造/受容の意図から派生する。 | 美術館のレプリカ、成功した文化の盗用、土産物、キッチュ。 |
| 偽物の本物 | 本物またはオリジナルと認識されるが、実際には構築されたもの、操作されたもの、または固有の「本物らしさ」を欠いていると判明する実体。 | 真正性は、パフォーマンス、製造されたもの、または欺瞞、操作、ハイパーリアリティによって侵食されたもの。 | 偽造高級品、ディープフェイク、作られたブランドの真正性、ソーシャルメディアのペルソナ。 |
この表は、両概念が持つ独特でありながら関連するパラドックスを並列で提示することで、読者が報告書全体を通して概念的な区別を追跡出来るように、分析の枠組みを設定します。
2. 真正性とオリジナリティの基礎
「本物」と「オリジナル」の伝統的な理解は、独自の源泉、唯一の創造物、そして検証可能な来歴に結びついています。この定義は、分野によって異なる形で現れます。芸術においては、真正性はしばしば作家の手、独自の創造、そして歴史的文脈に依存します。贋作は、その意図が起源について欺くことにある為、これを直接的に挑戦します。商業においては、真正性はブランドの完全性、品質、そして合法的な起源に関連します。偽造品は、確立されたこれらの規範に違反するため「偽物」とされます。アイデンティティの文脈では、真正性は自己の真実性、内面と外面の一貫性を意味します。
真正性に対する歴史的および哲学的視点を見ると、特にルネサンス以降の個人としての芸術家の台頭とともに、オリジナリティに対する歴史的な重視が見られます。ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」の概念は、オリジナル作品の持つ独特な価値が機械的複製によって損なわれることを示しており、この「本物」に置かれる価値を理解する為の重要な背景を提供します。真正性の概念は、検証可能な起源に焦点を当てることから、より主観的で経験的な理解へと進化してきました。
真正性の初期の定義が、来歴や法的起源といった客観的な基準に傾倒する一方で、「本物の偽物」や「偽物の本物」の存在は、主観的な知覚と社会的な合意が決定的な役割を果たすことを示しています。例えば、偽造品は客観的には偽物ですが、着用者にとってステータスシンボルとして機能する場合、その「本物らしさ」は主観的に構築されます。同様に、歴史的な再現イベントは客観的にはオリジナルの出来事ではありませんが、主観的には「本物」の体験を提供します。これは、検証可能な事実と知覚された現実との間の動的な緊張を示唆しており、真正性は単に固有の性質ではなく、交渉された社会的な構築物でもあることを意味します。
ベンヤミンの「アウラ」の概念は、オリジナルの持つ独自の価値を強調しています。しかし、デジタル技術や大量生産の普及により、ほとんどあらゆるものが完璧に複製されたり、シミュレートされたりするようになりました。これは根本的な問いを投げかけます。もし全てがコピー可能であるならば、「オリジナル」はその特別な地位を失うのでしょうか、それともその希少性ゆえにその価値は更に偶像化されるのでしょうか。パラドックスは、複製が「偽物」を遍在させる一方で、対照的に「本物」への欲求を強める可能性があるということです。例えその「本物」が定義や特定が困難になったとしても、この状況は、後に議論される境界線の曖昧化の舞台を設定します。
3. 「本物の偽物」の探求:模倣が独自の現実を獲得する時
コピーや模倣品が真の価値や地位を獲得する事例を分析すると、その「本物らしさ」がどのようにして確立されるのかが明らかになります。
美術館のレプリカと教育的価値
高品質なレプリカは、オリジナルではないにもかかわらず、教育、アクセシビリティ、保存において重要な「本物」の目的を果たします。これらはより広範な観客が芸術や歴史を体験することを可能にし、その機能的な真正性において「本物の偽物」となります。その価値は、オリジナルとの同一性ではなく、提供される経験と知識の共有にあります。
土産物と感傷的価値
土産物は通常、ランドマークや物品の大量生産された模倣品ですが、個人にとっては記憶や経験を象徴する「本物」の感傷的、象徴的価値を獲得します。その「本物らしさ」は、そのオリジナリティではなく、個人的な重要性に結びついています。これは、感情的な繋がりが物理的な起源よりも優先される例です。
キッチュとパスティーシュ:美的・文化的再評価
キッチュは、しばしば当初は「偽物」や真正でないものとして退けられる、本物の芸術を模倣した大量生産の芸術です。しかし、キッチュは広範な魅力、ノスタルジックな価値、あるいは皮肉な評価を通じて文化的な「本物らしさ」を獲得し、正当な文化現象となることがあります。同様に、パスティーシュは、ユーモラスな意図やオマージュの意図をもって様式的な模倣を行うことで、単に欺くのではなく、借用された要素から新しく「本物」の何かを創造します。これらの例は、模倣が独自の美的価値と文化的地位を獲得し得ることを示しています。
文化の盗用:再解釈の複雑性
ある文化から要素を取り出し、別の文脈で再構築することは、議論の的となることがあります。理解の欠如から搾取的または「偽物」と見なされることもありますが、これらの盗用は、倫理的配慮を伴いながらも、真に新しく「本物」の文化的形態の創造に繋がることもあります。ここでの「本物らしさ」は、その起源が借用されたものであっても、新しい文化的な産物の中に存在します。
ファッションのトレンドとファストファッション
ファストファッションは、高級デザインを複製し、それを手頃な価格で提供します。これらはオリジナリティや素材の点で「偽物」ですが、その広範な普及と現代のスタイルへの影響において「本物」となります。その「本物らしさ」は、その社会的および経済的影響力にあります。
「本物の偽物」の事例では、「偽物」の対象や出来事が、何らかの形でオリジナルに変容することによって「本物」になるわけではありません。そうではなく、その「本物らしさ」は、その機能(教育的、社会的、経済的)、それが提供する経験、または個人や社会によってそれに帰属される意味から派生しています。これは、真正性が検証可能な起源(存在論)だけでなく、有用性、感情的な共鳴、そして文化的影響にも関わることを意味します。価値は「それが何であるか」から「それが何をするか」または「それがどのように感じられるか」へと移行します。
多くの「本物の偽物」(美術館のレプリカ、ファストファッション、土産物)は、排他的または遠隔のオリジナルをより広範な観客にアクセス可能にしたいという欲求から生まれます。これは、文化的経験や物質的な商品を民主化しようとする社会的な傾向を示唆しています。これはオリジナルの「アウラ」を希薄化させる可能性がありますが、同時に参加と関与を広げることで、新しい形の「本物」の価値を創造します。その意味するところは、「偽物」が伝統的な真正性の概念に挑戦しながらも、包摂と共有された経験を促進する進歩的な社会機能を果たすことができるということです。
4. 「偽物の本物」の探求:真正性が問われる、あるいは構築される時
一見すると本物に見える実体が、実は構築されたもの、操作されたもの、あるいは固有の「本物らしさ」を欠いていると判明する状況を検証します。
美術品の贋作と欺瞞の意図
美術品の贋作は、典型的な「偽物の本物」です。これらは本物に見え、しばしば専門家を欺きますが、その「本物らしさ」は欺瞞の意図と真の来歴の欠如によって損なわれます。贋作であることが暴かれると、例え物理的には変化がなくても、その認識されていた真正性は剥奪されます。
偽造品とブランドの希薄化
偽造高級品は、本物の製品を模倣し、しばしば素人目には区別がつきません。一部の人々にとってはステータスシンボルとして機能するかもしれませんが、その「本物らしさ」は、その違法な起源、品質保証の欠如、そして関与する欺瞞によって根本的に損なわれています。これらはオリジナルブランドの真正性を希薄化させます。
ディープフェイクと信頼の侵食
ディープフェイクの深刻な影響は、AIを用いて極めてリアルでありながら完全に捏造された画像、音声、または動画を作成することにあります。これらはまさに「偽物の本物」であり、現実の説得力のある幻想を提示し、視覚的証拠と情報の完全性に対する信頼を損ないます。記録された現実そのものの「本物らしさ」が問われることになります。
作られた真正性とブランドのストーリーテリング
ブランドがマーケティング、ストーリーテリング、そしてキュレーションされた体験を通じて、いかに自らの「真正性」を積極的に構築しているかについて議論します。これは、「真正性」が本当に固有のものであるのか、それとも慎重に設計された見せかけであり、その作為的な性質において「偽物の本物」であるのかという問いを提起します。
ソーシャルメディアのペルソナとキュレーションされた自己
個人がソーシャルメディア上で、高度にキュレーションされた理想化された自己を提示することについて分析します。この「本物」のペルソナは、しばしば注意深く構築された「偽物の本物」であり、知覚される真実性がパフォーマンスである為、オンラインアイデンティティの真の「本物らしさ」について疑問が生じます。
美術品の修復
美術品の修復は、その「元の状態」に戻すことを目指す一方で、必然的に変更を伴います。もしかなりの部分が置き換えられた場合、修復された作品は依然として「オリジナル」なのでしょうか、それともオリジナルを近似するだけの新しい、構築された実体、すなわち「偽物の本物」となっているのでしょうか?
「偽物の本物」の事例は、真正性が不変の性質ではなく、外部からの操作(贋作、ディープフェイク)や内部的な知覚(作られた真正性、ソーシャルメディアのペルソナ)に非常に影響されやすいことを示しています。「本物」に見えるものが、構築されたものや欺瞞であると暴かれることがあり、真正性に対する私たちの理解が、しばしば信頼と検証可能な情報に基づいていることを浮き彫りにします。そして、その両方が損なわれ得ることを示しています。これは、知覚された現実の脆弱性を露呈するものです。
「本物の偽物」がしばしば肯定的な機能を果たすのに対し、「偽物の本物」はしばしば欺瞞を伴い、社会の根幹をなす要素を損ないます。美術品の贋作は美術史を歪め、偽造品は経済と消費者の信頼を傷つけ、ディープフェイクは真実と民主的議論の基盤そのものを侵食します。これは、本物と偽物の境界線が曖昧になる一方で、その創造の意図と受容の結果が倫理的評価にとって極めて重要であることを示しています。「偽物の本物」の拡散は、信頼、情報の完全性、そして現実の共有された理解に対して重大な脅威をもたらし、社会を客観的事実がますます争われる「ポスト真実」の環境へと押し進めています。
5. 意図的な欺瞞と真正性の倫理的境界線
「本物の偽物」がその非オリジナル性を明示しつつ価値を獲得する一方で、真正性の議論には、意図的な欺瞞を伴う「偽物」の側面も存在します。これは、あたかも本物であるかのように振る舞いながら、実際には虚偽や不誠実さに基づいて他者を欺く行為を指します。このようなケースは、前述のパラドックスとは異なり、倫理的な問題と社会的な信頼の喪失を伴います。
5.1 虚言癖と信頼の破綻
虚言癖を持つ個人は、他者から良く見られたい、あるいは自分を大きく見せたいという欲求から、頻繁に虚偽の情報を語ります。彼らが提示する「真実」は、しばしば偽りの詳細や全くの虚偽を含み、意図的に相手を欺こうとします。このような嘘は、一時的に自己の承認欲求を満たすかもしれませんが、最終的には時系列の整合性が取れなくなり、周囲からの信用を失墜させます。虚言癖のある人は、嘘が他者を傷つけることを想像しにくい傾向があり、その結果、人間関係の孤立や職を転々とするといった事態を招く可能性があります。これは、透明性や一貫性が信頼の基盤となる社会において、その根幹を揺るがす行為と言えます。
5.2 欺瞞的なスピリチュアル実践と搾取
スピリチュアル界隈に蔓延る「自分自身を救っていなく、スピリチュアルをやる」という状況は、しばしば「スピリチュアル詐欺」という形で現れます。これは、実証不可能な霊感や超能力をでっち上げ、人々の不安を煽り、高額な商品やセミナー参加権を売りつけたり、巨額の寄付を強要したりする手口です。詐欺師は、被害者の心の隙間に入り込み、洗脳を通じて自由な意思決定能力を奪い、自発的に金銭を支払わせることもあります。
このような行為は、医療やカウンセリングの倫理基準に照らしても問題があります。例えば、カウンセラーは効果が立証されていない疑似科学や霊的治療をクライエントに実施すべきではないとされています。また、クライエントの福祉に貢献するという目的から逸脱し、カウンセラー自身の欲望の為にクライエントを利用することは厳しく禁じられています。ここでの「偽物」は、その機能が「偽物であること」にあるのではなく、「本物であると偽って」、他者を欺き、搾取することを目的としています。
5.3 意図と透明性の重要性
前回の議論で触れた「プラセプラス」のような「食用偽薬」は、「偽物である」という事実を明示し、その上で特定の機能(飲んだことに意味があるというユーモアや、薬を飲ませたくない相手への代替)を提供していました。つまり、透明性があり、欺瞞の意図がありませんでした。
しかし、本節で挙げられたケースでは、意図的な欺瞞が核心にあります。虚言癖もスピリチュアル詐欺も、相手に「本物である」と信じ込ませることで、自己の利益や承認欲求を満たそうとします。このような行為は、信頼関係を損ない、経済的、精神的、社会的に深刻な被害をもたらす可能性があります。情報の発信元が信頼出来るか、その情報に偏りがないか、複数の情報源と照らし合わせる等、批判的な視点を持つことが重要になります。
このセクションは、真正性の議論において、単なる模倣や複製と、意図的な欺瞞との間に明確な倫理的境界線が存在することを強調します。後者は、社会の基盤となる信頼を侵食し、深刻な結果を招く為、その区別は極めて重要です。
ソースと関連コンテンツ
▶︎ 代償が大きすぎる、虚言癖。
▶︎ 研究における欺瞞:種類、倫理的考察と例
▶︎ 虚言癖は治せる? 虚言癖がある人のセルフケアや治療法をご紹介します!
6. 境界線の曖昧化:シミュラークル、ハイパーリアリティ、そしてポスト真正性の時代
伝統的な「本物」と「偽物」の概念に挑戦する高度な哲学的概念について議論します。
シミュラークルとハイパーリアリティ(ボードリヤール)
ジャン・ボードリヤールのシミュラークル概念を導入します。これは、オリジナルを持たないコピーであり、本物と偽物の区別が崩壊する状況を指します。模倣からシミュレーションへの進展を説明し、シミュレートされたものが現実そのものよりも「本物」になるハイパーリアリティへと至る過程を解説します。例えば、ディープフェイクは、存在しなかった現実を創造するシミュラークルの完璧な例です。バーチャルリアリティやメタバースは、シミュレートされた体験が最重要となるハイパーリアルな環境を代表しています。
デジタルツインと仮想表現
デジタルツインは、物理的なオブジェクトの仮想モデルであり、リアルタイムで更新されます。その機能性において「本物」である一方で、物理的なオリジナルとそのデジタルコピーの間の境界線を曖昧にし、どちらが主要な「本物らしさ」を持つのかという疑問を提起します。
AI生成アートと作者性
AIが芸術を創造することの意味を探ります。それは「本物」の芸術なのでしょうか?「芸術家」は本物なのでしょうか?これは、人間のオリジナリティと作者性という伝統的な概念に挑戦し、創造者の「本物らしさ」が曖昧なポストヒューマンな創造の理解へと私たちを押し進めます。
NFTとデジタル希少性
NFTが、本質的に複製可能なデジタル資産に対して人工的な希少性と「所有権」をどのように生み出すかを分析します。これはデジタル領域における所有権の「本物らしさ」を構築し、例え基となるデジタルファイルがコピーであっても、「オリジナル」と「価値あるもの」を構成するものの境界線を更に曖昧にします。
不気味の谷
人間そっくりのレプリカが不快感を呼び起こす現象について議論します。この現象は、模倣がほぼ完璧でありながら微妙にずれている場合に、「偽物」と「本物」を調和させようとする私たちの生来の葛藤を浮き彫りにし、それらを区別する上での知覚的課題を強調します。
技術とメディアが境界線の曖昧化を加速させていることは明らかです。デジタル技術は単なる複製ツールではなく、既存の枠組みに挑戦する新しい形の「現実」を積極的に創造しています。「ポスト真実の時代」の影響について議論し、客観的な現実がますます争われ、主観的な物語が優勢になることで、「偽物の本物」と真の情報を区別することが困難になっています。
ボードリヤールのシミュラークル概念と、ディープフェイク、デジタルツイン、バーチャルリアリティといった現象の出現は、コピーがもはや既存のオリジナルを単に模倣するだけでなく、主要な現実となり得る、あるいはオリジナルがなくても存在し得るという根本的な変化を示唆しています。これは存在論的な逆転であり、シミュレートされた、あるいはコピーされた実体が独自の独立した存在と影響力を獲得し、時にはその文脈で「本物」が何を意味するかを定義することさえあります。「本物」はシミュレーションの機能となり、その逆ではありません。
本物と偽物の区別が崩壊し、シミュレーションが現実と区別出来なくなり、あるいは現実を凌駕するようになると、真実を知り、検証する為の私たちの伝統的な方法(認識論)は深く挑戦されます。ディープフェイクが説得力を持つ、ブランドの真正性が作られるといった状況で、私たちはどのようにして何が「本物」であるかを識別すれば良いのでしょうか?これは信頼の危機と、情報と経験の性質に関する広範な不確実性に繋がります。「ポスト真正性の時代」を乗り越えるには、批判的思考だけでなく、ハイパーリアリティに満ちた世界で知識を獲得し、真実を確立する方法の根本的な再評価が必要です。
7. 各領域への影響:芸術、商業、アイデンティティ、そして社会
「本物の偽物」と「偽物の本物」が異なる分野に与える影響を分析します。
芸術と文化
贋作やAI生成アートは、作者性、オリジナリティ、そして人間の創造性の価値といった概念に挑戦します。一方で、レプリカや歴史的な再現イベントは、アクセスを民主化し、関与を促進します。キッチュやパスティーシュは、美的境界を拡張します。文化の盗用は、「本物の偽物」との関わりにおいて敬意の必要性を浮き彫りにします。
商業と経済
偽造品は、経済的損失、ブランドの希薄化、そして消費者の欺瞞に繋がります。著作権法や知的財産法は、「本物」の創造物を保護する為に不可欠です。戦略的な利用としては、ブランドが「作られた真正性」を用いて消費者と繋がり、本物と構築されたブランドアイデンティティの境界線を曖昧にしています。ファストファッションは、「本物の偽物」(模倣品)が市場トレンドを牽引する例です。
アイデンティティと自己認識
ソーシャルメディアのペルソナは、個人がいかに自己のアイデンティティの「偽物の本物」を作り出しているかを示しており、真の自己表現とパフォーマンスの間の問いを提起します。デジタルツインやバーチャルリアリティといった技術的な拡張は、アイデンティティをデジタル領域へと広げ、「偽物」の環境で「本物」の体験を創造します。治療用クローンは、「本物」の人間を構成するものが何かという深遠な問いを投げかけます。
社会と信頼
ディープフェイクや「ポスト真実の時代」は、機関、メディア、そして共有された現実に対する公共の信頼を損ない、事実と捏造を区別することを困難にしています。バーチャルリアリティやメタバースは、それ自身の「本物」の相互作用と経済を持つ新しい社会空間を創造し、伝統的な社会構造に挑戦しています。
シミュレーションとコピーの能力は、全ての領域において二面性を持っています。一方では、偽造品による経済的損害、ディープフェイクによる信頼の侵食、文化の盗用における倫理的ジレンマといった重大な脅威をもたらします。他方では、レプリカによる芸術へのアクセス民主化、AI生成アートによる新しい創造形態の促進、バーチャルリアリティにおける全く新しい経済と社会空間の創造といった計り知れない機会を提供します。これは、「本物の偽物」と「偽物の本物」の現象が本質的に良いか悪いかではなく、その影響が意図、文脈、そして社会的な規制に大きく依存することを示唆しています。
伝統的に、価値はしばしば希少性とオリジナリティに結びついていました(例:芸術作品の唯一無二のアウラ)。しかし、「本物の偽物」の多くの事例(例:土産物、歴史的な再現イベント)では、価値は対象の独自性からではなく、それが提供する経験やその有用性から派生しています。NFTでさえ、人工的な希少性を生み出す一方で、その根底にある価値は、デジタルエコシステム内のコミュニティ、ステータス、または有用性から来ています。これは、価値がますます没入型体験、機能的利益、そして知覚された繋がりにより重きを置く、より広範な経済的および文化的傾向を示しています。これは、将来の経済モデルと文化的消費に深遠な影響を与えます。
8. 結論:パラドックスを乗りこなし、未来の展望
「本物の偽物」と「偽物の本物」は単純な矛盾ではなく、コピーとシミュレーションに満ちた世界における真正性の複雑で進化する性質を表しています。真正性は固定された客観的な性質ではなく、起源、意図、機能、知覚、そして文脈の動的な相互作用であることを再確認する必要があります。主要な区別は、「本物の偽物」が非オリジナル性にもかかわらず有用性や文化的受容を通じて正当性を獲得する一方で、「偽物の本物」は精査されると崩壊する欺瞞的または構築された真正性であるという点にあります。
ますますハイパーリアルな環境において、個人と社会にとっての意味合いを考察します。「ポスト真実の時代」において、どのように批判的識別力を養うべきでしょうか?複製とシミュレーションの利点(例:アクセシビリティ、新しい創造形態)と、欺瞞のリスクや信頼の侵食とのバランスをいかに取るかという継続的な課題を検討します。
この状況を乗り越えるには、文脈、意図、そして存在し得る複数の「本物らしさ」の層に対する洗練された理解が必要です。真正性の未来は、単一のオリジナルに戻ることではなく、その多様な現れと、それらを創造し消費することに伴う倫理的責任をより微妙に認識することにあるでしょう。
本報告書全体を通して、「本物」と「偽物」を区別する為の伝統的な指標がもはや十分ではないことが示されています。ディープフェイク、作られた真正性、そしてハイパーリアリティの台頭により、個人と社会は、真実と捏造を識別する上で前例のない課題に直面しています。これは、高度な批判的思考、メディアリテラシー、そして知覚された現実に対する絶え間ない問いかけを必要とします。その意味するところは、情報と情報源を批判的に評価する能力が、この複雑な情報環境における基本的な生存スキルとなるということです。
真正性を対象や人物の固有で静的な特性として捉えるのではなく、「本物の偽物」と「偽物の本物」の分析は、それが交渉、検証、そして再評価という継続的なプロセスであることを明らかにします。対象の「本物らしさ」は、変化する文脈、新しい情報、または進化する社会的価値に基づいて付与されたり(「本物の偽物」のように)、取り消されたり(「偽物の本物」のように)することがあります。これは、真正性の本質主義的な理解から、真正性が社会的、文化的、技術的な相互作用を通じて継続的に構築され、争われ、確認される、パフォーマンス的かつ関係性的な理解への移行を示唆しています。この動的な理解は、真正性の未来に適応する為に不可欠です。