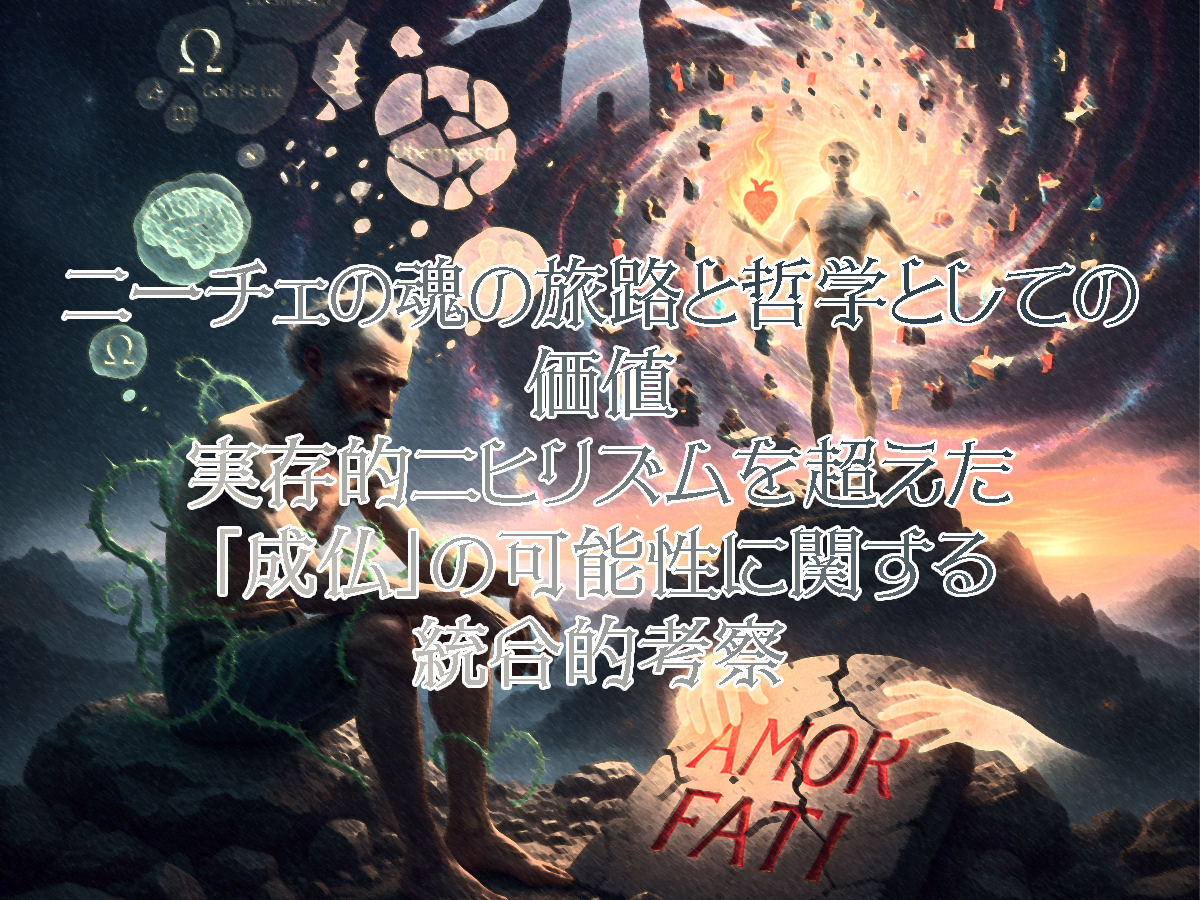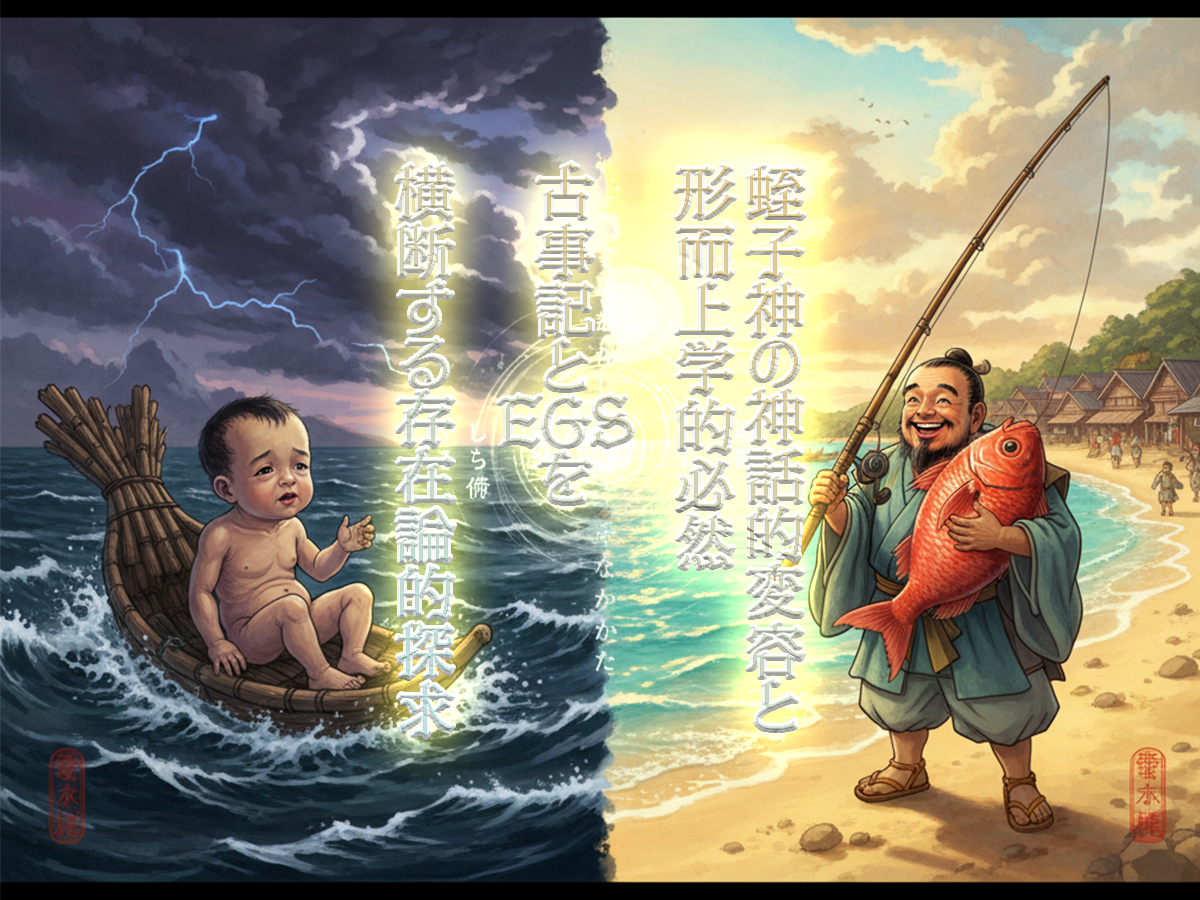序章:知性の孤独と魂の問い──ニーチェを巡る現代の葛藤
フリードリヒ・ニーチェ(Friedrich Nietzsche, 1844年〜1900年)は、19世紀ドイツの哲学者・文献学者であり、「神は死んだ」「超人」「永劫回帰」といった思想を通じて、西洋哲学の根幹を揺るがした異端児として知られている。彼の著作は、伝統的な価値観の崩壊(ニヒリズム)を予見し、現代の「生きづらさ」や「虚無感」と共鳴するメッセージ性を持つ為、100年以上経った今も多くの人々に影響を与え続けている。
本報告書の目的は、ニーチェが説いた哲学的な理想の極致と、彼が迎えた悲劇的な晩年(1889年に発狂し、事実上廃人として生涯を終えた)との間に横たわる深い矛盾を、現代の心身相関理論や精神分析、更には東洋的な「成仏」(魂の安寧)という概念を援用して多角的に分析することにある。
1.1. 本報告の課題設定:「神の死」と「成仏」という対極の問い
ニーチェは、自己の運命の必然性を肯定し、愛しうることで創造性を発揮するという「運命愛(Amor Fati)」の思想を説いた。これは、人生の苦悩、醜さ、喜びの全てを永遠に何度も繰り返すとしても、それを望むかという「永劫回帰」の試練を乗り越え、自己を完全に肯定する究極の境地を意味する。この運命愛は、ニーチェが到達しようとした最高の自己肯定であり、哲学的な意味での「究極のコヒーレンス」(調和)の表現であると解釈出来る。
しかし、この壮大な思想体系を構築した本人は、晩年、イタリアのトリノで発狂状態となり、母と妹に看病されながら、事実上の廃人として生涯を終えた。彼は「自分こそが神だ」といった宗教的妄想や自我の崩壊を示しており、その結末は、彼が理想とした「超人」とはかけ離れた、究極の自己喪失であった。この哲学的な理想と、現実の精神錯乱というギャップこそが、本報告が解明すべき哲学的な核心である。
また、現代において「思考が現実化する」といった心身相関やスピリチュアルな概念が広がる中で、ニーチェの「力への意志」が、安易な自己肯定や受動的な願望実現として消費されていないかという批判的視点も導入する必要がある。彼の哲学の厳格さと、現代におけるその断片的な消費は、しばしば混同されがちである。
1.2. ニーチェの思想と現代人の「生きづらさ」の共鳴
ニーチェは、単なる「難しい哲学者」としてではなく、「現代人の心の闇を100年以上前に暴いた先駆者」として今も多くの人に影響を与え続けている。彼の思想は、現代社会における伝統宗教の失墜や、集団的な価値観の喪失によって生じるニヒリズム(虚無感、価値の喪失)と深く共鳴する。彼の提唱した「自己肯定・自己変革を促すメッセージ性の強さ」は、現代の疎外感や「生きづらさ」を感じる人々に、自立と覚醒を促す教えとして受け止められている。
その一方で、彼の哲学は、その鋭さやキャッチーさから、SNSや自己啓発の文脈でしばしば断片的に抜き出され、言葉の表面だけが消費される傾向にある。彼の思想が、現実への不満を抱え、誰かを見下し、強さを装いたいだけの「ネット弁慶」のような人々に、自己正当化の道具として利用されてしまうという構造は否めない。この断片化は、彼の思想の深遠な苦悩と、そこから価値を創造しようとした厳格な意志を覆い隠してしまう危険性を孕んでいる。
第二部:絶対的な「生」の肯定としてのニーチェ哲学
ニーチェ哲学の本質は、既存の価値観が崩壊した後の世界において、いかにして生命を肯定し、新しい価値を創造するかという、実存的な問いに正面から向き合う点にある。
2.1. 「神は死んだ」後の価値創造:ニヒリズムの克服
ニーチェの有名な言葉「神は死んだ」は、単なる無神論の宣言ではない。これは、西洋文明を支えてきたキリスト教の神への信仰という「究極的な価値観」が近代において形骸化し、もはや人々を導く力を失ったという文明史的な危機宣言である。この価値観の喪失、すなわちニヒリズムは、人類にとって単なる絶望ではなく、それまで神や超越的なものに依存していた「価値創造の責任」を人間自身が引き受けなければならないという「自由」と「義務」を伴うものであった。
2.2. 超人(Übermensch)思想の真意:自己創造の義務
「超人」思想は、このニヒリズムの危機を乗り越える為の具体的な人間像を提示する。超人とは、社会の道徳や常識、既存の価値観(ニーチェが「奴隷道徳」と批判したもの)に縛られることなく、自分の内なる価値観で生きる人間を指す。「超人になれ。羊のままではなく、自己を創造せよ」というメッセージは、受動的な人生を否定し、能動的な価値創造を厳格に要求する。
ニーチェの代表作『ツァラトゥストラはこう語った』では、ツァラトゥストラが説く三変身(駱駝→獅子→子供)の寓話を通じて、超人への道のりが示される。駱駝は重荷を背負い、伝統や慣習に耐え忍ぶ段階を象徴する。続く獅子は、「汝為すべし」という伝統的な道徳の価値を破壊する「自由な精神」の段階であり、ニヒリズムの克服に向けた破壊的意志を体現する。しかし、究極の目標は、破壊的な獅子を超えて「子供」になることである。子供は、純粋な創造性を持ち、「踊る星」のように人生を創造的に導く存在であり、究極の肯定的意志を持つ。この創造的な精神こそが、超人の核となる。
2.3. 運命愛(Amor Fati)の厳格さ:永劫回帰の試練
ニーチェの思想の中でも最も厳格な概念の一つが、運命愛(Amor Fati)である。これはラテン語で「運命の愛」を意味し、運命は必然的なものとして人間に降りかかるが、それにただ忍従するだけでは創造性は生まれないと説く。真の創造性とは、この必然的な運命を積極的に肯定し、自己のものとし、愛しうる能力から発揮される。
この思想は「永劫回帰」の仮説によって試される。「この人生が永遠に何度も繰り返されるとしたら、お前はそれを望むか?」という問いは、人間の生き方を根本から問い直す倫理的な試練である。もし、自分の人生の全て、その苦悩や醜さ、失敗でさえも無限に繰り返すことを喜んで肯定出来るならば、その生は価値を創造したことになる。この運命愛こそは、ニーチェが生涯を通じて理論的に達成しようとした、物理的な苦痛や精神的な失敗さえも完全に受容し肯定する「究極のコヒーレンス」(心身霊の全てを調和させる最高段階の在り方)の哲学的な表現である。
2.4. 哲学の誤読:何故ニーチェは「弱者」に都合よく利用されるのか
ニーチェの哲学は、本来、自己を律し、自立する「貴族的な精神」を要求する極めて厳格な思想である。しかし、現代社会においては、彼の思想がしばしば誤解され、利用されている。彼の言葉を引用する人々の多くが、現実に不満を持ち、誰かを見下し、強さを装いたいだけの「ネット弁慶」として見えてしまうことは否めない。
彼らが陥る罠は、ニーチェが批判した「奴隷道徳」そのものに囚われている点にある。奴隷道徳とは、弱者が強者(真の価値創造者)を妬み、その強者の言葉や価値観を都合よく切り取り、自己の復讐心や不満を正当化する為に使う構造である。ニーチェは、既存の道徳を打ち破ることを求めたが、彼の言葉を「自分を正当化する札」のように使う行為は、結局のところ、自己の弱さや受動的な状態を覆い隠す為の、新たな依存形態に過ぎない。真の超人は、自己の混沌を力に変え、秩序を再構築する意志を持つが、誤読者は混沌を混沌のまま維持し、ニーチェの言葉を盾に取る。
第二部:理性と身体の悲劇的な不調和:精神崩壊の哲学的な教訓
ニーチェが晩年に迎えた精神錯乱は、彼が説いた「超人」の思想と、彼自身の身体的・心理的な現実との間に、回復不可能なほどの不調和(ディスコヒーレンス)が存在していたことを示唆する。この悲劇は、知性だけで人は救われないという実存的な教訓を含んでいる。
3.1. 哲学者の病:知性至上主義と感性の欠落
ニーチェは、著作の中で、感情や本能を切り捨てた「理性の在り方」を批判していた。彼は、知性(アポロン的)と本能(ディオニュソス的)の統合こそが、創造的な生を可能にすると考えた。
しかし、彼自身の生涯を見ると、理性を徹底的に使い、世界や神を批判する一方で、その過程で、自己と世界との「ズレ」を強烈に自覚し、孤立・孤独・矛盾を内面に抱え込み過ぎた。
彼の悲劇は、「頭(理性・知性)だけが過剰に働き、心(感性・共感・身体感覚)が置き去りになった結果」とも言える。彼は人間関係において極めて不器用であり、ルー・サロメへの失恋や突発的な求婚といった哀しい逸話が示すように、現実を生きることが非常に下手であった。実存的な不安と矛盾を自己の内に取り込み過ぎ、他者や身体感覚との共感・交流(感性)を失ったことが、知性の孤独を極限まで深め、最終的なメンタルと肉体のバランス崩壊に繋がったと考えられる。
3.2. 晩年の病因論:神経梅毒からCADASILへの診断論争
ニーチェが発狂した原因については、長年にわたり学術的な論争が続いている。晩年のニーチェは、「自分こそが神だ」という妄想や自我の崩壊といった症状を示した。
従来の有力説は、当時一般的だった「神経梅毒」(General Paralysis of the Insane, GPI)による進行麻痺であった。しかし、近年の研究では、この診断を裏付ける確固たる証拠が不足しているという指摘が増えている。
代替的な説として、遺伝性疾患である「CADASIL」(皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症)が提唱されている。研究者たちは、CADASILがニーチェの病気の全ての兆候と症状を説明できると論じている。ただし、19世紀後半には検査手段が限られていた為、確実な診断は不可能であり、当時の診断的偏見(バイアス)も考慮すると、依然として非定型的なGPIが最も可能性の高い診断であるとする見解も残されている。
この病因の不確定性は、哲学的な解釈の余地を広げる。もしCADASILのような純粋な遺伝性疾患であったならば、彼の苦悩は避けがたい「運命の必然性」そのものであり、彼が教えた「Amor Fati」の最高の、そして皮肉な試練となったであろう。一方、もしそれが神経梅毒のように避けられたかもしれない原因であったならば、それは「知性の孤独」や身体的放縦がもたらした自己崩壊という、より教訓的な意味合いを強めることになる。
| 医療診断の論争点:ニーチェの晩年の病因 | |
| 診断名 | 特徴と研究状況 |
| 神経梅毒 (GPI) | 進行麻痺、精神錯乱。証拠不足ながら当時一般的だったため有力説として残る。 |
| CADASIL | 遺伝性疾患、症状を全て説明可能とする説がある。 |
3.3. 心身相関理論とコヒーレンスの重要性:ハートマス研究所の知見
現代の神経科学や心身相関理論は、心臓と脳の関係、すなわち「コヒーレンス」(調和)の重要性を強調する。これは、ニーチェの悲劇的な結末を解釈する上で極めて重要な視点を提供する。
心臓は、単なるポンプではなく、感情を感知し、脳に情報を送る複雑なネットワークの中心であるとされている。心臓から脳へ送られる情報量は、脳から心臓へ送られる情報量よりもはるかに多いことが示されており、心臓は脳よりも先に「感じている」という認識が広まっている。
この理論によれば、「心(ハート)」が整っていない状態では、脳の思考も整わず、結果として現実創造も歪むことになる。生理学的コヒーレンス(調和)は、心拍変動(HRV)のパターンが比較的調和的なサイン波状の信号を示すことによって評価される。このコヒーレンスが増加すると、他のシステム(呼吸、血圧、脳リズム)が同期し、より効率的な機能へと移行する「周波数引き込み」(Frequency Pulling and Entrainment)という現象が生じる。システムが有意義な機能を果たす為には、「グローバル・コヒーレンス」の特性を持つことが必須とされる。
ニーチェの生涯に見られた内面の矛盾、孤独、怒り、そして現実生活での不器用さは、彼のサイコフィジオロジカル・システムにおける「コヒーレンス」を長期的に崩壊させたと考えられる。
彼は哲学的に最高の統合(Amor Fati)を目指しながら、その実現に必要な生物学的に最も基本的な統合(心身の調和)に失敗した。彼の悲劇は、「知性」が「身体/ハート」を支配しようとした結果、生命システム全体の「グローバル・コヒーレンス」を失ったことによる、避けられない崩壊であったと解釈される。
第三部:「思考の現実化」論へのニーチェ的批判
現代のスピリチュアル界隈で語られる「思考は現実化する」という主張は、ニーチェの思想と表面上類似しているように見えるが、その根底にある「意志」の性質において、決定的な差異が存在する。ニーチェの思想は、受動的な「引き寄せ」の概念に対する厳格な批判を提供している。
4.1. 波動、エネルギー、現実創造:スピリチュアル概念の哲学的基礎付け
「全ては波動で出来ている」というスピリチュアルな観点は、現象学や量子力学的な解釈によって支持されることもあるが、哲学的考察においては、「波動」という物理的あるいはエネルギー的概念よりも、人間の「意図(意志)」の役割が重要となる。
ニーチェは、生の本質を「力への意志」で見出そうとした。これは、単なる願望の実現や、幸福を追求する欲望ではなく、生成変化する「生」そのものを肯定し、自己を超克し、既存の価値を超えて新たな価値を創造しようとする、根源的な衝動であり動的なエネルギーである。
4.2. 「力への意志」と受動的「引き寄せ」の決定的な差異
現代のスピリチュアル論の一部が説く「宇宙に委ねれば上手くいく」といった受け身の考え方は、ニーチェが求めた「力への意志」とは真逆である。ニーチェの哲学は、「苦悩を肯定し、自己を超えていく力」を強調する。
真の「思考の現実化」は、自己の苦悩や混沌(ノイズ)を否定したり、そこから逃避したりすることではなく、それらを力に変えて秩序を再構築する意志の行為として理解すべきである。ニーチェの哲学が音楽であるならば、それは「ノイズ」に近い。無秩序のように聴こえるが、その奥には再構築された秩序がある。
受動的な「引き寄せ」は、現在の苦難から解放されることを目的とするが、ニーチェの「力への意志」は、苦難そのものを生命力の源泉として受け入れ、自己の混沌を創造的なエネルギーとして燃焼させる能動性を要求する。したがって、ニーチェの思想は、現実創造における「能動性」と「厳しさ」を強調する、徹底的に厳格な哲学である。
4.3. 哲学と処世術の峻別:真理の探求と「すぐに役立つ答え」の誘惑
哲学の目的は、処世術とは異なり、「すぐに役立つ答え」を与えてくれることではない。哲学とは、真理を探す知的営みであり、その本質は「問い続ける姿勢」にある。処世術が特定の状況に対応する為の技術を提供するのに対し、哲学は、時代や流行に左右されない目線、物事の本質を見極める力、そして誰かの言葉より自分の内なる声を信じる姿勢といった、どんな時代でも通用する芯となる自分(超人の精神の根底)を育てる力を与える。
ニーチェの言葉を都合よく切り取り、人生を「楽」にする為に使用する人々は、結局のところ、彼が批判した奴隷道徳的な価値観に囚われている。彼らは、自己の混沌に飛び込み、自ら価値を創造するという厳格な義務から逃れ、他者が用意した「札」に依存している為である。
第四部:魂の旅路と「成仏」の多層的な解釈
根源的な問いである「ニーチェはちゃんと成仏したのか?」という問いに答える為には、「成仏」を単なる宗教的な安寧として捉えるのではなく、魂がこの世に残した影響と、自己の生を完了できたかという実存的な視点から多層的に解釈する必要がある。
5.1. 東洋哲学における「成仏」:未練の解消と霊的役割の完了
東洋思想、特に仏教における「成仏」とは、悟りの達成、あるいは未練や執着からの解放による魂の浄化、そして安寧の獲得を意味する。
ニーチェの最晩年を霊的観点から見ると、彼は約10年間、精神錯乱の状態にあり、言葉も交わせず、妹に囲われた「自己表現出来ない地獄」にいたとされる。彼は、その著作とは裏腹に、自己の存在を完全に肯定する「納得」の状態で死ねたとは考えにくい。
この「自己否定」「怒り」「創造性の封じ込め」といった要因は、魂に重い荷を残す要因であり、初期においては「未成仏」の状態であった可能性が高い。
5.2. 思想の継続的な影響力による魂の昇華説
しかし、「成仏」を魂の安寧だけでなく、「霊的な役割の完了」として捉え直すことで、異なる結論に至る。ニーチェの言葉や思想は、死後も多くの人に読み継がれ、20世紀思想、文学、アート、そして実存主義に決定的な影響を与えた。特に「自己超克」や「神の死」といった彼の核心的な問いは、現代社会においてもなお、人々の深層に影響を与え続けている。
誰かが本気で悩み、虚無に直面した時、「それでも生を肯定せよ」と囁くような彼の哲学は、時代を超えて機能し続けている。魂がこの世に何らかの影響を与え続けること、すなわち「霊的な役割を果たし続けている」ことは、一種の浄化作用として働く。
この視点から見れば、ニーチェは死後しばらくは未成仏の状態であったとしても、現代においては、その継続的な影響力と、思想の持つエネルギーを通じて「すでに昇華(成仏)している」と見る方が自然である。彼の魂の安寧は、超越的な静寂ではなく、永続的な「力への意志」の呼びかけという形で達成されたと考えられる。
5.3. 対照としてのルドルフ・シュタイナー:宇宙的カルマと転生観
ニーチェの「成仏」を考察する上で、同時代の思想家であるルドルフ・シュタイナー(Rudolf Steiner, 1861-1925)との対比は興味深い。シュタイナーは、人智学の創始者として、人生を宇宙的秩序の元に観察し、人間のカルマは宇宙を貫流する霊的なカルマによって規定されていると説いた。
シュタイナーの思想は、生と死、病気、事故、そして転生を、不可視の霊的因果律(カルマ)を通じて壮大なスケールで解明する。彼によれば、人間は誕生と死の間の地上生活と、死と新しい誕生の間の天の生活からなる全人生を生きる。この天の生活、すなわち死と新たな誕生の間の期間において、魂は超感覚的な諸世界(惑星天球)を旅し、次の地上生で成就すべきカルマを形成し、過去の悪を清算するとされる。
ニーチェが「神の死」を宣言し、「この生」の絶対的肯定(内在への回帰)を追求したのに対し、シュタイナーは「霊的宇宙秩序」と「転生」を通じて救済の道を示した(超越への拡大)。ニーチェが意図的に切り捨てた「超越的な救済の枠組み」の不在は、彼の「成仏」が、シュタイナー的なカルマ解消による安寧ではなく、徹底的に内在的な(生への完全な肯定としての)昇華でなければならないことを示唆している。
| ニーチェ(内在的肯定)とシュタイナー(超越的秩序)の比較 | |
| 比較項目 | フリードリヒ・ニーチェ |
| 価値創造の場 | 現世、この生の混沌(力への意志) |
| 救済の概念 | 自己超克、運命愛 (Amor Fati) による内在的肯定 |
| 人生の課題 | 価値の創造、ニヒリズムの克服 |
| 焦点 | 知性、意志、身体(ディオニュソス的) |
第五部:感情の階層モデルによるニーチェの存在論的分析
現代のスピリチュアルな教えの中で、感情のエネルギー振動レベルを示すモデルは、ニーチェの思想と現実のギャップをより明確に位置付ける為のツールとなる。エイブラハム・ヒックスが提唱する「感情の22段階」は、感情を最も低い段階(悲しみ、罪悪感)から最も高い段階(喜び、愛、至福)に分け、私たちが望む現実にどれだけ近付いているかを示すバロメーターとする。
6.1. エイブラハム・ヒックスの感情の22段階モデルの概要と適用
このモデルにおいて重要なのは、感情のエネルギー順位である。例えば、自己否定や罪悪感(7位)は、怒り(5位)よりも低いエネルギー振動を持つと定義される。これは、自分を責める自己卑下の状態よりも、外側に向けた怒りの感情を表現する方が、まだ次のステップへの移行エネルギーとして機能しやすいことを示唆している。
ニーチェの思想が目指した「運命愛」(Amor Fati)は、この感情の22段階において、最も高いレベル、すなわち愛、感動、心の平和、歓喜、そして喜び(至福)(15位〜22位)に位置付けられる。この至福の状態は、自己と他者、そして世界の全てが調和している状態(グローバル・コヒーレンスが達成された状態)である。
6.2. 運命愛(最高段階)を目指した哲学者と、低位感情に囚われた現実の男
ニーチェの哲学は、人間の魂のエネルギーを最高段階に引き上げる為の壮大な理論的装置であったが、彼自身の私生活は、その理論を肉体的に支えることが出来なかった現実を示している。
| ニーチェの生涯の段階 | 代表的な感情状態 | 22段階における推定位置 | 哲学的な対応概念 |
| 晩年期の狂気 | 悲しみ、無力感、自己否定 | 1〜8段階 (最低位) | エゴの極限的な喪失 |
| 著作活動期の初期 | 失望、孤独、怒り | 2〜5段階 (低位) | 奴隷道徳への反発(獅子の初期段階) |
| 『ツァラトゥストラ』最終境地 | 愛、心の平和、歓喜、至福 | 15〜22段階 (最高位) | 運命愛(アモール・ファティ) |
ニーチェの不器用な人間性(失恋、女性蔑視的な発言)は、彼が私生活において、失望、嫉妬、怒りといった低位から中位の感情に囚われやすかったことを示唆している。特に彼の著作にたびたび登場する女性蔑視の言葉は、ルー・サロメへの未練や、自己の人間関係における不器用さから生じた、低位感情(失望、嫉妬)の歪んだ表現であった可能性が高い。中島義道氏が「ニーチェ哲学の中で、最も読む価値のない部分だ」と切り捨てたこの部分は、彼の「心(ハート)」のコヒーレンスが乱れ、理性的な知性をもってしても制御しきれなかった感情の歪みとして解釈出来る。
6.3. 「超人」の精神の根底にあるもの:感情を力に変える意志
ニーチェの悲劇は、「知性だけでは人は救われない」という教訓を提供する。真の超人の精神は、感情の低位段階(悲しみ、怒り)を否定するのではなく、それらを力に変えて自己を超える為のバネとして利用する「昇華のプロセス」を要求する。
哲学の真価は、理論として最高段階(運命愛)の在り方を提示し、現代人(特に低位段階にいる者)に対して、その混沌と苦悩を否定するのではなく、それをエネルギー源として受け入れ、自己を超えていく為の指針(エネルギー転換の指針)を与えた点にある。彼が批判したのは、感情を切り捨てた理性であり、彼が求めたのは、知性と感性(心)を統合し、心・体・魂を調律する行為としての哲学であった。
結論:混沌の中の秩序と、真の自己統合の哲学
7.1. 哲学は「問い続ける姿勢」:時代を超えて自己を育てる力
ニーチェの功績は、伝統的価値観が失墜し、「全てがどうでもいい世界」(ニヒリズム)において、それでも生きる理由を問い続けたその姿勢そのものにある。彼の哲学は、現代の知的探求者に対し、時代や流行に左右されない目線、物事の本質を見極める力、そして自分の内なる声を信じる姿勢こそが、「超人」の精神の根底であり、自己を育て続ける力であることを示している。
7.2. 現代人への提言:知性、心、身体のコヒーレンスを求めて
ニーチェの悲劇的な結末は、現代人にとって重要な教訓を提供する。それは、知性、感性(心)、そして身体の三位一体的な統合(コヒーレンス)が、強靭な「在り方」を確立する為に不可欠であるということである。頭(理性)が心(感性)を無視し、身体感覚(本能)を置き去りにした結果、哲学的な理想は、生物学的な現実によって崩壊した。
真の自己統合(セルフ・マスタリー)とは、ニーチェが目指した通り、知識や理論だけでなく、心身の調和(ハート・コヒーレンス)を保ち、自己の運命の混沌を愛し、肯定出来る「在り方」を確立することに他ならない。
7.3. 最終的な成仏の評価
ニーチェの「成仏」に関する最終的な評価は、次の二つの要素の統合によって導き出される。
- 肉体的・精神的な完了の欠如:最晩年の精神崩壊は、彼が自己の生を完全に納得して完了させたとは言えない状況(未練と自己表現の封じ込め)を示唆しており、個人的な安寧としての成仏は達成されなかった可能性が高い。
- 霊的役割の継続的な完了:彼の思想が死後も人類の集合意識と個人の実存に与え続けた強い影響力は、「それでも生を肯定せよ」という霊的な役割を果たし続けている証拠である。
したがって、ニーチェは、超越的安寧としての静寂な「成仏」は得られなかったかもしれないが、彼の魂は、永続する「力への意志」の響き、すなわち内在的な意味での昇華を果たしたと結論付けられる。彼の存在は、哲学が「心・体・魂」を調律する行為になって初めて本当の力を持つという、偉大な教訓を後世に残したと言える。